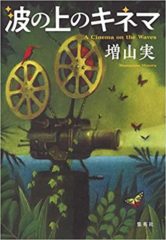「読書の秋」です。本、読んでますか?
本記事では、毎日Twitterで読んだ本の短評をあげ続け、読書量は年間1000冊を超える、新進の歴史作家・谷津矢車さんに、この秋に読んでほしい本10冊(+α)を選んでもらいました。ハードな人文書からエンタメ、ミステリ、ラノベからマンガまで全ジャンルを網羅。
必ず読みたい本が見つかるはずです!
すみなすものは 書物なりけり
高杉晋作が死の間際に辞世の句として「おもしろき こともなき世を おもしろく」と詠んだところで力尽き、野村望東尼という女性勤王家の読み継いだ下の句「すみなすものは 心なりけり」を見て「面白い」と口にして息絶えた、という逸話がある。この話の真偽はさておくにしても、この上の句は非常によくできている。下の句次第で歌い手の人生観が浮き彫りになるからだ。
さて、皆さんはどんな句をひねるだろうか。ちなみに、わたしは以下の通りである。
「すみなすものは 書物なりけり」
本はいい。無知なる自分を知ることができる。世界がとんでもなく広いのだと気づかされる。そして、本を読んでいる間だけは世界とつながったつもりになれる。
と、本を書くすべての著者、一冊の本を世に出し届けてくれるまでに尽力してくださっている皆様に感謝を捧げつつ、わたしの本棚から、今年わたしが出会った中で特に感銘を受けた本の一部を紹介したいと思う。
物事を俯瞰して眺める2冊
「津波の霊たち 3.11 死と生の物語」「ホモ・デウス(上下)」
まずはこちら「津波の霊たち 3.11 死と生の物語」(リチャード・ロイド・ハリー・著、濱野大道・訳/早川書房・刊)である。記者として二十年あまり日本に住み続けた英国人の著者が、東日本大震災の取材を通して見たもの、感じたものを描き出している。本書は大震災関連の本として出されているが、著者の視点のゆえか、震災ルポに留まらず、非常に深いところにまで切り込んだ日本社会論になっている。震災という非日常によって浮かび上がる日本列島に住む人々の心性を目の当たりにした時、わたしたちが普段意識しない不文律に影響される存在なのだと知るよすがになるだろう一冊である。
次に紹介するのは「ホモ・デウス(上下)」(ユヴァル・ノア・ハラリ・著、柴田裕之・訳/河出書房新社・刊)。あの「サピエンス全史」で全世界を驚かせたビッグヒストリーの旗手による待望の新刊である。人類を生物学的視点からとらえ、前著で歴史を読み解き直して見せた著者が、今度は人類種の大きな未来像を想像しようという試みである。もちろん、本書が描き出すような未来に向かうかどうかは誰にも分からないところだが、非常に読み応えのある一冊であるとともに、「物事を俯瞰して眺める」という作業の大切さもまた思い起こさせてくれる。
境界線を見つめる4冊
「君のいない町が白く染まる」「宝島」「波の上のキネマ」「凍てつく太陽」
さて、ハードな二冊が続いてしまった。お次は小説に行こう。「君のいない町が白く染まる」(安倍雄太郎・著/小学館キャラブン!・刊)である。主人公がひょんなことから幽霊の女の子・アカネと出会うことから始まる恋愛小説だ。漫画などではままある設定だろう。しかし、登場人物たちの感情を切り分ける力と確かなプロット力によって独自性を切り開くという新人離れした手腕をいかんなく見せつけてくれる(言い忘れたが、著者は本書がデビュー作)。実に今後が楽しみな作家が誕生したといえるだろう。なお、著者の安倍さんは二作目の小説「僕の耳に響く君の小説」(同じく小学館キャラブン!)を上梓している。こちらもチェックだ。
どんどん行こう。ここのところ、小説の世界では“境界線”を扱う小説が目立ち始めている。それが証拠に、わたしが読んだ範囲でも、優れた“境界線”小説がいくつもある。「宝島」(真藤順丈・著/講談社・刊)、「波の上のキネマ」(増山実・著/集英社・刊)、「凍てつく太陽」(葉真中顕・著/幻冬舎・刊)などがそうである。「宝島」「波の上のキネマ」は沖縄の近現代を、「凍てつく太陽」は北海道の近現代を舞台にした“境界線”小説である。日本史上において、沖縄と北海道は国境という名の境界線近くに位置するがゆえに各国の思惑や帝国主義に蹂躙されてきた。ここで紹介する三冊の本は、そういった“境界線”に舞台を置きながら、三者三様に想像の翼を広げ、全く違うテーマ――「宝島」は沖縄の人々の魂を、「波の上のキネマ」は物語の意義を、そして「凍てつく太陽」はエンターテイメントを、読者に突きつけてくる。この三つの本を読み比べ、作家ごとの問題意識やテーマの違いに思いを致すのも面白いだろう。
ネットスラングを話すマリー・アントワネット、異世界で娼婦になるJK
上記三冊もそうなのだが、ここのところ、現代小説家の歴史小説が存在感を放っている。その中でも独特の輝きを見せつけた本と言えばこちら「マリー・アントワネットの日記(Rose/Bleu)」(吉川トリコ・著/新潮社nex・刊)である。名前の通り、マリー・アントワネットの日記という体裁を取っているのだが、何と本書のアントワネットはギャル語・現代語・ネットスラングを多用するのである! けれど、この軽妙、軽薄な語りが200年以上前のブルボン朝と現代のわたしたちを橋渡ししてくれるとともに、歴史のヴェールに隠された実在の人物であるアントワネットを、血の通う一人の女性として読者の目の前に引き出してくれるのである。いちいちフランス流のしきたりに反発するアントワネットの姿に、会社や組織の虚礼に反感を抱く自分自身とを重ね合わせ、うんうんと頷く読者の方も多いはずである。
取り合わせの奇抜さという意味では、「JKハルは異世界で娼婦になった」(平鳥コウ・著/早川書房・刊)にも度肝を抜かれた。女子高生のハルが異世界に飛ばされて娼館で働き始める……というタイトルそのままの小説であり、いわゆる「なろう系」に属する小説なのであるが、本書は普段当ジャンルに親しんでいる人ほど衝撃を受けることであろう。「なろう系」の持つお約束や共通設定を逆手に取り、体一つで異世界を生き抜いてやろうと決心するハルの姿は、「なろう系」の生んだ異色の主人公像と言えるだろう。ただし、本書は扱うテーマがテーマだけに読み手を選ぶ。その点だけご注意願いたい。
新選組の女、大人vs子どもの知恵比べ、日本最後の忍者……
今年、個人的に一番引き込まれた歴史小説はこちら、「火影に咲く」(木内昇・著/集英社・刊)である。幕末の維新志士や佐幕派武士たちの「影」に息づく女たちの姿にスポットライトを当てた一冊である。「新選組 幕末の青嵐」や「地虫鳴く 新選組裏表録」(いずれも集英社)といった優れた新選組諸作でも知られる著者らしく、細やかに、時には大胆に幕末の志士と女の関係が描かれてゆく。この本を手に取られたあなたは、是非とも著者の筆の冴えに酔いしれていただきたい。なお、本書はかなり昔の短編も採録しているため、著者の歩みを俯瞰する一冊でもある。これまで木内作品に触れて来なかった方にもお勧めである。
「夏を取り戻す」(岡崎琢磨・著/東京創元社・刊)も良かった。これまで著者はお店を舞台にした連作短編を世に問われてきたが、本書ではその二つを取り払い、団地で起こった狂言誘拐事件を追う大人の記者たちと、誘拐事件をでっち上げた団地の子どもたちとの知恵比べを扱った。しかし、調べが始まるうちにこの団地を巡る様々な事情が浮かび上がり、また過去のある出来事が……。ミステリ作品でこれ以上のネタを明かしてしまうのは野暮というものゆえ口をつぐむが、大人の目に見えない、子どもの世界の力学を巧みに用いてストーリー構築をしてみせた。著者の新境地である。
最後は漫画から。「シノビノ(1~6)」(大柿ロクロウ・著/小学館・刊)である。幕末期にペリー艦隊を内偵したとされる実在の忍び甚三郎が、幕末の動乱の只中で忍び働きをするという筋の漫画だが、本書の良さはとてつもない「歴史離れ」ぶりである。ペリー提督や吉田松陰、新選組メンバーなどの実在の人物がバンバン出てくるのだが、少年漫画という枠組みに合わせてキャラクター構築されながら、最終的に歴史との平仄を合わせてくる。だが何より本書の美点は、「忍び」「武士」という幕末期においては滅びゆく存在を主人公側に配置したことで、幕末維新という時代の心性を描き出したところにある。全六巻。秋の夜長に読んでみてはいかがだろうか。
と、十冊(+α)紹介してみたが、まだまだ紹介し足りない。この世の中には、素晴らしい本が満ちあふれている。あなたの「面白きこともなき世を面白く」してくれる本だってきっとあるはずだ。
皆さんが下の句に「書物なりけり」とつけてくださる日が来たならば、書痴の端くれとしては非常にうれしい。
【プロフィール】
谷津矢車(やつ・やぐるま)
1986年東京都生まれ。2012年「蒲生の記」で歴史群像大賞優秀賞受賞。2013年『洛中洛外画狂伝狩野永徳』でデビュー。2018年『おもちゃ絵芳藤』にて歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞。