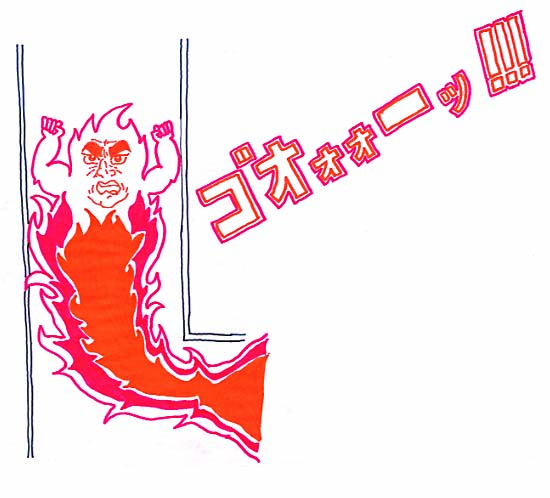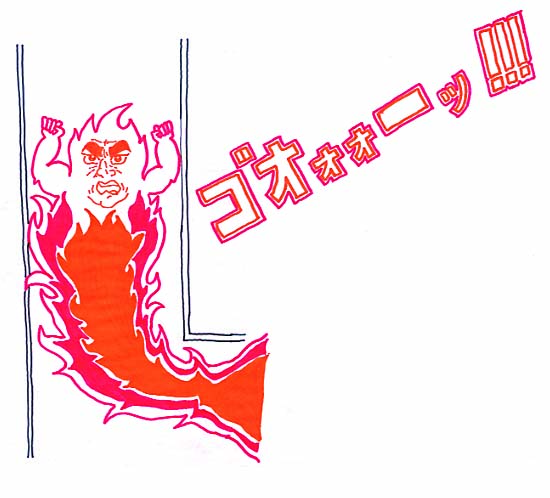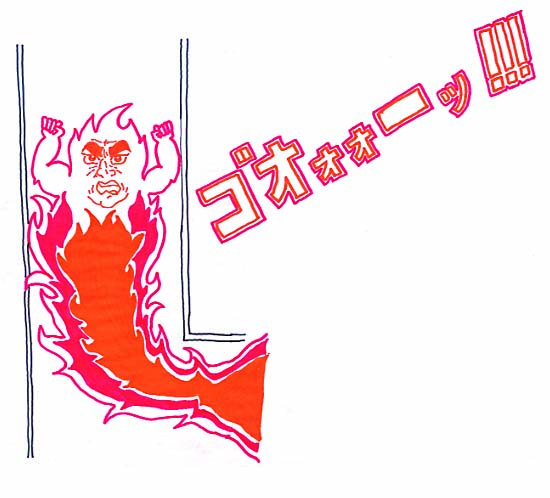本格的な炭焼きといったら、巨大な窯を作り、幾日も見張っていなきゃいけないものらしいが、ここではペール缶を使った超スモールバージョンに挑戦。しかも1日で片をつけてしまおうという安直なプランだ。これなら煙さえ出せる環境があれば、誰でも手軽に炭焼きが可能…なはずなのだが、果たしてそう上手くいくのかどうか!?
[用意した材料]
ペール缶(フタ付き)、薪ストーブ用煙突(直筒/T笠106mm径)、赤レンガ、丸太(コナラ)、薪、土
[用意した道具]
ディスクグラインダー(金属用切断砥石)、スコップ、シャベル、マジック、トーチバーナー、火ばさみ、うちわ、燻製用温度計
窯前あたふた劇場 ~「窯止めは突然に」の巻~
01 チャレンジャー豊田は、事前に炭焼き経験者の西田宏さんを訪ね、ささやかながら炭焼きについて勉強した 02-1 簡単炭焼き窯の主な資材は、ペール缶(ホームセンターで1000円で購入)と… 02-2 薪ストーブ用煙突(物置に転がっていた中古品) 03 ペール缶の底に煙突のT笠(T曲やエビ曲でも可)をあてがって、開口部の墨つけをする 04 ディスクグラインダーに金属用切断砥石をつけ、カット 05 こんな感じに 06 カットした部分を折り曲げ、煙突を差し込んでみる。問題なし 07 フタの一部も開口する 08 穴を掘り、煙突をはめたペール缶を置く。穴の長さはペール缶&煙突の倍くらいにした 09 ペール缶にぎっしりとコナラの丸太(直径70mm前後)を詰める。できるだけすき間がないほうがいい 10 ペール缶のフタをする 11 レンガをこのように配置して窯口を作る 12 土をかぶせる。これで炭焼き窯の完成 13 12時30分:窯口に薪を置いて着火 14 うちわであおいで薪を燃やす。窯の中が見えないので非常にサグリサグリ… 15 煙の温度が窯内の状態を読む目安になる。70〜80℃で安定していれば炭化が進行していると考えていいようだ。触ってもイマイチわからんね 16 燻製用の温度計で測ってみた。なんと80℃。イイんじゃない? 17 煙の色や匂いも重要な情報。炭化が進行しているときは、白くてツンと刺激臭のする煙がモクモク上がるはず。刺激のあるような、ないような…。鼻づまり気味なので… 18 13時30分:窯口を半分ふさぐ。炭化が始まったら、空気の流入量を減らし、じっくり燻すと聞いたため。白い煙がモクモクと上がり続けるので、炭化進行中と判断 19 それにしても窯内が見えないので非常に心許ない。そわそわしてしまう。窯ん中、どーなってんだろ? 20 そうこうしているうちに煙がだんだん茶色くなり、炭材が燃えているような匂いもしてきたので、窯口を完全にふさいで空気の流入を止めることに。こ、これで大丈夫かな? 21 大丈夫じゃなかった! 窯口をふさいで少ししたら、ゴォーッという音が聞こえ、煙突をのぞくと真っ赤な火柱が!*再現イメージイラスト 22 オーマイガァッ!!大急ぎで煙突にレンガを載せる 23 14時:意図とは違い、窯口と煙突をふさぐことを強いられた。すき間から白い煙が漏れる。いったい、どうすればいいのだろう? 24 15時:なす術を知らず、ヤケクソ気味に窯止め(窯を完全にふさいでしまうこと)。すべて土で埋めてしまった 25 翌7時:窯口を掘り出す。実はまだ微かな希望を持っている。ドキドキするぜ 26 いざ窯出し!うっ! 27 そりゃそうだろ、という声が聞こえてきそうだが……生焼けだった。ガビーン 28 右が最も生焼けだったもの。左が最も炭に近かったもの。この経験を次に生かすべし… *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます
窯前あたふた劇場 ~「あきらめずに煙を見よ」の巻~
01 いざセカンドチャレンジ。コナラの丸太をぎっしり詰める 02 前回と違うことを試してみようと、小枝を詰めて、できるだけすき間を埋めてみる 03 窯口を延ばしてみる。薪から窯までの距離をあければ、炭材が燃えにくくなるかなぁ、という考え 04 9時30分:薪に着火。すぐに白い煙が上がり始める 05 あれれ?煙が透明になってきた… 06 なんと!炭材が燃えている!*再現イメージイラスト 07 10時10分:まさかの窯止め。早過ぎる終戦… 08 って、終わるわけにはいかないでしょ。まだ午前中だぜ。確かにしばし呆然としたけど、絶望の淵からなんとか舞い戻り、煙突に詰めた土をかき出す。立て、立つんだ、俺! 09 まだ炭材はしっかりと形を留めている。再チャレンジだ 10 今度は窯口を短く、狭くしてみる。長い窯口が煙突効果を生んで、火を窯の中に引っ張り込んだのかもしれない 11 10時50分:復活。今度は片手にうちわ、片手に火バサミで、慎重に火力を調節する。失敗を経て、人は成長するのだ 12 ところが全然成長していなかった!またしても火が!*再現イメージイラスト 13 11時30分:再び窯口と煙突をふさいで消火。くぅ〜、ぐやじぃ〜 14 11時35分:なにげなく煙突のレンガを少しだけずらしてみると、炭化が進行しているときのような白い煙がイイ感じに噴き出した 15-1 窯口にも煙突にもわずかなすき間しかない状態で、白い煙が出続けている。このとき煙の温度は65℃ほど 15-2 窯口にも煙突にもわずかなすき間しかない状態で、白い煙が出続けている。このとき煙の温度は65℃ほど 16 はっきり言って窯の中の状態はよくわからないが、白い煙が出ているうちは、ひたすら待つことに決めた。うまく炭化が進んでいるなら、そのうち煙の色がだんだん透明になってくるはず。それにしても、H.D.ソロー君はイイこと言うなぁ… 17 いろんなところから微かに煙が立ち始めたので、土を盛って煙を止めてみた。煙突のすき間はさらに狭くした。まさか燃えてんじゃねーだろーな? 18 煙の温度は75℃で安定している 19 1時間、2時間、3時間……煙を見つめながら、ひたすら待つ。終わりは来るのだろうか…… 20 15時30分:白い煙がだんだん薄くなってきた 21 16時30分:窯止め。最終的に復活してから約5時間。初めてのマトモっぽい窯止め 22 窯出しは後日。これでどうよ?どうなのよっ!? 23 翌朝、窯を掘り出し、フタをオープン!おっ!? 24 こ、これは、炭じゃないかっ!? 25 どこからどう見ても、確かに炭ができている! 26 とりあえず、ひとしきり歓喜の舞い!すーみーがでっきたー♪おーれーがやっいたー♪ 27 できた炭を使ってみる。タンドール窯(後述のリンク参照)に入れて着火。火のツキは悪くなさそうだ 28-1 火力もバッチリ 28-2 「いい仕事するじゃな~い」と、タンドール窯を作ったナマステ設楽も脱帽(&着ターバン) 29 完!エッヘン! *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます
タンドール窯作りの記事はこちら!
今回のまとめに代えて…
「とはいえ、DIY炭焼き道は始まったばかりだ!」
2度も炭材に着火しながら、偶然にもその後の調整がうまくいき、なんとか炭ができた。この経験を踏まえて推測するのは、「そもそもペール缶の窯に対して106mm径の煙突は太すぎるのでは」ということ。最初からレンガでふさいで煙突を絞り、ゆっくり時間をかけて炭化を進行させたほうがよさそうだ。といっても、炭焼き職人じゃあるまいし、これは全然推測の域を出ない。きっと、ちょっとした条件の違いでも仕上がりが左右されるだろうし、試行錯誤を繰り返しながら自分なりのコツをつかむしかないのだろう。でもそんなふうにトライすることこそ、DIY炭焼きの醍醐味であることは間違いない。だって実際、失敗も込みで、すげえ面白いんだもん。
 実はその後、こんな大失敗も。夜中までイイ感じで煙が出ていたので窯止めせずに寝てしまったら、翌日、窯の中にはこれっぽちの灰が残るだけ…。やっぱり放ったらかしは禁物です…。チキショ~
実はその後、こんな大失敗も。夜中までイイ感じで煙が出ていたので窯止めせずに寝てしまったら、翌日、窯の中にはこれっぽちの灰が残るだけ…。やっぱり放ったらかしは禁物です…。チキショ~