ビートたけしの『フランス座』(文藝春秋・刊)は、著者が体験した事実をもとに描いた青春物語だ。そこには、今や知らぬ人はいないビートたけしの知られざる若き日々が、「こんなこと書いて大丈夫なのかな」と思うほど、正直に率直に、そして激しく描かれている。

ビートたけしの青春
ビートたけしが回想する日々は、私が過ごした日々と共通する部分も多い。とりとめがなく、ただひたすらに苦しく、明日、自分はどうなっているのだろうという不安に満ちた毎日。20歳前後の若者は、どんな時代にあっても息苦しい状態に耐えながら、将来への夢を無理矢理に作り出しとりあえずどこかに向かおうとする。
ただ、ビートたけしの場合、特殊なのはそれが浅草のエレベーターの中で培われたものだということだ。
知っているつもりだったが…
ビートたけしが浅草のフランス座出身だということは知っていた。けれども、彼が浅草に行ったのは、コメディアンになるための修行のためではなく、エレベーター番というアルバイトをするためだったということは、知らなかった。彼は「コメディアンになってみせる」というという熱い思いを果たすべく、周囲の反対を押し切って浅草に出向いたのだと私は思い込んでいた。
しかし……、彼は述懐する。
何故、フランス座のエレベーター番になったのか? 正直に言うと、大した理由はない。新宿から流れて浅草へ。流行の言葉ならドロップアウトということなのだろう。
(『フランス座』より抜粋)
強運を得る秘密
ツービートを結成後、漫才ブームにのって絶大な人気を誇った彼。テレビでその姿を見ない日はなかったころのことを私は今もよく思い出す。誰にも止めることのできない勢い。そして、漫才という枠を飛び越し『その男、凶暴につき』で映画監督としてのデビューも果たし、『HANA-BI』でベネチア国際映画祭金獅子賞を受賞するなど、世界の北野と呼ばれるようにもなる。
華麗なる経歴だが、一方で、写真週刊誌への殴り込みにより芸能活動を一時停止し、さらにはバイクの事故で重傷を負い、復帰は不可能だと報道されたこともあった。
しかし、彼は蘇る。その運の強さがどこから来るのか? 私には大きな謎だったが、『フランス座』によって、彼を取り巻く素晴らしい人たちが、彼を愛し育んできたからなのだと思うようになった。
母・北野さき
ビートたけしの母は、有名な方だ。この母ありてこの子ありという言葉を思い出させる。母への思いはまっすぐで、読むものを魅了する。
母親のことを考えると電話なんて出来ない。苦労して昼間はヨイトマケ、夜は酔った父親の暴力に耐えながら子供達の学費を作ってくれた母に、大学を辞めたなどと死んでも言えない。
その夜は寝られなかった。
(『フランス座』より抜粋)
さらに、窮地に陥ったとき、帰る先も母親のもとだった。
母ちゃんどうしてるだろう。急に家に帰りたくなった。怒られるだろうな、大学辞めちゃったし。俺、母ちゃんの顔見られるかな…。いつの間か東武線に乗っていた。
(中略)
関係ない事をどんどん喋るのを遮ると、悲しそうに母ちゃんは「まだお前の学費払ってんだよ、大学行きな!」と俺の手をぎゅっとつかまえた。
(『フランス座』より抜粋)
まさにこうありたいと思うような母親の姿がそこにある。
師匠の存在
ビートたけしが浅草仕込みの芸を持っているのは知っていた。タップダンスが上手なのもわかっていた。けれども、その芸を教えた師匠がいることを不覚にも私は知らなかった。
ファンの方には周知の事実なのかもしれないが、彼には師匠がいたのだという。深見千三郎という名のコメディアンで、皆に師匠と呼ばれ、尊敬されている人だった。ビートたけしのコメディアンとしての才能を見抜き、アドバイスをしたのも彼だ。
会ってわずか1週間後のこと、エレベーター番をしているたけしに師匠は声をかけたという。
「コメディアンは何でも出来なきゃしょうがねえぞ、お前も暇な時はタップとかギター、それか本ぐらい読んでろ」
(『フランス座』より抜粋)
たけしはその言葉を心の灯火として、それまで漫然とやっていたエレベーター番から、コメディアンを目指そうと考えるようになったらしい。
コントの台本も味わうことができます
『フランス座』は小説と銘打ってあるが、私はこの本を徹底的なドキュメンタリーとして読んだ。ところどころに、コントの台本がはさみこまれているからだ。私は子どものころから脚本を読むのが好きで、愛読書は脚本だと勝手に思っていたのだが、コントの台本を読んだことはなかった。
うきうきしながら読み始めた私は、ぎょっとした。正直に言うと全然おもしろくないのだ。いったいこの台本のどこで、お客さんは笑うのだろうとさえ思った。
何度も読むうち、コントは演じる側にそのすべてがかかっているのだろうと気づいた。台本には書いていない独特の間、コメディアンのひきつった顔、いきなり相方を殴りつける不可解さ。それらがすべて相まって、お腹を抱えて笑う作品となるに違いない。
もし、できることなら。
『フランス座』は単に有名な人物・ビートたけしの回顧録を小説化したものではない。そこに流れる暗さ、どうしようもない鬱屈、それでも前を向いて進もうとする若者達。そして、一読しただけではよくわからない台本を素晴らしい一度かぎりの舞台として昇華させる技術に私はうなった。新しい世界を知ったように感じた。
もし、できることなら、『フランス座』でとりあげたコントの台本だけを書籍化し、その台本を演じている彼の芸をDVDとして発売して欲しい。それがビートたけしを理解する一番の近道だろう。彼の笑いの本質が、いったいどこにあるのかわかるようになるに違いない。
【書籍紹介】
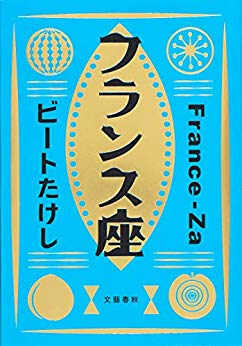
フランス座
著者: ビートたけし
発行:文藝春秋
「おいタケ!ちゃんとやってるか?」大学をドロップアウトしてストリップ劇場のエレベーター番になった俺を“コメディアン志望の若者”に変えたのは深見の師匠の一言だった。ビートたけしがついに描くあの日の浅草と師匠の物語。