夫に先立たれた妻を「未亡人」と呼ぶことは知っていた。では、妻が先に亡くなり取り残された夫を何と呼ぶのだろう。疑問に思っていたら、最近は男女を問わず「没イチ」と呼ぶのだと教えてもらった。高齢化社会を迎えた私たちにとって、「没イチ」後の生活をどう生きるかは大問題だ。夫婦が同時に死を迎えるのは、極めて希なケースであり、いつかはその日が来ると、妻も夫も覚悟しなければならない。

猛烈な妻を持った夫
『なにもできない夫が、妻を亡くしたら』(野村克也・著/PHP研究所・刊)は、妻を亡くした野村克也が、「没イチ」となった後の思いを正直に綴った「告白の書」だ。今さら言うまでもないが、野村克也は選手としてだけでなく、プロ野球4球団の監督を歴任し、独特の手法で選手を育て、チームを優勝に導くなど輝かしい功績を残している。評論家としても有名で、講演会の演者として引っ張りだこだった。
そして、何より恐妻家として知られ、妻のサッチーこと沙知代さんに頭が上がらないと自ら認めていた。日常生活では何もかも妻に頼り切りだったのだ。
著者がそんな妻の死にどんな風に向き合ったのか? 誰もが知りたいところだろう。私もそう思いながら、『なにもできない夫が、妻を亡くしたら』を開いた。そして、最初の1行で心をわしづかみにされた。
二〇一七年一二月八日──。
私は「ひとり」になった。(『なにもできない夫が、妻を亡くしたら』より抜粋)
「妻が亡くなった」とか、「妻が亡くなったのは、二〇一七年一二月八日だった」ではなく、私は「ひとり」になったと始まる。すさまじいまでの孤独を感じるオープニングで、このあと読み進もうかどうしようか迷ったほどだ。
沙知代夫人は、猛烈なキャラクターの持ち主として知られていた。かつては毎日のようにテレビに出演し、1996年には衆院選に立候補して、一躍、時の人となった。こうして華やかな取り上げ方をされる一方で、学歴詐称や脱税問題、周囲との激しい軋轢など、非難の矢面にも立たされた。夫である野村克也は良いときも悪いときも、妻の味方だった。裏切られたと知ったときでさえ、「自分には沙知代しかいない」とかばい続けた。
著者が妻に望んだことはただひとつ、自分より先に死なないで欲しいということだった。
自分から野球を取ったら何も残らない。自分の体は野球でできている、そう思っていた彼にとって、妻は何よりも頼りになる存在だった。彼は財布さえ持っておらず、必要なものはクレジットカードで買うように命じられていたそうだ。自分で稼いだお金が入っているのに、キャッシュカードの暗証番号さえ教えてもらえない。すべては妻が管理していたからだ。「あんたに渡すと女に使うと言われるんだよ」などとぼやきながらも、結局は受け入れていたところをみると、まかせておくほうが安心で安全だと思っていたに違いない。
野球界を引退してから、野村克也は日本全国で講演会を行う人気者だった。それも、妻の沙知代が仕事を引き受けては、「あんた、頑張りなさい」と、はっぱをかけ続けていたためだという。本来、口べたで人前で話すのは苦手だったそうだが、妻は「仕事が来るだけ有り難いでしょ」と言うだけだ。疲れるし、嫌だと思いつつも、講演を続けるうちに段々コツを覚えていった。そのうち、妻の言うとおりだ、仕事があるのは有り難いことだ、感謝しようと思うようになった。
このまま死ぬまで、妻の尻に敷かれて生きていこう。著者はそんな風に思っていただろう。そもそも、女性は平均寿命が男性より長い。まして、沙知代夫人は健康に問題もなく、人生を謳歌しているように見えた。それなのに……。
突然の別れ
別れは突然だった。
昼過ぎのことだった。リビングでテレビを観ていると、お手伝いさんがあわてたようにやってきて、叫んだ。
「大変です!奥さんの様子がおかしいです」。
驚いてダイニングに向かうと、朝食をとっていた妻が椅子に座ったままテーブルに頭をつけていた。(『なにもできない夫が、妻を亡くしたら』より抜粋)
最後の言葉は「大丈夫よ!」だったそうだ。救急隊員が駆けつけ病院に運ばれたが、亡くなってしまった。虚血性心不全による死だった。
あまりにも突然で看病する間もなく、妻の死を覚悟することさえできないままに、野村克也は妻を喪った。突然の、あまりにあっけない別れだった。
それでも、妙なことはあったという。昼ごろ、妻が突然「左手を出して。手を握って」と頼んだのだそうだ。滅多にそんなことを言わないので、戸惑いながら手首を握ったという。何か予感があったのかもしれないが、夫からしたら納得できない。
85歳という年齢ながら、元気いっぱいの妻。健康診断でも異常なしの妻。前夜も一緒にホテルで食事をしたばかりだ。そんな彼女が亡くなるなんて、誰にも想像できなかっただろう。
しかし、それは起こり、あとには突然「没イチ」となった野村克也が取り残された。あれほど「おれより先に逝くなよ」と頼んでいたのに。
もっとも、沙知代さんはその願いに素直にうなづいたりすることはなく、「そんなの、わからないわよ!」と答えていたそうだ。彼女は最期は「ピンピンコロリが理想」とも言っていたというので、理想通りの死を迎えたのだろう。
寂しくてたまらない
妻を亡くし、ひとり暮らしになっても、野村家には家政婦さんがいて、家事一般の世話をしてくれるため、実際の生活で困ることはほとんどなかった。加えて、息子さん夫婦が同じ敷地の中に家を建て、一緒に住んでいたので、何かと心強かった。
それでも、妻が亡くなった家で、著者は呆然としている自分を発見する。寂しいのだ。とにかく寂しくてたまらない。待っている人のない家に帰るのがつらい。それまで、特にいそいそと家に帰っていたわけではなかった。会話が多かったわけでもない。40年以上も夫婦をしていると、それほど話すことなどない。夫婦とはそういうものだろう。
野村家も表面上は、ふたりで暮らしていたときと変わらない毎日だ。しかし……。
同じ家のなかに彼女がいるかいないかで、まったく違うのである。顔は見えなくても、声はしなくても、同じ空間のなかに彼女がいることで、安心するというのか、心が休らいいでいたのだということを、ひとりになって改めて痛感した。
(『なにもできない夫が、妻を亡くしたら』より抜粋)
考えてみると、我が家も今年で結婚41年だが、たいした会話をしていない、どちらかが一方的に必要なことを話すだけだ。それも内容は業務連絡的なことが多い。最近は私が何か話しかけても、八割方「ちょっと待ってて。今忙しい」と、言われる。しばらくして、「何?」と聞かれても、今度はこちらが何を言うか忘れていたりする。いずれにせよたいした話ではなく、そのまま静かに日々は過ぎて行く。我が家でも、どちらかが「没イチ」になったとき、ひとりになるとはどんなことか、実感するのだろう。
没イチになってからの生き方
妻亡き後も、野村克也は一生懸命に生きた。
寂しさは克服できないままだったが、ひとりになってからは、何かあると妻ならどうしただろうと考えるようにした。さらには、これから先、自分がどう生きるかについても考えた。できることなら、仕事をしたまま逝きたい。それがひとりになった野村克也の生きる指針であり、「没イチ」としての生き方だった。そして、妻の死から2年2か月後、2020年の2月11日、野村克也は亡くなった。お風呂の中でぐったりしているのを発見され、すぐに病院に運ばれたものの、そのまま帰らぬ人となった。
『なにもできない夫が、妻を亡くしたら』には、ぼやきで有名だった故人特有のユーモアあふれる言葉が並んでいる。先に逝ってしまった妻に「なぜ置いていったのか」という悲しみをぶつけながらも、「良い奥さんだった」という感謝がつまっている。妻が生きているときには言えなかった言葉を綴ったラブレターのようだ。私たちは、ひとりになったとき、果たして互いにラブレターのような言葉を並べることができるのだろうかと考えてしまう。「没イチ」になった方はもちろんのこと、ふたりでいるのが普通だと思っている夫婦にも、様々な問いを投げかける本だと思う。
【書籍紹介】
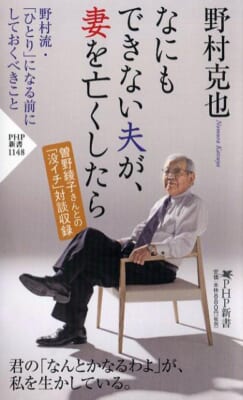
なにもできない夫が、妻を亡くしたら
著者:野村克也
発行:PHP研究所
2017年末、最愛の妻・沙知代さんが85歳で逝った。普段は財布も持たず、料理もしない「なにもできない夫」が、妻を亡くしたらどうすればよいのかー。「その日」はどんな夫婦にもやってくる。大切なのはそれまでに、支えとなる「ふたりのルール」を作っておくこと。野村家で言えば、それは「死ぬまで働く」「我慢はしない」「どんな時も『大丈夫』の心意気を持つ」などである。世界にたった1人の妻への想い、45年ぶりに訪れたひとり暮らし…。球界きっての「智将」が、老いを生きる極意を赤裸々に語る。巻末に曽野綾子氏との「没イチ」対談を収録。
楽天koboで詳しく見る
楽天ブックスで詳しく見る
Amazonで詳しく見る