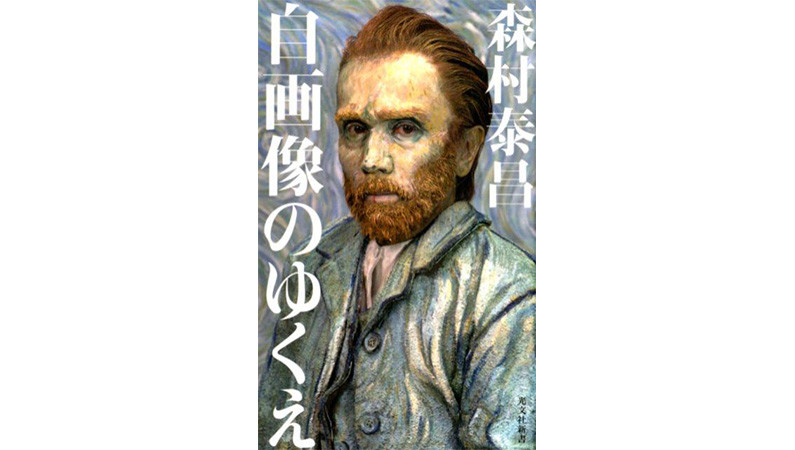現在、上野の森美術館で開催されている「ゴッホ展」は大盛況だ。私も観てきたが、オランダのハーグ派に導かれて独学で画家として歩み始めた時代から、パリで印象派に出会った時代、南仏アルルでの才能の開花、そして狂気に囚われながらも情熱的に描いた日々まで。フィンセント・ファン・ゴッホの画家としての歩みがとてもよくわかる構成だった。
このゴッホ展に合わせるように大手書店ではゴッホのコーナーができ関連書籍が並んでいる。と、その中に「ゴッホの自画像……? いやいや顔が違うぞ」という表紙の一冊があった。それが今日紹介する『自画像のゆくえ』(森村泰昌・著/光文社・刊)。
森村氏はゴッホの自画像に扮するセルフポートレイト写真で一躍脚光を浴びた美術家だ。ゴッホばかりでなく、ダ・ヴィンチ、フリーダ・カーロ、アンディ・ウォーホールといった画家たち、さらには名画に描かれた人物になりきった作品を次々と発表している。本書は、森村氏による「自画像論」で、自画像とはなにか? 自撮るとはなにか? を、その歴史とともに追求している。

ゴッホは自分の顔を描くことで”画風”を確立していった
ゴッホはその短い生涯で40枚もの自画像を描いているが、そのうちの29点は2年間のパリ滞在中に描かれたそうだ。森村氏の解説によると、オランダからパリにやってきたゴッホは、まだ画家としての自分がつかめていない焦りがあったという。「わたし」とは「ゴッホ」ではなく、「画家ゴッホ」でなければならない。そして「画家になる」ためには「画風」を確立する必要があったのだ。
ゴッホは自分の”顔”(=自画像)を描くことと、自分の”画風”を確立することとを、同一視していたのかもしれない。ゴッホにとって、自分の”顔”の絵ができることが、そのまま、自分の”画風”が完成することにつながっている。
(『自画像のゆくえ』から引用)
時代を追って色やタッチが変化していくゴッホの自画像の解説はとても興味深く読めるだろう。
自画像のはじまりは「鏡の中のわたし」
ところで、自画像はいつはじまったのか? だが、それは15世紀半ばだそう。
北ヨーロッパのフランドル地方の画家、ヤン・ファン・エイク作《赤いターバンの男》である。ファン・エイクの本作は1433年作とされており、これをもって「自画像のはじまり」としている。
(『自画像のゆくえ』から引用)
私を映すものは「鏡」だが、かつての鏡は今のようなガラス製でなく金属でできていた。そのため、ぼんやりと、おぼろげに見えるにすぎなかった。ガラス製の鏡が登場したのがローマ時代だが、表面がひずんでいたり気泡があり鮮明には見えなかったようだ。その後、透明でフラットなガラスの裏側に水銀箔を蒸着させて今日のような鏡が作られたのが15世紀だった。
ファン・エイクの作品は「これは絵ではない、鏡だ」、つまり鏡に映っているようによく描かれた絵だと絶賛されることとなった。
なるほどたしかに、「鏡」は、ファン・エイクの絵画における重要なキーワードのように思われる。私はつぎのようなある瞬間を思いうかべてみた。
……鏡の前に画家がやってくる。
そのきらめきに気づき、鏡のほうにふっとふりむく。
その瞬間に画家は、鏡に映しだされた男と視線があう。
一瞬、だれかがそこにいたのかと錯覚するが、
もちろんその男は画家ファン・エイク自身の鏡に映った姿にほかならない……。
(『自画像のゆくえ』から引用)
この時代から、鏡によって誰もが”私”を見定めることができるようになったのだ。
自画像のダ・ヴィンチはダ・ヴィンチではない?
さて、誰もが知っている有名な自画像といえば、レオナルド・ダ・ヴィンチが1512年ごろに描いた素描ではないだろうか。が、しかし森村氏は、ほんとうに彼本人の顔だったのか? という疑問を投げかけている。
ダ・ヴィンチは美形で、優雅で、とてもお洒落な人で、死の間際に至ってもその美しさは変わらなかったという。つまり威厳と風格をかねそなえたあの自画像とはかけ離れているのではないかというのだ。ダ・ヴィンチが遺した手稿の研究が大きく進んだのは19世紀になってからで、そのころになって技術、芸術,科学の父であるイメージが定着していった。
するとどうなるか。バラ色のワンピースを着た美形で、あいきょうをふりまいているなどという図が、西洋の精神の頂点に立つ人物としてふさわしいかどうか。どうもおさまりがわるい。そこで、”元祖”であり”父”であり”キング”であり、”天才”あり”偉人”である人物像としてだれもが思い描けるイコンとして、我々のよく知るあの顔が、レオナルド・ダ・ヴィンチの公式ポートレイトとして定着していったということではなかっただろうか。
(『自画像のゆくえ』から引用)
この独自の自画像再考論はとても興味深い。
”自撮り”の母はプリクラ
さて、現代は写真の時代だ。皆がスマホで自分を映し、SNS上にアップしている。森村氏によると現代の「わたしがたり」のルーツは、プリクラだそう。プリクラは1995年に発売され、2000年に大ブレイク、そして同年にカメラ付き携帯電話が発売になった。”持ち歩けるプリクラ”の登場である。
”持ち歩くプリクラ”として展開し、その機能を”写メール”として打ちだしたわけで、この”カメラ付き&ミラー付き・ケータイ”によって、現代の自撮り文化がはじまったともいえる。
(『自画像のゆくえ』から引用)
そして2013年には、自撮りの英語表記である「セルフィー」が『オックスフォード英語辞典』にあらわれた。私を撮り、私を語ることは、世界の常識になったというわけだ。
本書には、上記のほかに、アルブレヒト・デューラー、カラヴァッジョ、ベラスケス、レンブラント、フェルメール、フリーダ・カーロ、アンディ・ウォーホールの自画像を考察している。
また、森村氏がセルフポートレイトによる写真作品という手法にいきついた話に加え、巻頭には彼の作品もカラーで収録されている。
セルフィーの時代、自分をどう見せ、なにをアピールしたいのか?を自問自答する意味でも、読んでおきたい一冊だ。
【書籍紹介】
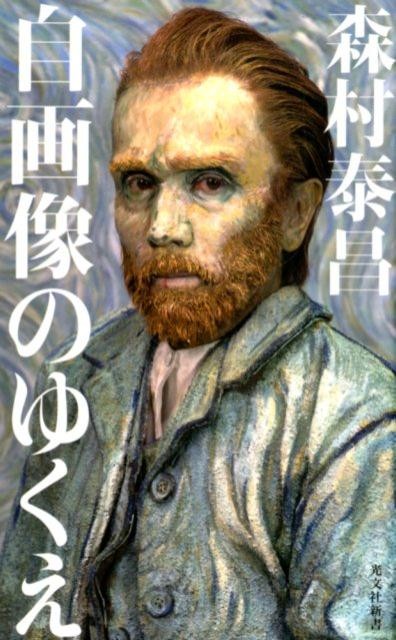
自画像のゆくえ
著者:森村泰昌
発行:光文社
だれもが感じているように、現代ほど「わたしがたり」にあふれかえった時代はこれまでになかった。世界的にその傾向にあるのかもしれないが、日本ではこの傾向がとくに顕著であるようにも思われる。(中略)本書は、私なりの想像力をつけくわえて試みた、自画像の歴史をめぐる、21世紀人のためのツアーである。――セルフポートレイト作品を作り続けてきた美術家が約600年の自画像の歴史をふりかえりながら綴る「実践的自画像論」