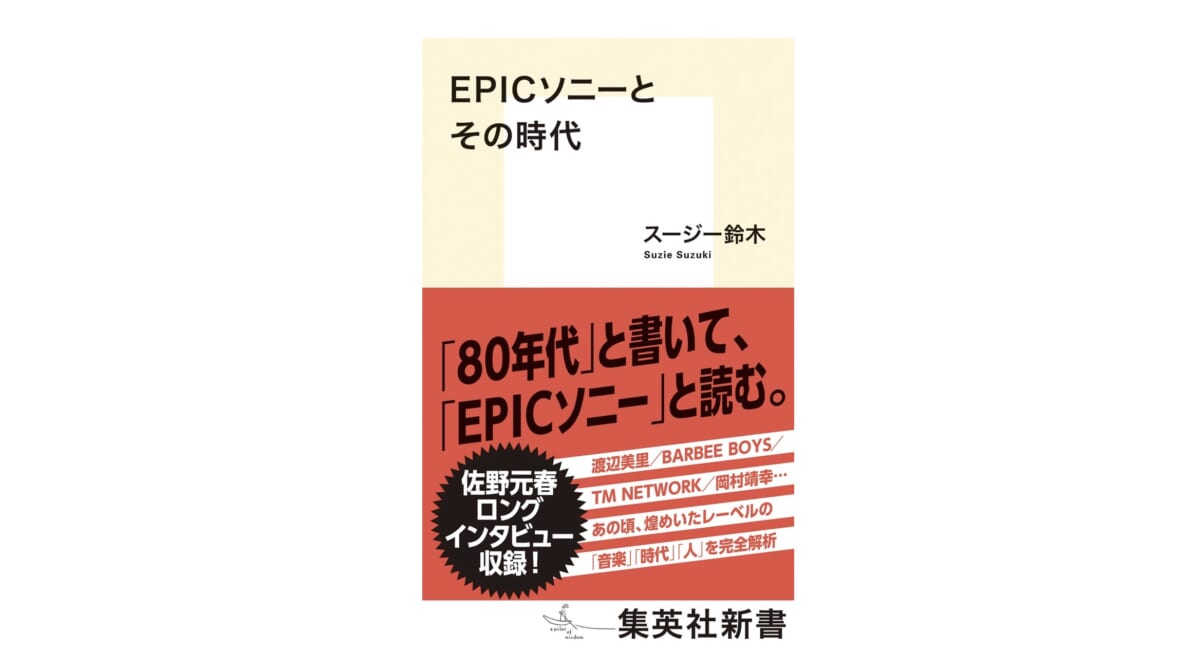現在40代から50代の音楽好きの人たちは、そのほとんどが「EPICソニー」というキーワードにピンと来ることだろう。現在は「エピックレコード」という名称のソニー・ミュージックレーベルズの社内レコードレーベルという位置付けだが、80年代から90年代にかけては、日本の音楽シーンを牽引するレコード会社だった。
EPICソニーと歩いた青春
僕が中高生のころに聞いていた日本の音楽は、そのほとんどがEPICソニーのアーティストだったように思う。
僕が音楽にどっぷりとハマったきっかけが佐野元春だったし、渡辺美里もよく聞いていた。岡村靖幸の変態っぷりに度肝を抜かされ、めちゃくちゃ聞き込んだし、バンドをやっていたときはBARBEE BOYSはすごいバンドだと少々恐れをなしていた。あんなことできやしないし、そのあともBARBEE BOYSのようなバンドは出てきていない。大澤誉志幸の声に憧れて声を枯らそうとしたけれど、ちっとも枯れなかったなぁ。
今思えば、全員EPICソニーのアーティストだ。また、当時はテレビでも音楽番組が多かったが、テレビ東京の深夜にやっていた「eZ」という番組もよく見ていた。これはアーティストのPVを流すという、今のCS放送のような体裁の30分番組だった。これもEPICソニー制作の番組だった。そう、僕は気付けばEPICソニーとともに青春時代を送っていたのだ。
EPICソニーの歴史を紐解く一冊
青春時代は、EPICソニーということを意識していたわけではない。ただ気になるアーティストがEPICソニーだったというだけ。ただ、EPICソニーというのは当時は相当変わったレコード会社だったようだ。
『EPICソニーとその時代』(スージー鈴木・著/集英社・刊)は、音楽評論家の著者が、EPICソニーというレコード会社について細かく考察した書。これを読むと、EPICソニーがどのような経緯で立ち上げられたのか、そしてなぜ80年代の音楽シーンを席巻したのか、その理由がわかる。
一言で言えば、EPICソニーは「反骨精神」から生まれたレコード会社。アイドルの新人賞争い、大物歌手の賞レース争いといった音楽ビジネスを疑問視し、歌謡曲ではない路線、賞レースとは関係のない独自の音楽シーンを切り開くという思想のもとに作られたのだ。
スタッフもほぼ未経験、アーティストも抱えていない状態からスタートし、さまざまな新人アーティストを発掘。そして佐野元春やTHE MODSといったアーティストをデビューさせ、「日本のロック」という未開拓のフィールドを切り開いてきた。決してロックがやりたかったわけではなく、賞レースから一番遠いところを探したら日本のロックシーンだったというわけだ。
そして、メーカーとのCMタイアップという手法でさまざまなアーティストを売り出していく。大沢誉志幸(現・大澤誉志幸)の『僕は途方に暮れる』などは、当時大ヒットした。僕もこのCMは覚えている。
今では当たり前になっているアーティストのPVも、EPICソニーが仕掛けたもの。テレビの歌番組などに出られないアーティストたちのプロモーションとして、独自の映像作品を自社で作り、それをホールなどで上映したり、先述した「eZ」で流すことで認知度を高める。
しかし、「日本のロック」という未開の地を切り開いてきたEPICソニーも、次第に方向性が変わり、いつの間にかソニー本体に吸収されることになる。この辺りの話は本書を読んでほしい。いかに当時のEPICソニーが革新的だったか、そしてメインストリームに対するカウンターカルチャーであったのかがわかることだろう。
僕がEPICソニーを聞いていたのは必然だった
本書では、EPICソニーを「佐野元春」だと定義している。
要するに、あのEPICソニーの本質は何だったのか。80年代EPICソニーのキラキラとした像のキラキラとした皮を剥いで、剥いで、残るもの。それが佐野元春であり、彼が作り出した音楽ではなかったのか。
(『EPICソニーとその時代』より引用)
佐野元春は、EPICソニーでデビューし、日本のロックを牽引してきた存在。僕は佐野元春にハマり、音楽にどっぷりと浸かり、今でも音楽から抜け出せないでいる。僕がEPICソニーのアーティストを知らず知らずのうちに聞いていたのは、おそらく偶然ではない。また、こんな記述もある。
「EPICソニーがタイガースならば、CBSソニーは巨人」という比喩は、当時の音楽シーンを知っている方々ならば、感覚的に納得できるものだと思う。
私自身の感覚としても、80年代のCBSソニーには王者の風格を感じていた。V9を成し遂げた昭和40年代の巨人のようなイメージで見ていた。(『EPICソニーとその時代』より引用)
当時のCBSソニーは、松田聖子の大ヒットがあり、その後浜田省吾、尾崎豊、プリンセス・プリンセス、レベッカ、ユニコーンなどなど、ロックシーンでも人気アーティストを抱えていた。楽曲もポップだし、聞きやすく、大衆に指示されやすいものだった。僕も好きなアーティストが多い。まさに巨人。まさに読売ジャイアンツ。
ただ、とがっていなかった。EPICソニーのアーティストは、決して万人受けするわけではないが、ひとつとがったものがあり、それがやけにキラキラ輝いていた。
阪神タイガースというのもうなずける。僕は東京生まれだが、父親の影響(宮城出身)で生まれてこの方阪神タイガース一筋。やはりメインストリームではなく、それに対抗する何かを応援したくなる気質があるようだ。佐野元春と阪神タイガースが大好きな僕が、EPICソニーに惹かれていたのは偶然ではないと思う。
本書の目玉はインタビューパート
本書はEPICソニーについて深く掘り下げた内容で、とても興味深い。しかし、本書のクライマックスは第三章のインタビューパート。登場しているのは、EPICソニーの元プロデューサーの小坂洋二と、佐野元春だ。
小坂洋二は、佐野元春をはじめとした新人アーティストをプロデュースして売り出した人物。音楽ファンなら一度は耳にしたことがある人物だが、あまり表だって話すことはなかったので、たいへん貴重なインタビューだ。
そしてミスターEPICソニー、佐野元春。彼のインタビューというのは珍しくないが、EPICソニーに最初期からその中核を担ってきた人物の言葉は重い。これまでのインタビューでは話していない内容もあり、こちらもたいへん興味深い。
80年代90年代に青春を送った人で、音楽好きな人なら、絶対におもしろく読める一冊。あの当時の曲を聞きながら読むと、一層味わい深く読めるはずだ。
【書籍紹介】
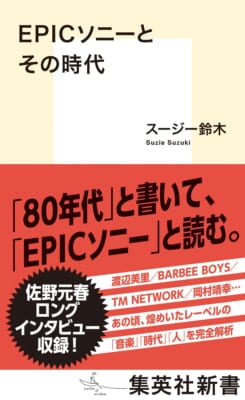
EPICソニーとその時代
著者:スージー鈴木
発行:集英社
先進的な音楽性により八〇年代の音楽シーンを席捲したレコード会社「EPICソニー」。レーベルの個性が見えにくい日本の音楽業界の中で、なぜEPICだけがひと際異彩を放つレーベルとして君臨できたのか?そして、なぜその煌めきは失われていったのか?佐野元春“SOMEDAY”、渡辺美里“My Revoltion”、ドリカム“うれしはずかし朝帰り”など名曲の数々を分析する中でレーベルの特異性はもちろん、当時の音楽シーンや「八〇年代」の時代性が浮かび上がっていく。佐野元春ロングインタビュー収録。