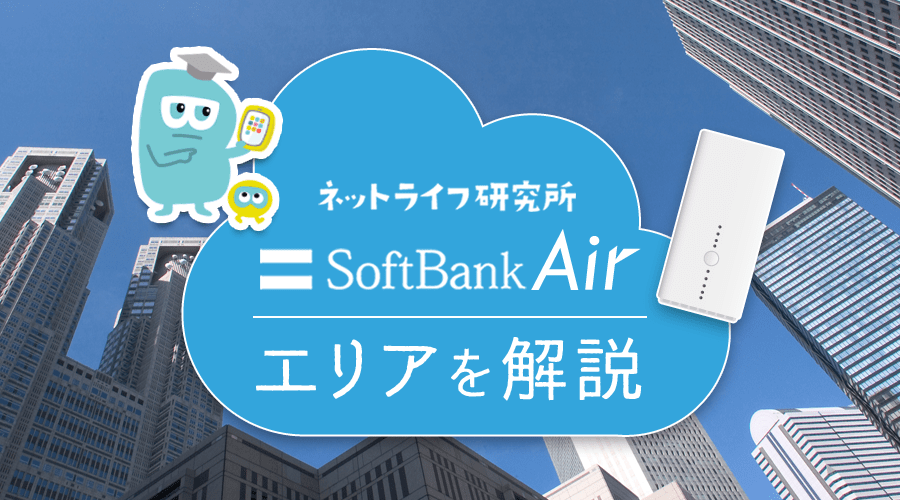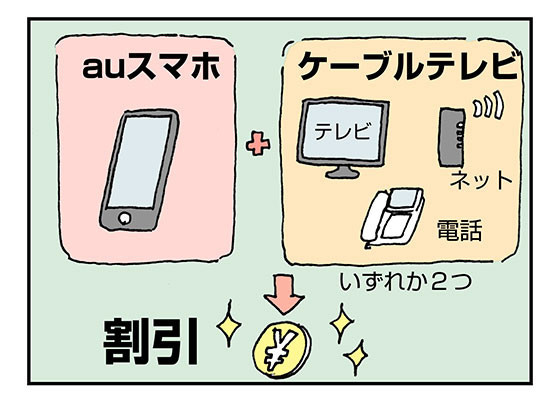今年のCESは開催50年のアニバーサリーを迎えました。あらためて2017年のCESに展示された主なトピックスを振り返りながら、直近のエレクトロニクスの未来を考察してみたいと思います。
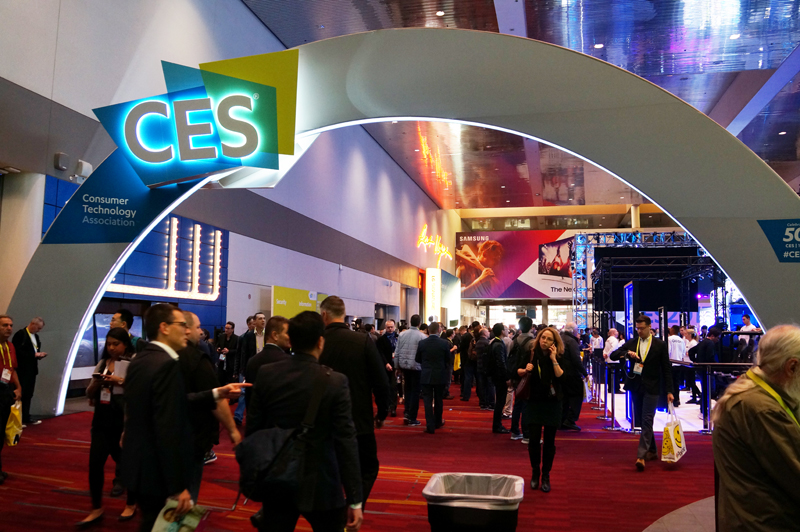
有機ELと液晶はどっちが買いなのか
今年のCESでは、ソニーが初めての“大画面”有機ELテレビを商品化して、年内に世界展開することを発表しました。同時に大型有機ELテレビの商品化では先を行くパナソニックも最新世代機を発表。本世代の製品からは、いよいよ日本にも上陸することになりそうです。またCESへの出展はなかったものの、東芝もCES明けのタイミングに日本で発売する有機ELテレビ“レグザ”「X910シリーズ」を発表しました。

各社の有機ELテレビが日本の店頭に並んだときに、私たちテレビを購入する側のコンシューマーは、一体液晶と有機ELのどちらを選ぶのがよいのか迷ってしまいそうですね。
有機ELの特徴をいくつかまとめておくと、有機ELは素子そのものが発光する自発光型ディスプレイなので、液晶のほかにバックライトが必要になる液晶テレビに比べて、煌めくような明るさと、反対に深く沈む黒色を画面にうまく描けるといわれています。また有機ELの方が視野角が広かったり、パネルそのものが薄く成形できるという点もよく長所に挙げられます。
ただ、一方で大画面化が困難であったことから、かつてテレビ用としてパネルの開発に取り組んでいたいくつかのメーカーも、徐々に液晶へ主力をシフト。液晶テレビの高画質化技術も独自の発展を遂げて来たため、今では画質の優劣で「液晶と有機ELではどっちがベターなのか」を判断することにはあまり意味がなくなったように思います。
今回のCESで有機ELの“ブラビア”「A1Eシリーズ」を発表したソニーも、昨年日本でも発売された液晶“ブラビア”のフラグシップである「Z9Dシリーズ」が「ブラビアの中では最高画質のモデルであり、リファレンス」であると、幹部が記者会見の場で明言しています。CESの会場ではX94E/X93Eシリーズという、最新世代の高画質エンジンを積んだ液晶テレビの新製品も発表。また、有機ELと液晶の“レグザ”ハイエンドモデルを同時に発表した東芝も、新しいシリーズを上下関係ではなく、液晶と有機EL、それぞれが持つ映像の味わいや得意とする表現を見比べて欲しいラインナップとして位置づけています。

実際に有機ELパネル自体は各社ともに自社で製造しているものではなく、同じサプライヤーから入手したデバイスを組み立ててテレビとしてセットアップしています。パネルの実力だけでは差が付かないので、各社の映像の出来映えは画像処理エンジンの性能であったり、ノイズ処理や4Kアップコンバートなどのアルゴリズムの完成度、あるいは開発者の“画づくり”のセンスが勝負所になってきます。

また、当然ながらテレビとしてのデザインや使い勝手も購入時にはとても気になるポイントになります。ソニーはA1Eシリーズで大画面テレビの「音質」にも着目して、画面から音が出る新技術「アコースティック・サーフェス」を搭載してきました。従来の主流だった、パネルの下向きに搭載されていたスピーカーよりも自然で迫力のある音が楽しめる驚きの技術です。
気になるのはテーブルトップスタンドをなくした卓上カレンダーのようなデザイン。筆者の場合、もしこれを買ったらいま使っているテレビラックの上には置けないだろうなと設置の問題を考えてしまいました。壁掛もできるようですが、このままのデザインでA1Eシリーズが日本上陸となれば、ある程度置ける家庭が選ばれることになりそうですね。パナソニックや東芝のテーブルトップスタンド付きのテレビの方が万人に置きやすいメリットはあると思いました。

これからどうなる?AIとスマート家電の関係
今年のCESでは「AI(人工知能)」や「ロボット」というキーワードがあちこちから聞こえてきました。今回は残念ながら時間をかけてみっちりと取材ができなかったのですが、日本の自動車メーカー・ホンダはドライバーとコミュニケーションを交わせる人工知能搭載のEV(電気自動車)のプロトタイプ「NeuV(ニューヴィー)」をCESで発表しています。NeuVは、ソフトバンクとの共同開発による「感情エンジン」を車に積んで、独自のドライブサポートが実現できるコンセプトカー。

パナソニックは「デスクトップ コンパニオンロボット」と名付けた卵型のAI搭載ロボットの試作機を出展しました。ユーザーと音声で受け答えができたり、卵の殻が二つに割れると中に隠れているプロジェクターが出てきて映像を映したり、足下に4つのオムニホイールを付けて自由に動き回れるようにもなるそうです。

LGエレクトロニクスは欧米を中心にインターネットとクラウドにつながるスマート家電を積極的に展開しているメーカーです。そのスマート家電の司令塔になる小さなパーソナルアシスタントロボット「LG HUB-BOT」を発表して、ロボットと暮らす生活を提案しました。HUB-BOTに話しかけると声でスマート家電を動かせたり、キッチンに置けばHUB-BOTがレシピを声で説明、寝室では本の読み聞かせに活躍するようなイメージを想定しているようです。

ロボットといえば、ソフトバンクがいち早くコンシューマーに向けて発売した「ペッパー」が国内海外を問わずとても有名になりました。ペッパーの発売後の反響を聞くと、ショップの店頭に介護施設、一般の家庭などに広がって人と人とのコミュニケーションをつなぐロボットとして活躍しているそうです。恐らくこれからAIやロボティクスの技術は、ペッパーのような単体のコミュニケーションロボットとしての成功例に止まることなく、家電や車などあらゆるエレクトロニクスと合体していくのだと思います。
ソニーも昨年の経営方針説明会で平井社長が、これからロボット事業に参入することを宣言しています。例えばですが、ソニーのブラビアが感情を持って、テレビがネットワーク家電を制御したりリビングで雑談相手になってくれたら生活が楽しくなるかもしれないですね。シャープが「ココロエンジン」を発展させながら展開するスマート家電のように、家電メーカーが得意としていて、既に私たちの生活に必要とされている家電機器にプラスαの価値としてAIやロボットが組み込まれていくかたちがより自然なのではないかと筆者は考えています。いずれにせよこれから注目したい分野です。
4K/HDR動画は自分で撮る時代
パナソニックがミラーレス一眼“LUMIX”の最新モデル「GH5」をCESで正式に発表しました。4K/60p動画の撮影に対応するデジタル一眼として、パナソニックのプレスカンファレンスでも特に時間を割いて紹介された看板製品です。

LUMIX GHシリーズのミラーレス一眼はもちろん日本でも歴代モデルが発売されてきたので、その実力は多くのカメラファンが知るところではないでしょうか。特にデジタル一眼で4K動画撮影を楽しむ文化は、パナソニックのLUMIXが先頭に立って牽引してきたイメージがあります。
その最新モデルのGH5では、いま“4Kを超える高画質”として話題の4K/HDRコンテンツが、プロ専用ではないコンシューマー用のカメラで撮影できるようになることが大きな話題を呼んでいます。
これはHLG(Hybrid Log Gamma)と呼ばれる、主に放送コンテンツでの活用を想定したHDR映像の記録方式をGH5に採用することで、同じHLGによるHDR動画の表示に対応するパナソニックの4Kテレビで見るというエコシステムを完成させて、パナソニック独自の価値として提案するものです。明暗や色彩の表現力が広く、目で見たままの被写体により近いイメージを再現できる映像技術といわれるHDRに対応する動画を、一般のコンシューマーが手元の機器で体験できるようになればHDRの実力がより身近に感じられて、認知拡大にも弾みが付きです。おそらく同様の4K/HDR動画撮影に対応する家庭用ビデオカメラ、デジタルカメラは今年各社から発売されるはずです。
VRは次の大物の登場に期待
VR(仮想現実)は昨年のCESで最も注目されたトレンドワードの一つでした。今年の会場を見渡すと、サムスンがGear VRの特設体験スペースを設けたり、ソニーのPlayStation VRの体験展示も賑わっていました。直接VR関連の商品を持たない出展社も、自社製品のプレゼンテーションをVRヘッドセットを使って見せることで、来場者に足を止めてもらうためのマグネット代わりにしていました。


またVRヘッドセットだけでなく、ゲームコンテンツを楽しむためのコントローラーデバイスも種類が増えています。日本から出展したCerevoは、触感をフィードバックできるコントローラー「Taclim(タクリム)」を発表。手に着けるグローブ、足に履くシューズに触感を返すタクタイルセンサーを内蔵して、仮想現実世界の中にあるオブジェクトに触れる感覚をリアルに再現。筆者もブースでこれを体験して、VRコンテンツの豊かな可能性を感じた次第です。


パナソニックからはBtoB(ビジネス用途向け)を想定したものですが、220度のワイドな視野角を実現したヘッドマウントディスプレイの試作機が展示されました。独自開発の光学テクノロジーにより、3面のディスプレイをつないで広い視野を実現。音声はヘッドホンを使わずに、音を振動で伝える骨伝導スピーカーにより聴き取りやすさと装着感に工夫を凝らしています。プロトタイプではHDMIケーブルでPCにつなぐかたちでデモをしていましたが、将来はWiGigの高速無線伝送技術を組み込む計画もあるそうです。

VRは昨年、PS VRやHTC VIVE、Oculus Riftなど大物のヘッドセットが発売され、いまはひと段落して次の大物を待っているような雰囲気を感じます。もちろん既存のハード機器で楽しめるキラーコンテンツの登場も重要です。ソニーではグループ企業のソニーピクチャーズやソニーミュージックを巻き込みながら、いわゆる“ノン・ゲーム”タイプのVRコンテンツ制作を加速させて、ゲーマー以外のVRユーザー開拓を積極的に図る考えを表明しています。来年のCESが開催される頃には、ハード・コンテンツともにVR関連の大きなニュースも取材してお届けできるといいですね。
北米でもいよいよハイレゾブーム到来か
最後に、今年のCESで気になったオーディオ関連の話題をもうひとつご紹介します。CDよりも高音質なハイレゾ(ハイレゾリューションオーディオ)は、いま日本では徐々に認知が広がり、対応製品も増えてきました。一方で、欧米での開拓はいまだ道なかば。特に北米ではハイエンドオーディオや、一部のヘッドホンファンの間では浸透しつつあるものの、一般的な認知を獲得するには至っていないといわれています。去年までのCESでは、ハイエンドオーディオ系の出展が集うベネチアン・ホテルの会場では話題に上るものの、メイン会場のラスベガス・コンベンションセンターではあまり多くの展示を見かけることがありませんでした。
今年はちょっと雰囲気が変わりはじめていました。アメリカで次世代デジタルエンターテインメントの普及促進に向けて活動する業界団体DEGが、いまハイレゾに対応するポータブルオーディオやコンテンツを一堂に集めて展示する「Hi-Res Audio Pavilion」を構えて、色んな角度からハイレゾの魅力を紹介していました。

その中で最も興味深かったトピックスは、北欧に拠点を置く音楽配信サービス「TIDAL(タイダル)」が欧米でハイレゾ品質の音楽配信をはじめたことです。日本でもApple MusicやSpotifyといった音楽配信サービスが楽しめますが、多くはハイレゾどころかCD品質のクオリティにまだ達していません。
もっともそれは無理もないことで、もしハイレゾ音源のデータは容量が大きいので、インターネット経由で普通に配信すると通信トラフィックを圧迫してしまい、またLTE/3Gネットワークでスマホやタブレットを使って受信しようものならあっという間にパケ死を招いてしまいます。
今回、TIDALはメリディアン・オーディオという英国のブランドが開発したMQAと呼ばれる技術を採用して、ハイレゾの音源データ量を1Mbps(およそCD相当)のビットレートに変換して伝送するサービスを新しくスタートさせました。北米ではオーディオに限らず、ビデオコンテンツもインターネット配信で楽しむ文化とインフラが定着しているので、これまで普通にTIDALを楽しんでいた人々が、これからはハイレゾもふくめて聴き放題で試せる環境ができて、認知と普及が拡大する可能性が高まりました。これからは海外発のヒットチューンが続々とハイレゾ化されて日本にやってくることになるのでしょうか。海外ブランドからハイレゾ対応のオーディオ機器がさらに増える機会にもつながるよう、期待しましょう。