買い物依存症、ホスト沼、整形など、自らの身体を張った体験で世間を騒がせてきた作家・中村うさぎ。原因不明の難病ととも生きる今、改めて「恋愛」「結婚」「人生」について語ってもらった。
(企画・撮影:丸山剛史、執筆:小野田衛)

中村うさぎの現在
──今回は中村さんの半生の中でも、特に2013年に病気で倒れたとき以降の話を伺えたらと考えています。当初は「原因不明の難病」と発表されていましたが、これは100万人に1人がかかると言われるスティッフパーソン症候群でよろしいんですか?
中村 いや、そこが微妙なところでね。スティッフパーソン症候群じゃないかとは言われているんだけど、正式な病名はいまだに確定していないんです。診断書に病名が書かれていない状態。だから私の場合、難病指定に付随する福祉は受けられないんですよ。
──そんなこと、あるんですか。
中村 周りの人にしてもお医者さんにしても、入院したころの私の状態を見たら1人じゃ歩けないことは明白なわけです。それでも病名が診断書に書かれていない以上、福祉や介護的なサービスが受けられない。だから結局は夫が1人で面倒を看るしかない。
介護手当に関していうと、65歳になると誰でも公的なサービスが受けられるんです。でも、私は62歳。65歳以下の人は、国に指定された「特定疾病」だと診断されないとダメなんですね。この特定疾病というのは、末期がんとかパーキンソン病とかいろいろあるんですけども。いずれにせよ私の場合は病名が確定していないわけだから、介護保険の権利がない。
これは役所に言わせると病院側の問題だということになるし、病院側からは制度の問題だと聞かされた。私から言わせれば、「御託は並べなくてもいいから、とっとと病名を書いてくれよ!」というのが本音。ただスティッフパーソン症候群と断定するには、当てはまらない症状がいくつかあるらしいんです。だから医者も病名を書く自信がないんでしょう。
──セカンド・オピニオンは考えなかった?
中村 もちろん考えました。カルテも出してもらいましたし。だけど今以上に症状が大変な時期だったから、車椅子でいろんな病院を回るのが体力的にキツかったんです。だってタクシー移動するにしても、トランクに車椅子を入れなきゃいけないわけですよ。よくトランクに私物を入れているタクシーの運転手さんがいるじゃないですか。あれはNG。それ以外にも行動はすごく制限されるんです。それに加えて、病院に用意する書類などの手続きもすごく複雑でしたし。そういうことが重なって、「もういいか、ここで」と面倒くさくなっちゃった(苦笑)。
──とはいえ、現在は一時期に比べたら回復に向かっているということでよろしいんですか?
中村 そうですね。入院した当時と比べれば、だいぶ症状は緩和されています。病名は確定していないものの、投薬は続けていますし。手が震えるのを抑える薬、全身が突っ張るので筋肉を和らげる薬、あとは万能薬と言われるステロイド……。今は車椅子がなくても、つえを使えばなんとか外も歩けるようになっていますから。家の中だけだったら、壁に手をついて身体を支えながら歩けるようになってきました。
──ブログを拝見させていただくと、新型コロナウイルスの感染拡大前は外食も頻繁にされていたようでしたが。
中村 1人では絶対に無理ですけどね。誰か支えてくれる人が一緒じゃないと、外食なんてできない。それから新しいお店に行くときは、下調べをめちゃくちゃします。エレベーターなのか階段なのか? 階段なら手すりがついているのか? そういうことって健康なうちは気にもしなかったんですけど。
いかんせん病名すら確定していないわけだから、完治も何もないんですよ。それ以前の問題。だけどこれが本当にスティッフパーソン症候群だとしたら、そもそも完治というのが存在しないんです。症状を抑えることしかできない。そういう意味でいうと、薬の量も減ったし、一時よりはマシになっているのかなと思うんですけどね。

あの世など存在しない
──生死に直結するような病気に直面したことで、人生観や書く内容にも大きな変化が生じたかと思います。
中村 私の場合、入院中に心肺停止もしましたしね。そのときは呼吸も心臓も止まったわけで、要するに一瞬は死んだということなんです。そこで確信したのは、「あの世など存在しない」ということでした。
──よく「走馬灯のように記憶が蘇る」とか言いますけどね。
中村 ねぇ? 佐藤優さんみたいなクリスチャンに言わせると、「うさぎさんは覚えていないだけですよ」ってことになるんだけど。たしかにその可能性もあるんですよ。なにせこっちは意識を失っているんだから。天国の門だか地獄の門だかを実際に見ても、この世界に戻ってきたときに覚えていないというのはありえる話でね。
でも、薄ぼんやりとした記憶の中で私が覚えているのは、テレビの電源をプチっと切った感覚。あれに近いんです。ある瞬間を境にして、急に世界が真っ暗になる。そこからは、ただの闇。夢さえ見ない深い眠りの底に沈んでいく感じかも。そして目が覚めたら、もう3日くらい時間が経っていた。
だから結論として、死んだら何もないですよ。ゼロの状態になるだけ。私は無宗教だけど、死んでも何かしらあるのかもしれないとは思っていたんです。よく言うじゃないですか。死んだあとも魂は残っていて、その魂が死んだ自分の肉体を眺めているとか。あるいは臨死体験として、トンネルの向こうに光が見えるとか。でも私の場合、そういうことは一切なかったですから。極めてあっさりしたものでした。
──死は別にスピリチュアルなものではないと。
中村 霊的な体験は一切ありませんでしたね。もともと私は死を怖がる性格でもないんだけど、あの体験をしたことで「死ぬのって楽じゃん」と思うようになりました。だって意識が残るっていうのは、自我があるということ。自我がある限り。生きているのと同じ煩悩が続くわけでしょう? この世に未練や後悔も残るだろうしね。私のことだから、友達の反応とかにいちいちムカついているかもしれない。「勝手なことばかり言いやがって……」とか(笑)。
だけど実際は単に深く眠っているような状態だったわけで、そこには何の責任もなければ、何の感情もない。私にとって死は「一大ラッキーイベント」でした。あのときに死ねなかったのが今でも無念です。
──「何も考えなくていいから楽」というのもわかるのですが、中村さんは常に「私とは何?」と考えながら執筆してきました。
中村 そうですね。だからもう、そういうのから解放されたいの。「私とは何か?」「人間とは何か?」みたいなテーマって、私以外の人だってやってることでしょ。私の代わりの誰かが文章にして、その考えがもっと核心を突いてたり面白いものだったりしたら、世の中にとっても結果的にいいわけですし、私が死んでも誰も困らない。
意識が戻って退院したあと、つくづく「生きるって大変すぎる。死んだほうが絶対に楽」って思い知らされました。なにしろ自分の力で歩けないという状態は、今まで経験したことないわけですよ。乙武(洋匡)さんみたいに生まれつき不自由な状態だったら感じ方も違うんだろうけど、それまで当たり前だったことが当たり前にできなくなる無力感というのは相当に大きくてね。
乙武さんとは何度かごはんを食べたこともあるし、それ以外にも車椅子に乗っている知り合いが私には何人かいるんです。そういう人たちが食事をしたりトイレ行ったりしている様子を見ながら、「やっぱり大変そうだな」なんて他人事みたいに思っていたんですけど。いざ自分が急にそうなってみると、とてつもない無力感に襲われるんです。「私は何もできない人間だ」って……。
だってトイレにすら自分ひとりでは行けないんですから。そもそも普通の家はトイレが車椅子仕様になっていないですしね。それで夫が介護用の支柱をつけてくれたりしたんですけど、それを使ってひとりで用を足せるようになるまでは本当に何ひとつできなくて。夫も介護疲れみたいな感じになったし、こっちとしては申し訳ないという気持ちでいっぱいになりますよ。
──やはり介護疲れみたいなことも起こりましたか。
中村 たとえば疲れ果てた夫がソファで大爆睡しているとするじゃないですか。だけど、そんなときに限って私は猛烈にトイレに行きたくなるんですよね(笑)。それがウンコだったらオムツの中にすればいいんだけど、おしっこだとそうもいかない。というのも成人用に作られたオムツとはいえ、我慢に我慢を重ねた状態で出すとオムツの脇から漏れてしまうんです。そうすると車椅子の座布団が濡れたりして、いよいよ後始末が大変なことになる。
──自尊心が傷つけられるということは?
中村 まぁ単純に落ち込みますよね。もちろん老いると人間は誰でも少しずつ弱っていくものだと思うんです。葉っぱが1枚ずつ落ちていくように、身体のいろんな機能が低下していって……。「歯が悪い」とか「腰が痛い」とかね。入院した時点で私は50代の後半。それがいきなりおばあちゃんになった気分でした。たしかに昔から私は生き急ぐタイプではあったけど、老化まで急ぐことはないだろうって(笑)。

最後まで残っていたのは「恋愛欲求」
──買い物依存、ホスト、整形……。世間が考える中村うさぎ像というのは、自身の強烈な欲望に突き動かされている姿だと思うんです。そういったエネルギーは今どこに向かっているんでしょうか?
中村 ……今は、もうなくなってしまったのかもしれないな。それでも恋愛欲求みたいな感情だけは、退院直後もまだ残っていたんです。だけど車椅子のオムツ生活だから、実際はどうにもままならないわけですよ。出会い系で誰かと知り合ったところで、夫に車椅子を押してもらいながらラブホ行くわけにもいかないしねぇ(苦笑)。
──若いうちは「50歳にもなれば、恋愛なんてどうでもよくなるはず」と考えがちですが、実際は男女ともにそんなこともないですよね。
中村 もちろん個人差はあるとは思うんですよ。私の場合は「性欲」というよりは「承認欲求」みたいなものが強いんです。「女として誰かから求められたい」という感情ですよね。セックス自体が楽しくて仕方ないというタイプも世の中にいますけど、私自身はそうではなかった。この承認欲求というものは、身体が悪くなったところで急に消えるわけもないですから。
たしかに私は売り専で買ったり、出会い系サイトで知り合った男とやったりもしていました。だけど病気してセックスができなくなったところで、欲求不満は特に感じませんでしたね。セックスという行為自体は大して重要じゃなかったんだと思う。
──とはいえ「相手から求められたい」という感情の中には、「性的に求められたい」というニュアンスも含まれているのでは?
中村 もちろんですよ。でもそれは「性欲」とはまた別の欲求でしょ? 「セックスしたい」という欲求ではなく「欲情されることで女としての自分の価値を確認したい」という承認欲求なんです。「女である」というのは一体どういうことか? 「女」の定義はひとつやふたつではなく、もっと多面的なものだと思う。で、少なくとも私にとって女であるということは「子どもを産む」みたいな要素とは切り離されていて、「男の欲望の対象である」ということが大きな意味を持っている。
自分が好きな人から好かれたい。これは誰しもが持つ感情だと思います。だけど現実は自分が好きでもない人から欲望のまなざしで見られたりもする。じゃあ、このシチュエーションをどうやって受け止めるのか? 私の場合は「快感」と「不快感」が入り混じった気持ちになるんですよね。
──自分の中で矛盾を抱えた状態?
中村 やっぱり女だと若いころに痴漢されたり、男の人につきまとわれたりして、怖い目に遭うことが多いじゃないですか。だから男性の性的な視線に対する嫌悪感というのが、どうしても根強く残ってしまう。痴漢に遭ったときの屈辱感とか羞恥心というのは、男にはちょっと想像できないと思いますよ。一種の男性嫌悪というか……。
でもその一方で、自分が年を取って誰からも性的な視線を浴びなくなると、なんだか自分の価値が暴落したような切ない気分になるわけです。「男の欲望の対象であることの快感と不快感」というアンビバレントな気持ちは、多くの女性が抱えていると思います。で、人生の時期によって、快感の方が優勢だったり不快感の方が強かったりする。私自身、「男なんてもういいや」となった時期が30代半ばくらいでやってきましたし。
──それは前の旦那さんと離婚して、そのあと恋人とも別れた時期ですか?
中村 そうです。その男とは不倫だったんですけどね。それで別れてからは「鉄の処女期」が到来するんです。鉄の処女期に私が何をしていたかというと、オカマとばかり遊んでいました。ホストにハマる42歳くらいまで、8年くらいは「一生、男なんて必要ない」と本気で思っていましたね。

「女としての承認欲求」とホスト
──そんな禁欲生活を送っていたのに、なぜホストにハマったんですか?
中村 禁欲ではないです。性欲や恋愛欲求を我慢してたわけではないので。ただもう本当に心から「男なんかいらない」時期だったんです。でもその8年の「鉄の処女期」の間に私はすっかり「女の旬」を過ぎてしまった。そのことに気づいたとき、私の中に再び「女としての承認欲求」が蘇ったんですね。若いころとは違って焦りを強く含んだ恋愛欲求です。
そこに、ホストが現れた。女客との仮想恋愛のプロですよ。旬を過ぎて焦っていた私は簡単に手に入る恋愛に飛びついてしまったんだと思います。でも結果的に手に入ったのは「女としての充足感」ではなく、「騙された!」という屈辱感だったわけですが(苦笑)。
私がハマったホストというのが、ものすごくバカだったんですよ。本当に無教養で頭が悪かった。だから、「こんなバカに騙されたなんて、私もっとバカじゃん!」と愕然としました。どんだけバカだったかというと、くらたま(倉田真由美)と一緒にホストクラブに行ったとき、彼女が真顔でこう言ったくらいです。「こんなに頭が悪い人たちと話したのは、これまでの人生で初めてかもしれない」って(笑)。
──唖然とするほどのバカさ(笑)。
中村 でも、くらたまの反応も当然だと思う。だって私たちの周りにいる編集者とかってどんなにチャラチャラしててもいわゆる一流大学出てたりするし、知的水準だって決して低くないですからね。くらたま自身、一橋大学を出ているわけですし。でも、私の指名したホストの無知と無教養には目をみはるものがあった。「サルが人間に進化する狭間のミッシングリンクはこいつだった!」とか冗談で言ったくらいです。
──のちに整形にハマったときは、雑誌の企画とも連動していましたよね。ホストにハマったのは純然たる好奇心からだったんですか?
中村 最初はまさに好奇心でしたね。新宿二丁目で遊ぶのに飽きて、女友達と「通りを超えて歌舞伎町行ってみるかー」と軽い気持ちで足を踏み入れたんです。で、さっきも言ったように、今まで見たこともない人種に出会った。見たこともないほど美形で、見たこともないバカな男ね(笑)。
当然、「こんなバカが私を騙せるわけがない」と見下していたんですが、甘かったですね。ホストは騙しのプロだった。よく野球なんかのスポーツ記事で五角形のレーダーチャートが載っているじゃないですか。「守備力」「打撃」「走力」とかが一目でわかるグラフ。あれでいうと、ホストって他は何もできないくせに人を騙す能力だけは突出して高いんです。
それでホストにハマってまんまと騙されて、女として終わりかけているんじゃないかという焦りにますます拍車がかかった。「こんなバカ男に騙されるなんて、私はもう女として終わってるんじゃない?」「ていうか私ってもはや男には欲情されないのかな?」って。要するに女としての市場価値が暴落していることをホストクラブで思い知らされたわけです。そこで見た目の若さを取り戻そうとして、整形に走ったんですね。
──出会い系などに傾倒していったのも同じ流れですか?
中村 うん、同じ。「まだ自分は女として求められている」と安心したかったんです。私の場合、出会い系サイトで会った男とは、よっぽどのことがないとホテルまで行かないんですよ。大抵は向こうが行きたそうにしているのを見て、満足した時点で終了。そこが私のツボだったんだと思います。
──傍から見てわからないのは、中村さんは作家としての社会的ステータスもあるし、ファンもいれば収入もある。つまり何ひとつ不自由ないはずなのに、なぜ「もっと、もっと!」と求めるかということなんです。
中村 その疑問は、東電OLの話にも通じると思う。東電の総合職といえば、少なくとも当時はエリート街道そのもの。「それなのに、なぜ立ちんぼなんてやってたのか?」という疑問と衝撃を世間に与えたわけじゃないですか。私があの事件で興味深かったのは、一部の女性たちから「その気持ちわかる」という共感を集めたことなんですよね。その人たちは売春なんて関係のない世界で生きているんだけど、「東電OLは私かもしれない」という思いがあった。
やっぱり女が社会の中でバリバリ仕事していくと、社会的成功とは裏腹に失うものも多くなるわけですよ。たとえば婚期や出産のタイミングも逃すでしょうし、女としての旬を仕事に捧げてしまうと何か重要なものを犠牲にしたような気持ちになる。「出世することが果たして女としての幸せなのか?」という自問は、常につきまとうんじゃないかな。特にあの当時はね。
──そこは男側が見落としがちなポイントかもしれません。
中村 根本から違うんだと思いますよ。男の場合はどんなブサイクで生まれてきても、社会的な成功や富によって綺麗なトロフィーワイフをゲットすることも可能じゃないですか。だけど女の場合は、それがなかなか難しい。地位や富や名声がモテと結びつかないんですよ。いや、むしろモテを遠ざける。
ましてや私たちみたいな作家や漫画家といった人種は、名前が知られるほど恋愛しにくくなるんですね。なぜなら、作品の題材として書いちゃうから。私はもちろん、(内田)春菊さんにしても、岩井志麻子にしても、くらたまにしても、自分の恋愛を赤裸々に書いちゃうでしょ。これじゃ男から警戒されますよね(笑)。
──「男からチヤホヤされたい」という気持ちは、病気を経てどのように変わりました?
中村 退院直後は気持ちの面では変わらなかったけど、現実問題としてデートもセックスも諦めざるを得なくなると、その欲求も薄れていきましたね。退院直後はドラクエとかのオンラインゲーム上でイチャイチャしてました。「どんなエッチが好きなの?」とかチャットでやりとりしてね。
──ドラクエということは、相手が子どもかもしれないじゃないですか。
中村 そうなのよ! 一度なんか相手が小学生なのに気づいて慌てたことがありました(笑)。私は下ネタ大好きなんだけど、中学生の子に下ネタ言ってたらその子の親から怒られたこともあった。横から会話を見ていたお母さんが「こんな下品な人とは遊んじゃいけません!」って(笑)。まぁ、私も「チン毛、生えた?」とか普通に訊いてたからね。でも、もともとは本人が「チン毛がまだ生えない」って言い出したのよ? だから会うたびに挨拶代わりに「よぉ、チン毛生えたかー?」って訊いてたら、ついに親から怒られちゃった(笑)。
でもまぁ、最近はオンライン上のバーチャル恋愛も飽きてぱったりとやめた。本当に性欲も恋愛願望も一切ないもんなぁ。たまにオナニーはするんですよ。でも私のオナニーはセックスの代替行為ではないの。マッサージみたいなもので「肩が凝ったから、マッサージでも受けるか」という感覚。「あー、なんか気持ちいいことしたい……そうだ、オナニーしよっと」みたいな感じなんです。そこにロマンティックな要素は一切ないですね。

「書くことがない」問題
──買い物にしてもホストにしてもそうですが、熱狂できるものがあったからこそ中村さんは書き続けられたと思うんです。今、書きたいと思う対象は?
中村 それがないんですよね。実は「書くことがない」という問題は、病気になる何年か前から始まっていたんです。そんななか、死にかけたことで感じたことも多いにあったし、しばらくはそのことを題材にしていたんですよ。生活も一変して、すべて驚きの連続でしたし。だけど歩けないという生活も当たり前の日常になっていくと、自分の中で新鮮さはなくなってしまう。
──中村さんの場合、これまでも書くためのネタを作るため何かにハマったわけじゃないですからね。
中村 そこは明確に違う。単なるネタだったら、買い物依存症にしたってあんなアホみたいお金は使わないですよ。もうちょっとスマートにやっているはずです。ホストだってハマりたくてハマったわけじゃないですしね。私からしたら、出会い頭の事故みたいなもので。
でも、たしかに書く題材がないというのは困ったことではあるんです。最近は母がボケ始めたから、それについて書こうかとも思ったんですよ。まずは大阪の実家に帰って、母の様子を観察日記みたいにして書こうと思いついた。そうしたら、父親からきっぱり拒否されちゃった。痴呆の妻を抱えているだけでも大変なのに、要介護の娘まで来たらたまったものじゃないと思ったのかな。とにかく「帰って来なくていいから!」の一点張りでした(笑)。
──その気持ちも当然でしょうけど。
中村 実際、介護ってめちゃくちゃ大変ですからね。だから夫には本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいです。介護ヘルパーはプロだからそれでお金をもらっているけど、夫の場合は不幸にも役目が回ってきただけですから。もし私の病気がなかったら、他にできたこともいっぱいあったろうし。だからいっそのこと専門の施設に入ろうかと考えたこともあったんだけど、夫が「私が世話するから」って言ってね。

軽い結婚を固い絆に変えた税務署とのバトル
──ゲイでもある旦那さんとの関係について、改めてお伺いします。20年前に結婚されたときは、ビザ取得の関係から籍を入れたという話でした。言ってしまえば、行きがかり上の結婚だったのかもしれない。
中村 もともと仲はすごくよかったんです。しょっちゅう私の家に泊まりに来ていましたし。何人かいたゲイ友達の中でも、一番親密だったんじゃないかな。そういう意味じゃ信用していたし、その信用する人が日本在留問題で困っていたから手を貸したということなんです。誰でもいいという話では決してなかったですよ。
とはいっても、ゲイとの結婚ですからね。相手はゲイのパートナーと同性婚したくなるかもしれないし、ノンケの私だっていつ恋人を作ってそいつと一緒暮らしたくなるかわからない。世の中的にもすごくレアなケースだし、いろんなトラブルの可能性があったのは事実なんです。当時の私は40歳だったけど、夫はまだ30歳。「もし同性のパートナーと一緒になりたいと思ったら、いつでも結婚解消していいからね」と、それは最初から伝えておきました。
──極めてドライですね。
中村 ドライだし、すごく軽い結婚。最初の数か月は同居もしなかったですしね。私も1人暮らしの生活が長く続いていたから、他人と一緒に住むことに抵抗があったんですよ。友達としてはよくても、同居すると許せなくなることってあるじゃないですか。それは恋愛だけじゃなく、ちょっとした生活習慣の違いとか。そういうこともあって、「とりあえず結婚はするけど、別々に近所に住むか」みたいな話になりました。
ところが、あるときに彼が病気して連絡を取れなくなったんです。もともと彼が病弱だということもあって、そこで私はすごく心配になっちゃった。で、「こんなに心配するくらいなら、一緒に住もう」ということになったんですけどね。
──今はお互いに必要不可欠なパートナーとなっているようですが、ゆるやかな関係から強固な絆に変化したきっかけが何かあったんですか?
中村 ターニングポイントは税務署とのバトルですね。当時の私は「税金を払え!」「いや、払うお金がない!」といったことで、ひどく揉めていたんですよ。そのころは買い物依存も一段落してホストにお金を落としまくっていた時期で、「こんなに高い税金を納める筋合いはない!」と突っぱねていたんです。税務署側からしたら徴収するのは当然の話。でも私としては「働けば働くほど税金に取られる。これはどういうことなんだ!? これじゃ働きたくなくなるだろ!」とか言っていた(笑)。
──窓口の人も困惑したでしょうね(笑)。
中村 さらに私って、お金の計算とか書類をまとめるのが猛烈に苦手なんです。請求書も満足に書けないくらいですから。そのころはすでに私の状況がひどすぎて、税理士さんすら匙を投げていたんですよ。それで夫が税務署までついてきてくれたんですね。しょうがないからってことで、夫は確定申告の書類の書き方を勉強してくれた。私も私で「頼む!」と全面的に甘えちゃって。
で、税務署から呼び出しくらってはケンカする日々が続くわけですよ。「これは経費として認められません」みたいな話になって。もう終わったあとはグッタリ疲れちゃって、税務署の近くの喫茶店で休みながら、私がふと言ったんです。「あんたも私みたいな女と結婚したばかりに、こんな得意でもない税金の書類を作らされてさ……。しかも狭い部屋で税務署の人に説教までされてさ……。ほんとごめんね」って。
──たしかに結婚前はこんなことになると想像もしていなかったでしょう。
中村 そうそう。で、その喫茶店での彼の言葉というのが、またすごく印象的だったの。「あなたは私と人生観が180度違う」と言うわけですよ。「前からつき合いはあったから、どういう人か理解していたつもりだった。だけど実際に結婚してみると、『こんな人がこの世にいるんだ』と驚くことばかりだ」と。
どういうことか聞くと、「あなたは明日が今日と同じだと我慢できない人。毎日が違う日じゃないと退屈してしまう。あなたにとって幸せとは、毎日が違う状態になっていることなんでしょう」って言いだした。たしかにその通りですよ。それで彼が続けて言うのは「だけど、私はあなたとまったく逆なの。私にとっての幸せは、明日も今日と同じな状態が幸せだということ。今日と違う明日だったら怖いのよ」って。そりゃ私だって安定志向の人が世の中にいることは知っていたし、アリとキリギリスでいえば完全に私はキリギリス型だけど、夫がこんなバリバリのアリだったとは知らなかった。
──失礼ですが、それだけ価値観が根本から違うと普通は破綻してもおかしくない気がします。
中村 そもそもなぜこんなことになっているかというと、私は目の前にお金があったら全部使っちゃうし、後先なんて何ひとつ考えていない。毎日が刺激的だったらそれでいいやという考え方だから。それで税務署から叩かれているわけです。もちろん彼自身の考えは私と全然違うんだけど、彼は「その違いを受け容れるわ」と言うんです。「だって私たちは結婚しているんだから。ただの友達だったら放っておくけど」って。
──それもすごい覚悟です。人間の器が大きいというか……。
中村 彼は結婚のハンコを押すとき、自分に問いかけたらしいんですね。「この人の人生を自分が半分は背負わなくてはいけない。それでも大丈夫なのか?」って。だって彼から見たら、私は完全な変わり者。性格も変わっているし、仕事も変わっているし、オカマとしか遊ばないし、シャネルばかり着ている。まぁ、ただの友人なら「面白い人だな」という扱いでいいんだけど、結婚して人生を背負うとなると、話が違ってきますからね。でも、彼にそんな一大決心があったとは、その喫茶店で初めて知りました。
で、彼は続けてこう言ったんです。「刺激を求めてあちこち飛び回るあなたを私は変えようと思わないし、それがあなたの生き方なんだって納得してる。でもね。あなただっていつか飛べなくなる日が来ると思うの。もう飛べなくなって、家に帰って休みたくなる日がね。そのときに私があなたの帰る場所になるから。あなたと同じ生き方はできないけど、あなたの帰る場所を作って待ってるわ」って。そして今、どこにも行けない身体になって、あの時の言葉が口先だけの言葉じゃなかったとしみじみとわかるんです。
──お互いに束縛しないスタイルが結果的によかったんでしょうか。
中村 彼に恋人ができて、家を出た時期もありましたよ。結局、また戻ってきたんですけど。最初に「家を出て彼氏と住みたい」と聞いた時も私は「おお! そんな彼氏ができてよかったじゃん」って感じで、喜んで新居の手続きを手伝いました。そのころは私も私で毎晩のように遊び歩いてたしね。自分が束縛されたくないから彼のことも束縛する気は一切ない。
──自著の中だと、中村さんのホスト通いに旦那さんは反対していたようですが。
中村 ああ、それは恋愛感情とか嫉妬ではなく、家族が変なカルト宗教にハマっているときに「あんた騙されてるよ! 目を覚ませ!」って言いたくなる気持ちだったみたいね。ところが私はどこ吹く風で、「うるさわね! 自分のお金を自分の好きなように使って何が悪いの!」って逆ギレする始末。冷静に振り返ると、これ以上ないくらいのダメ妻ですよね。
──しかし旦那さんにとっても、結局は中村さんが必要な存在だったんじゃないですか。じゃなかったら、とっくに別れていると思います。
中村 そこのところは彼に聞いてみないとわからない。だけど奉仕するのが好きな人ではあると思うんです。弱った猫を道端で見つけると、すぐ拾ってきたりしますしね。そうやって考えると、彼にとって今の私は弱った猫なのかもしれないな。放っておけない存在なのかも。こういう見方は、彼の善意に対して失礼かもしれませんけどね。
今はこうやって私が一方的に彼の世話になっているわけだから、どうしても「ごめんね」と言うことが多くなるんです。それに対して彼は「そんなことはない。あなたは私にいろんなものを与えてくれたから、これはお返しなの」と言ってくれるんですね。たしかに彼は私のおかげで日本に住めることになった。それに彼は虚弱体質なうえに社交性もないから、そんな様子を見かねて「もう働かなくていい! あなたの生活の面倒は私が見る!」と言ったことがあるんです。「1人くらい養ってやれるわよ!」と自信満々だった。税金は納めていなかったですけど(笑)。今は収入も減ったし、そのころと比べるとつつましい生活を送っていますが。
【後編:中村うさぎが考える夫婦の在り方、この先の人生——そして、今振り返る番組降板騒動の真相。を読む】
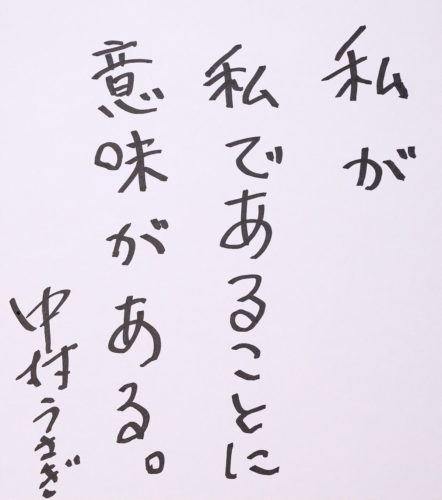

【プロフィール】
中村うさぎ(なかむら・うさぎ)
◎1958年、福岡県生まれ。同志社大学文学部英文科卒。OL、コピーライターを経て、ジュニア小説デビュー作『ゴクドーくん漫遊記』がベストセラーに。その後、壮絶な買い物依存症の日々を赤裸々に描いた『ショッピングの女王』がブレイク。著書に『女という病』『私という病』『あとは死ぬだけ』など。