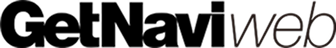『ザリガニの鳴くところ』(ディーリア・オーエンズ・著/早川書房・刊)は、「これはアメリカ文学だ」と意識しながら読み始めた1冊です。
これまでは、どこの国の作品かをとくに考えることもなく本を選んできました。残念ながら、私には英語と米語の区別もつかず、原文で読む語学力もありません。そこで、今までは翻訳された本をただ楽しみ「あ〜、面白かった」で終わっていたのです。

2019年のアメリカで一番売れた本
本の帯に”2019年アメリカで一番売れた本”とあったことも、好奇心に火をつけました。アメリカ人が今、どんな本を好むのだろうと急に気になったのです。まして、昨年の売上げが、全米で500万部を突破しているというのですから、これは読まずになるものかっ! となりました。
2019年といったら、アメリカが新型コロナウイルスで苦しむ前のことです。国内外に問題を抱えていると言われてはいますが、それでも世界一の大国として安定した状態を享受していたはずです。
けれども、ほんの数か月で状況は変わってしまいました。アメリカは今、新型コロナウイルスに苦しみ抜いています。人々は目には見えないウイルスに怯え、握手やハグもできず、家に閉じこもって暮らす孤独な生活を強いられています。
こんなときだからこそ、『ザリガニの鳴くところ』のような書物が、その力を発揮するのではないでしょうか。物語の主人公は、あり得ないほどの孤独に耐えて生きるカイアという名の少女なのですから。
「湿地の少女」の正体は?
物語は、アメリカ合衆国の南東部に位置するノース・カロライナの湿地で、チェイス・アンドルーズという名の若い男の死体が発見されたところから始まります。
温暖で湿潤な気候として知られるこの土地で、彼は生まれ育ちました。若く、快活で、人生を楽しんでいた青年でした。自殺は考えにくいものの、事故なのか殺人なのかはっきりしません。
チェイスは有力者の息子です。それだけに警察は必死の捜査を開始しますが、なかなか進展しません。次第に疑いの目は湿地で暮らす一人の女性・カイアに向けられます。
彼女は6歳のころからたった一人で、湿地の中にある掘っ立て小屋のような家で生きてきました。家庭が崩壊し、捨て置かれてしまったのです。学校にも行かず、貝を掘り、それを売りながら、どうにか自活する日々……。毎日が生き残りをかけた戦いです。
けれども、カイアには「自然」という偉大な先生がいました。ひとりぼっちではありましたが、湿地で共に生きる鳥や貝、キノコに育まれ、共に暮らし、美しい女性に成長します。カイアに好意を持ち、字を教え、本をプレゼントしてくれるボーイ・フレンドもできました。そんな彼女にようやく幸福が訪れるかと、胸をなで下ろしたそのとき、事件が起こったのです。
ミステリー? それとも、愛の物語?
読み終わった後、私はしばし呆然となりました。何とかして、この小説の核となる部分をお伝えしたいと思うのですが、物語の詳細を書くのは、これから読む方達の楽しみを奪ってしまうでしょう。
とくに、エンディングは絶対にお知らせするわけにはいきません。となると、いったい何をどう書いたらいいのだろうと、キーボードを叩く手が止まってしまいます。
『ザリガニの鳴くところ』が、いったいどのジャンルに属する小説なのかも私にはよくわかりません。舞台として描かれる湿地の描写が秀逸なので、自然を描いた文学のように思えます。ナショナルジオグラフィックを見ているようです。
ところが、主人公であるカイアの成長を描くという点では、一人の女性の伝記でもあります。アメリカのドラマでよく用いられる手法ですが、著者は物語を年代によって書き分けています。
幼いカイアが成長していく1952年以降の年代と、事件の捜査が行われる1969年との間を行ったり来たりしながら話が進んでいくので、最初はちょっと戸惑うかもしれません。けれども、慣れると自分もカイアと共に、湿地のまんなかで一緒に年を経ているような気持ちになります。
カマキリや蛍を観察する筆致も細かく専門的です。その意味では、優れた昆虫記のようでもあります。何よりも、最初の登場人物が死体なのですから、ミステリーの要素もたっぷりです。
著者ディーリア・オーエンスについて
『ザリガニの鳴くところ』の著者・ディーリア・オーエンズは、幼いころから自然の中で育ったそうです。
文章を書くことが大好きで、小説家になりたいという夢を持っていました。結局、カリフォルニア大学のデイヴィス校で動物行動学の博士号を取り、動物学者となりました。
夫のマーク・オーエンズと共にカラハリ砂漠で調査を行い、『カラハリ アフリカ最後の野生に暮らす』などの著書を生み出し、数々の賞も受賞しています。
けれども、彼女は小説家になりたいという夢を捨てませんでした。69歳になったとき、この『ザリガニの鳴くところ』を執筆したといいます。そう、この本は彼女の処女作なのです。
小説を書くことに年齢は関係ないのでしょう。定年もありません。書きたいという情熱さえあれば、死ぬまで書き続けることができるでしょう。反対に、子どもでも書き始められます。
物語を創るのは自由で深い作業だと私は思います。空高く飛ぶような快感もあれば、ずぶずぶと泥沼にはまっていく絶望も味わうでしょう。ディーリア・オーエンズは、希望と絶望、その両方を身をもって示した希有な女性だと思います。
湿地を眺め、物語にはまる
『ザリガニの鳴くところ』を読んで、小説の主人公とは必ずしも人間である必要はないのだと思うようになりました。
もちろん、主人公のカイアは、魅力的な少女です。家族に捨てられたとわかっていながら、母親や兄を慕い続けるけなげさには心を打たれ涙が出ます。
生き残りをかけた戦いに手を貸す船着き場の燃料店の主・ジャンピンや、彼女を愛するがゆえに悩み苦しむ青年テイトにも共感を覚えます。それでも、カイアに生きる力を与えたのは、彼女が暮らした湿地だったのだと思います。そして、この湿地こそが物語の真の主人公だと思うのです。
湿地にいたから、彼女は孤立してしまいました。
湿地から出ようとしないから、学校にも通えませんでした。
湿地にいるから、不気味だとして遠ざけられました。
けれども、湿地こそが、カイアに壮大な自然の営みを教え、食物を与え、育んでくれたのです。オーエンズは物語の最初に書いています。
湿地は、沼地とは違う。湿地には光が溢れ、水が草を育み、水蒸気が空に立ち昇っていく。(中略)そして、その湿地のあちこちに、本当に沼地と呼べるものがある。(中略)泥だらけの口が日差しを丸呑みにするせいで、沼地の水は暗くよどんでいる。
(『ザリガニの鳴くところ』より抜粋)
自然は美しいだけではないと、著者はよく知っています。沼地は「生命が朽ち、悪臭を放ち、腐った土塊に還っていく。そこは再生へとつながる死に満ちた、酸鼻なる泥の世界なのだ」とも書いています。
きれい事ではいかない世界。美しいと眺めているだけでは何も与えてくれない自然界。生き残るために起こる残酷な出来事。そうした多くの要素が混じり合い、発酵し、腐り、そして再生する、それがこの物語の主人公である湿地です。
私は『ザリガニの鳴くところ』を何度か読みましたが、今、また読み返しています。そうしないと、湿地に足をとられ、身動きがとれなくなってしまうからです。まさに「はまった」と、言っていいのかもしれません。
【書籍紹介】

ザリガニの鳴くところ
著者:ディーリア・オーエン
発行:早川書房
ノースカロライナ州の湿地で男の死体が発見された。人々は「湿地の少女」に疑いの目を向ける。6歳で家族に見捨てられたときから、カイアはたったひとりで生きなければならなかった。読み書きを教えてくれた少年テイトに恋心を抱くが、彼は大学進学のため彼女を置いて去ってゆく。以来、村の人々に「湿地の少女」と呼ばれ蔑まれながらも、彼女は生き物が自然のままに生きる「ザリガニの鳴くところ」へと思いをはせて静かに暮らしていた。しかしあるとき、村の裕福な青年チェイスが彼女に近づく……みずみずしい自然に抱かれた少女の人生が不審死事件と交錯するとき、物語は予想を超える結末へ──。