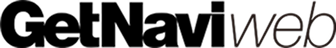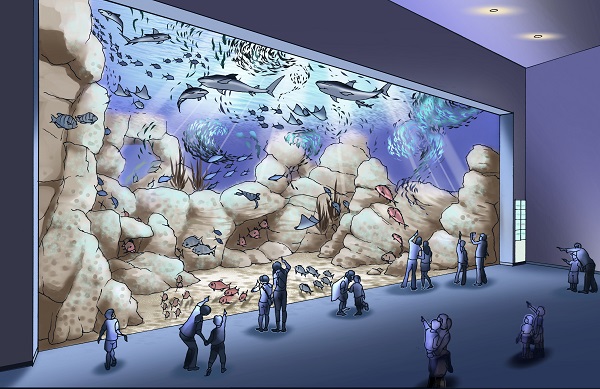現在78歳、「人生の最後に新しい笑いを作りたい」と意気込む萩本欽一さんのインタビューを2回に分けてお届けする。3時間にも及ぶ取材の中で触れた話題は多岐に渡り、現在のテレビ界に思うことから知られざる幼少期のエピソードまで熱く語ってくれた。「視聴率100%男」と呼ばれた欽ちゃんが見据える、お笑いの過去・現在・未来──。
(企画・撮影:丸山剛史、執筆:小野田衛)
頭が”お利口モード”になっちゃうから自主退学!?
──今日は長いインタビューになりますが、よろしくお願いします。こういった取材は最近よく受けるんですか?
萩本 そうね。ほら、僕の場合はずっと大学に通っていたから。その間に来る取材は「年を取ってからの生き方」とか、そういったテーマが多かったかな。もっとも今はその大学も辞め、こうして芸能の世界に戻ってきたわけだけどさ。
──では、そこから伺いたいと思います。駒澤大学に入学した際は大々的に報じられていましたが、自主退学したのはどういった理由でしょうか?
萩本 ひとつあるのはTwitterの存在。僕の場合、Twitterはネタを募集したりするのに使っているの。昔は番組内でハガキを読んだりしたけど、それと同じ感覚だよね。それでTwitterの投稿を読んでいると、「昔、欽ちゃんの番組で腹を抱えて笑いました」というのがあったわけ。腹を抱えて笑った……この言葉が、すごく自分の中で引っかかったんだ。たしかに僕はコント55号のときに腹を抱えるような笑いを追求してきた。それは間違いない。だけどそのあとテレビで冠番組を持つようになってからは、腹を抱える笑いとは違う方向に進んだという自覚があるわけですね。だから最後にもう一度、腹を抱える笑いに全力で取り組みたいと、そう考えたわけです。
──原点回帰というわけですか。
萩本 そういうこと。後世の人が振り返ったとき、「欽ちゃんというのはコント55号で舞台の腹を抱える笑いから始まって、一度はテレビの世界に行ったけど、最後は再び腹を抱える笑いをやりながら亡くなったね。最期に作った笑いも面白かった」と語るような感じが理想かもしれないな。じゃあ、どうやってその笑いを作るのか? (坂上)二郎さんがいれば、それは簡単な話なの。でも、今は二郎さんがいないじゃないですか(※2011年、没)。だから僕が「第2の二郎さん」を作るしかない。これは時間がかかる作業ですよ。3年くらいはかかると思う。そういうこともあるから、少なくてもあと3年は長生きしたいと僕は考えているんだけどね。
──つまり理想のお笑いを作り上げたいから大学を中退した?
萩本 大学というのは、脳をまともにしていく場所なのよ。これ以上、勉強すると、笑いにマイナスになると僕は考えたわけ。最初、僕が大学へ行こうと思ったのはボケ防止のためだったんだけどね。だけど通ってみたら、どんどん頭が”お利口モード”になっていることが実感できた。これはマズいと思いましたよ。年齢的にもそんなに遠回りできる時間は残されていないし。正しいことを教わって身につけるのが学問。でも、笑いって正しくないことを考え出す作業でしょ。同時にやるのは非常に難しいよね。学ぶこと自体はすごく楽しかったし、本当は辞めたくなかったんだけど。
──そうだったんですか。
萩本 笑いの頭に戻すため、2年くらい一時停止するという方法を僕は考えていたの。だけど学校側は「一時停止という制度はない。退学するか休学するか、どちらかにしてください」と言うわけ。しかも休学する場合も、学費は半分払わなくちゃいけないらしい。それから「いつまで休むつもりですか?」とも聞かれたから、「理想の笑いができるまで。だから、いつまでかかるかわかりません」って正直に答えたんだけどね。そういうアバウトな考え方というのは、どうにも大学のシステムにそぐわないんだよ。大学職員も困惑していたからさ。
──前例がないでしょうしね。
萩本 「いい笑いができたら復学」なんて規約は大学に存在しないの。もうお互い会話がまったく噛み合わないんだから。こっちも話しているうちに頭が痛くなってきちゃってさ。「だったら、もう辞めます」みたいな感じになったわけ。学生証を返してくれって言われたときは、さすがに納得いかない気持ちになりましたけど。「こっちは別に辞めたくて辞めるわけじゃないのに……」って。向こうも向こうで「ここで辞めるのはもったいないです」と言っていたけど、そういう問題じゃないよね。
──仏教学部でしたよね。ボキャブラリーを増やす目的があったと自著の中でも書かれていましたが。
萩本 だけど実際に通ってみると、学問の言葉というのは難解なのよ。テレビで使える言葉とは根本的に違うの。そこは見込み違いというか、僕の考えが甘かったところかもしれない。だからといって僕にとって大学が無意味だったといえば、そんなことはまったくないけどね。一番の収穫は、今の若者が理解できたということ。普通の若者と会話できたことは、僕にとっても大きな財産でした。さらにいうと、学ぶことの楽しさを生まれて初めて知った。これも非常に大きかったね。
──大学合格した時点で74歳でした。
萩本 小学校、中学校、高校と僕は先生の話をまったく聞かない生徒だったのね。話を聞かないから内容がわからない。わからないから勉強がつまらない。こういう悪循環だったんです。それで大学に入って改めて先生の話をちゃんと聞いてみると、これがとてもいい話をしているわけ。勉強ということも忘れて、普通に感心して聞いちゃうくらい。で、また先生も情熱的に話してくれるんだよね。そこで僕はこう考えたんです。「これだけ熱心に先生がためになる話をしてくれるんだから、試験で70点とか取っているようじゃ失礼だな」と。だから僕は常に80点以上を取っていましたよ。
──ただ一方で、試験をあえて受けないでF判定をもらったことも多かったとか。
萩本 それは1年生のときね。1年のときはたしかに全部ブン投げたりしていた。というのも、同級生に「欽ちゃん、単位取得のルールは知ってる?」って訊かれたの。なんでも授業に全出席すれば50点。さらに小テストがあるからプラス10点。これだけで勝手に60点はいくんだよね。僕は真面目に授業に出ていたから、仮に試験が全然ダメだったとしても進学できるわけ。若い大学生は単位が取れればそれでいいかもしれないよ。でもさ、勉強って本来はそういうものじゃないでしょ。そもそも大学って社会に出てから役に立つ知識を身につける場所なんだから。「何も身についていないけど、単位は要領よく取りました」なんて人材を企業が欲しがるものなのかねぇ。そういう単位を取ろうとする姿勢が僕にはバカらしく感じたから、試験で70点くらいしか取れなさそうな場合は、あえて受けずに単位を落としたんだ。同級生からは「何やってるの?」って思われただろうけど。でも、僕に触発されて試験を受けなかった学生もいたな。若い坊さんだったけどね。あの子には悪いことをした(笑)。
「欽ちゃん、友達になろうよ」に驚く!
──若者に対する見方は、どう変わりました?
萩本 男と女のつき合い方が確実に変化しているよね。一番驚いたのは、1年生のときにクラスの女の子から「欽ちゃん、友達になろうよ」って言われとき。
──なんという馴れ馴れしさ! 芸能界の超大御所相手に距離の詰め方がすごいですね。
萩本 そのへんは何ひとつ臆するところがなかった。こっちは何十歳も離れている女の子から、いきなり「友達になろう」なんて言われるとは予想もしていなかったわけ。オタオタしちゃって、気の利いた言葉のひとつも返せないでさ(苦笑)。それで彼女とは大学4年生になったとき、もう一度その件を話したのよ。「あのときの『友達になろうよ』だけどさ、あれはどうやって返すのが正解だったんだろうね。僕はずっとそのことを考えているんだけど、いまだに答えが出ないんだ」って。そうしたら彼女は言ったんだ。「そんなの簡単じゃない、欽ちゃん。『もうすでに友達だよ』って言えばよかったのよ」。もうね、完全に一本取られたと思った! すごい感性ですよ。僕の発想にはないことをアドリブで返してくるわけだから。我々の世代は「ここから知り合い」「ここから友達」「ここから男女」みたいなことを理屈で考えがちなんだよね。
──世代論的に、若い人のほうがコミュニケーション能力が高いということですかね。
萩本 そこは微妙なところだけどね。ひょっとしたら、その彼女がたまたま洒落たことを言えるタイプだったのかもしれないし。いずれにせよ、この年齢になった僕も新たな発見と驚きがあったのは事実ですよ。「友達になろうよ」に「もう友達だよ」……この発想は目から鱗だったなぁ。その気づきがあっただけでも、大学に行った意味があったのかもしれない。それから「テレビをやってきて本当によかった」と痛感したこともあった。
──どういうことでしょうか?
萩本 ある教授が「どうしても欽ちゃんに会わせたい人がいる」と言ってきたわけ。その人は教授と一緒にいる女性の事務員なんですよ。で、会ってみたら「私は欽ちゃんで育った世代。『欽どこ(欽ちゃんのどこまでやるの!?/1976年~1986年)』の公開収録でスタジオに遊びにいったこともあるんです」と話し始めたのね。
──月曜日の『欽ドン!』シリーズ(1981年~1987年)、水曜日の『欽どこ』、金曜日の『欽ちゃんの週刊欽曜日』(1982年~1985年)。一時は民放3局をまたいでゴールデンタイムに番組を持っていて、文字通り国民的存在でした。
萩本 ありがたいことにね。その事務員の女性も公開収録に来たのは20歳のときだったと言っていたな。そして実際に番組が放送されると、その女性のスタジオで大笑いする顔がアップで映されたらしいの。こう言ってましたよ。「ちょうどそのころ、うちの父と母の間には離婚の話が持ち上がっていたんです。だけどオンエアされた私の笑顔を見て、母が父に伝えたそうです。『お父さん、この子の笑顔をなくさせることはやめましょう』って。だから私、欽ちゃんにはどうしてもお礼を言いたくて……」。
──めちゃくちゃいい話ですね。
萩本 さすがに僕も考えちゃったよね。笑いをするうえで、僕は人の害にならないようにしようと心がけていたのね。でも、人のためになることをしているとは想像したこともなかった。ところが実際は、テレビの笑いが人の役に立つことだってある。そんな話を聞いちゃったらねぇ……新しい笑いをきちんと作らないといけないなって、しみじみそこで考えました。それが大学3年生のときなの。さっき言ったTwitterでの「腹を抱えて笑いました」という書き込みと、事務員さんのご両親の離婚回避話。この2つが僕の中では決定的だったね。自分の軸足を笑いに移さないとダメだと思った。
素人のほうが名人芸に近い?
──そして今、力を入れている番組がNHK-BSの『欽ちゃんのアドリブで笑(ショー)』ということになります。この番組を始めた意図は?
萩本 今、テレビの笑いというのは「言葉」になっているわけですよ。もちろんコントだってあるけど、それは言葉のコント。その点、コント55号は「動き」のコントだったからね。そこがポイントになってくる。
──「第2の二郎さんを見つける」という発言もありましたが、萩本さん自身が若手の中から発掘するということですか?
萩本 なにも若手とか素人に限定しているわけじゃないんだけどね。でも、自分の笑いが確立しているベテランは逆に難しいという面はあるよ。むしろ笑いについて何も知らない人をイチから育てるほうが話は早いと思う。究極的なことを言うと、この番組では僕や先輩たちが浅草でやっていたコメディ……あれを復活させたいんです。
──萩本さんのキャリアの出発点ですね。
萩本 浅草の軽演劇では、たとえば僕のちょっと上の世代に渥美清さんがいたの。コメディアンというか、いわゆる喜劇俳優だよね。僕がテレビをやる中で素人みたいな人をなぜ重宝したかというと、そっちのほうが浅草の名人芸に近いからなんです。
──素人のほうが名人芸に近い? 矛盾するようにも聞こえます。
萩本 いや、矛盾しない。というのも名人とか達人と呼ばれる人たちは、芸がわざとらしくないんです。これはある意味、素人芸に近い。名人芸を極めていったら素人っぽくなるというのは、笑いの世界ではよくあることなのよ。だから僕が自分の笑いを追求するときに、素人っぽい要素はすごく重要。もっと細かく言うと、最初から素人だけを探しているわけじゃないんだよね。名人を探していたら、結果的に素人が目に留まるということなんです。
──見栄晴さん、斎藤清六さん、わらべの3人……たしかに欽ちゃんファミリーは素人っぽさを残したメンバーが多かった印象があります。
萩本 うん、今もそこを狙っているという部分は変わらない。二郎さんっていうのは名人だったけど、すごく素人っぽいところもあったのよ。だって、二郎さんって次の日もまったく同じように失敗できるんだから。見ていたら、「この人はまるで素人みたいだな」って感じるはずなんだ。だけど、実は素人って昨日とまったく同じように失敗できないのよ。たまたま失敗しただけだから、その日の失敗はその日だけしかできないわけ。プロだからこそ、素人っぽく見せる。だけど素人とは明確に違う。そこなんですよね、僕が目指しているのは。すごく難しいことではあるんだけど。
──深い……。そして坂上二郎さんの天才性に改めて驚かされます。
萩本 たとえばコント55号には「飛びます、飛びます」というギャグがあるでしょ。「あれをやってくださいよ」って言われたとき、普通の芸人さんだったら喜んでやると思うんだよ。自分たちの持ち芸なわけだし。ところが、二郎さんは「飛行機やって!」と求められてもすぐにやらないのよ。「俺も40近いからさ。あまりみっともないことはやりたくないんだよなぁ」みたいな感じで躊躇するわけ。この間が重要なの。振られてもマゴマゴしちゃって、まるで素人みたいだなって思うじゃない。でも、そのあとで楽しくなっちゃって、振り切れたように飛び回る。そこが面白いんだよね。
──なるほど。ギャップの妙みたいなものですか。
萩本 僕の考えだと、芸を覚えて3年目から9年目くらいの人は使えないんだよね。10年目くらいから、逆に素人に近づくところがあるんだけど。でも、こういう面白さって口で説明するのが難しいの。だから育てるのも難しい。世間からすると「欽ちゃんは頑張って素人を育てているんだね」ということになるかもだけど……まぁ本当は育てちゃなんていなくて、勝手に育っているだけなんだけどさ(笑)。それはさておき、本当のところはずっと名人を探し続けてきただけなんだよ。我々の世界では「ブチ込み型」というんだけど、若い芸人さんなんかはすぐ自分の持ちネタを披露するでしょ。
──観客のニーズに応えているんでしょうけど、観客に媚びているという言い方もできるかもしれません。
萩本 そうなんだよ。実際、劇場のファンの子はそれで喜ぶだろうから。僕だって、それを止めるような真似はしません。だけどテレビで数字を取ってくれって言われたら、話は別。「世間一般に広がっていくか?」という角度で考えると、厳しいものがあるよね。だから僕が自分でやった番組では、そういうことは一切させていない。やっぱり大人の人にも観てもらいたいですから。
『欽ちゃんのアドリブで笑』は人生の総決算
──かつては「視聴率100%男」とも称されましたが、さすがに今のNHKでやっている番組では数字のことは意識していない?
萩本 数字に関していうと、「コント」って銘打つとなかなか伸びないものなんだよね。テレビ番組欄に「コント」って書かれていると、笑わせてくれるんだなって誰でもわかるじゃない。そうすると、どこかで身構えちゃう。僕の理想は「今から笑わせます」というのではなく、「思わず笑っちゃった」というかたち。でもね、この理想の笑いを完成させるのは時間がかかりますよ。本腰を入れないと無理だし。だから僕は『欽ちゃんのアドリブで笑』を「最後の仕事」と言っているんです。
──人生の総決算的な位置づけというわけですね。
萩本 新しい笑いが作れないんだったら、やる意味がないよ。体力も落ちている中、わざわざ僕が笑いに戻る理由もないしね。
──そこが疑問だったんですよ。萩本さんの場合、すでにお笑いの世界で確固たるステータスを築いているわけじゃないですか。余計なお世話だと思いますが、金銭的に困っていることもおそらくないかと思います。番組の収録は苦労も絶えないはずなのに、なぜあえてその道を選択するのか? モチベーションは何になるんですか?
萩本 釣りをやる人の中には「フナに始まりフナに終わる」という言葉があってね。笑いもそれに近いんじゃないかと僕は思っているの。最後は原点に戻って、腹を抱える笑いを作りたい。浅草の笑いで終わらせたいのよ。もうそう考えるようになった時点で、大学に行っている場合じゃなかったわけ。大学側と休学について話し合ったとき、僕は「いつ戻れるかはわかりません」と伝えた。でも、本音では「大学に戻れる時期が来たとしても、そのころに僕は死んでいるだろうな」と考えていました。
──いやいや、そんな……。
萩本 でも、これは冗談じゃなく本当の話よ。それくらい長期戦になると睨んでいたし、それくらいの覚悟で取り組んでいますから。
「動きの笑い」と「言葉の笑い」
──今のお笑いシーンに対して感じることはありますか?
萩本 コント55号でやっていたのは、動きのある笑い。当時の僕らは「腹を抱えて笑ってもらうためには、これしかない!」と確信して、あれをやっていたわけ。だけど、55号の笑いというのはテレビ向きではないじゃない部分があった。どういうことかというと、テレビというのは平面でしょ? それに対して舞台は奥行きがあるじゃない。僕らは舞台で縦横無尽に動き回っていたし、場位置も照明の段取りもまるで関係なかった。でも、その立体的な動きをテレビで再現するのは不可能なんだよ。それから間の問題もあったね。テレビってカットして編集するメディアでしょ。僕らが作った間なんて関係なくなっちゃう。そういうこともあって、テレビの中で舞台の芸を追求してもしょうがないって気づいたの。それで、どうしたか? 動きではなく、言葉の笑いを追求することにしたんです。それがテレビに合った笑いだと僕は思ったので。その典型例が『欽ドン!』だったんですよ。
──そういう流れがあったんですね。
萩本 それで今テレビをつけると、みんな言葉の笑いになっているでしょ。僕からすると、若手の人たちは言葉の使い方がすごく上手だなって感心しますよ。僕なんか全然かなわないくらい、言葉の達人がたくさんいますから。昔に比べて、言葉という意味でレベルは確実に上がっている。
──となると、その礎を築いた萩本さんが偉大だという話になりませんか?
萩本 そう言っていただけると光栄だけどね。そして、すべての若手芸人たちに僕は抜かされていったと……。
──そんなことはないです(笑)。
萩本 実際、それくらい思われてもいいのよ。よくぞ、ここまで若手が育ってくれたなという喜びしか僕にはないし。ただ、ここからテレビも変わっていくかもしれないね。だって、いよいよ4K、8K放送になっていくわけでしょ。「深み」という概念をテレビが表現できるようになったら、また動きの笑いが求められるかもしれない。
──時代が一周して、コント55号に戻るというわけですか。
萩本 ところが、そうなったときに誰も動きの笑いをやっていないのよ。みんな言葉の笑いに走っているわけだから。違うことをやる必要なんてなかっただろうしね。でも、今の若い人は本当にすごいよ。ネタなんてなくても、ポッと舞台に立てば言葉で面白くすることができちゃうんだもんなぁ。
──萩本さんから見て、「こいつはすごい!」と唸るような若手とは具体的に誰ですか?
萩本 いや~、全員がすごいよ。それぞれ違うすごさがある。たとえばダウンタウンはダウンタウンの言葉を生み出したと思うし、それは他の人たちだってそう。今、一緒にやっている(劇団)ひとりとか澤部(佑)にしても、いつも感心しちゃうもんね。1個テーマを与えると、彼らはナンボでも転がしていけますから。
──浅草の劇団で育った萩本さんと劇団ひとりさんでは、笑いの共通言語があるんですか?
萩本 それが面白いところで、ひとりや澤部は僕の笑いに寄せてくるの。僕が「こういう笑いをやりたいから、こうやって……」とかいちいち説明しなくても、彼らは勘がいいから気づくんだよ。そういう意味でも、すごいなって感心した。それとこれは自分が仏教を専攻して知ったことなんだけど、4年間「勉強する」わけじゃなくて「修行する」という発想なんだよね。
みんな本当の笑いに気づいていない
──ん? 勉強と修行の違いとは?
萩本 「教わる」じゃなくて「気づく」。この差だね。でも思い返してみると、浅草時代の先輩コメディアンはいつも僕に「お前、もっと修行しろ!」って言っていたわけ。仏教と笑い……まるで関係ないように思えるじゃない。でも、確実に繋がっているなって僕も驚いたよ。要するにね、勉強して覚えたことよりも、自分で考えて気づいたことのほうが考え方に幅が出るということなの。ひとりや澤部は放っておいても修行できるタイプだったし、これからは企業だって部下に修行させるところが伸びるんじゃないかな。マニュアル通りに「相手からこう言われたら、こうやって言い返せ」とか勉強するのではなく、自分で気づいていける環境づくりを社内で進めるとかさ。逆にいうと、これからは「何をすればいいんでしょうか?」とか指示を待っているようじゃダメで、自分でどんどん気づいていかなくちゃいけない。
──今、日本企業は国際競争力が低下していますが、そういうところに状況打破のヒントがあるかもしれない。
萩本 そうね。だって日本はますます勉強社会になっているでしょ。でも、それじゃ世界で勝てないですよ。日本人はもっと修行しないとダメだと思う。僕が今やろうとしているのは、笑いの世界で修行システムを作ること。これが上手くいったら、どこかの企業が「わが社も欽ちゃん式の修行を……」とか言い出すかもしれないね(笑)。
──たしかに昔から芸人は「芸を盗め」という言い方をします。
萩本 共演者に「こうしてくれ」って言うと、どうしてもそれは勉強になっちゃうのね。言われたほうは「わかりました。その通りにします」って萎縮しちゃうでしょ。だから今は極力、僕のほうからああだこうだと言わないようにしているの。
──最近は人々がテレビを観なくなったと言われています。また、芸人志望の若者も主戦場をテレビでなくYouTubeに求めるパターンが増えています。こういった現象をどう思いますか?
萩本 ひとつ言えるのは、「本当に面白い笑い」に気づいていないんじゃないかということ。面白い笑いがどういうものかを知ったら、当然、YouTubeよりもテレビを、テレビよりも舞台を選ぶようになりますよ。収入面だけを考えたら、「YouTuberのほうが儲かるから、テレビで戦うのは損」という考え方も成立するかもだけどね。僕、わからないんだよ。YouTubeならではの笑いというものが。自分でやろうとも思わないしさ。やっぱり僕はテレビに育てられた人間じゃない。テレビの可能性や面白さを知っているし、お世話になったという気持ちもある。だから最後までテレビとともに歩みたいんだよね。たしかに今は人々が昔ほどテレビを観ることがなくなっているし、バラエティの視聴率が20%を超えることは少ないかもしれない。でも本当に面白い番組が作れたら、30%を取ることもできると思うよ。
最初の給料は「要らない」!?
──吉本興業のお家騒動については、どうご覧になっていますか?
萩本 意外とみんな気づいていないんだけど、この仕事で一番大事なのは運なんだよね。運をどうやって引き寄せるかっていうのが勝負どころなわけ。僕の最初の給料なんて、割合でいうと9:1でしたよ。当時はそれこそ修行だから、「それで何が悪いの?」と思っていたし。むしろ9:1の1を「要らない」って(浅井企画の)社長に返そうとしたくらいだから。
──浅井良二前社長も面食らったんじゃないですか?
萩本 そのとき僕が言ったのは「社長はお金が欲しいから事務所を経営しているんでしょ? だったら、あげますよ」って。それから領収書を会社に持っていったら、必要経費として現金を渡してくれるという制度もあったの。だから弟子が必死で領収書をかき集めていましたよ。それで二郎さんの分も含めたら、月30万円くらいになったのかな。そこで僕は弟子に伝えました。「お前ねぇ、社長はお金が好きなんだよ。こうやって領収書を持っていくのは、社長が不幸になるってことだから。それは絶対やめなさい」。弟子は口をポカーンとさせていたけどね。それでも、その場で30万円分の領収書を破かせたよ。我々は運を使う仕事なのよ。目先のお金よりも、番組が当たるほうがはるかに重要でしょ。
──なかなかそこまで割り切れる人もいないと思いますが。
萩本 あるとき、社長は僕に言ったけどね。「欽ちゃんには、いっぱい儲けさせてもらったね。これからは欽ちゃんも、自分でたくさん儲かるようにしてほしいんだ」って。最初はどういうことかわからなかったんだけど、要するに自分の個人事務所を社長が作ってくれて、そこに会社からお金が入るようなかたちにしてくれたの。その頃になるとギャラの額も一桁違ってきていたから、本当に儲かるようになったタイミングで手を貸してくれたわけだよね。逆に言うと最初の実入りがない段階からガツガツしていたら、こんな話にはならなかったかもしれない。
──「損して得取れ」ということですか。
萩本 社長とはパーセンテージの話もしたことあるけど、それこそコントみたいだったからね。まず社長は「俺は10%しか取らない」って、こう言うわけ。それに対して僕も「何を言ってるんだ! お世話になっているんだから、30%は取ってもらわないと困る!」って主張してね。そこからは逆の意味での押し付け合いだよ。「うるせぇな! こっちはすでに欽ちゃんで儲けたんだから、10%しか取らねぇよ!」って社長も意地になっていたから(笑)。最後は間に入った当時のマネージャーが「この話は終わらないから、間を取って20%にしましょう」って決めたんだけどね。
──しかし、浅井前社長も男気がありますね。「仏の浅井」と呼ばれていたみたいですし。
萩本 こんなこともあったよ。社長が自分の家を建てたとき、「お願いだから、欽ちゃんも建ててくれ」ってお金を持ってきて言うわけ。おそらく社長の中では「欽ちゃんの儲けで家を建てることができた」みたいな引け目があったのかもしれないね。だから僕が言ったのは「社長、申し訳ないって考える必要はないよ。そのお金は持って帰ってくれ」ということ。借金しようが何しようが、自分の力で家を建てて「俺も頑張ったな……」と感慨にふけるのがいいわけでさ。社長のお金で建てた家なんて達成感もないじゃない。
──自分の努力で勝ち取ってこそ意味がある。
萩本 そういう僕からすると、今、吉本の芸人さんがギャラの配分で揉めていることなんて意味がわからない! それからついでに言うと、公正取引委員会が「圧力をかけるな」と注意した問題。あれが話題になっていることも意味がわからない!
ジャニーさんは、僕にとってもすごくありがたい人
──ジャニーズ事務所の問題ですね。元SMAPの3人に対して番組に出演させないよう圧力をかけたという疑いがあるとされています。
萩本 それを言ったら、コント55号だってずっと圧力をかけられていたよ! 僕らは個人事務所みたいな感じだったから、ゲストに歌手の人たちが出てくれないのよ。しょうがないから、同じように個人事務所でやっていた前川(清)くんをゲストに呼ぶしかない。それで前川くんと一生懸命やっているうちに、いろんな事務所が「うちも……」みたいに言ってくれるようになったというわけ。芸能界ってそういうものだよ。
──しかし最近では、その元ジャニーズ事務所の香取慎吾さんが『欽ちゃんのアドリブで笑』に出演したと話題になりました。
萩本 ジャニー(喜多川)さんが生きていたとして、慎吾くんが番組に出ることに怒ると思う? 僕が知っているジャニーさんは、そんな人ではなかったよ。
──ジャニーさんと面識があったんですか?
萩本 うん、麻雀仲間だったんだよ。そんなに強くなかった気がするけどね(笑)。それであるとき、ジャニーさんは笑いに目覚めたらしいんだ。「大将、うちにも笑いのセンスがありそうな気がする奴がいるんだ」と言ってきたの。ここがジャニーさんのすごいところなんだけど、「センスがある奴がいる」じゃないんだよ。「ありそうな気がする」という言い方をするわけ。「だから大将、ちょっと見てくれる?」って、こう頼んでくるんだ。それでジャニーさんが実際に連れてきたのが、のちにSMAPになるメンバー。
──先見の目があったのでしょう。SMAP以前は、アイドルがお笑いをやるという文化はそれほどメジャーではなかったですし。
萩本 実際、ジャニーさんは言ってたもん。「今までは歌が売れて、女の子にキャーキャー騒がれたらよかったのかもしれない。でも、これからの時代はそうじゃない。広く世間一般に届いて、番組としてちゃんと成立させないとダメなんだ」って。ところが「SMAPを見てくれ」というこの話は、僕にとっても新しい発見があったわけ。コメディアンの修行では「間が大事」ということで、まずは言葉よりも先に踊りを覚えさせられるのね。踊りと音楽がすごく重要視される世界だから。僕も2年くらい踊りを頑張ったけど、そっちは全然才能がなかったね。
──クレイジー・キャッツもザ・ドリフターズも音楽畑ですし、そこはリンクしていたのかもしれないですね。
萩本 うん、それは間違いないだろうね。その点、ジャニーズの子たちは最初からリズム感もあるし、笑いに大事な間が取れるわけよ。今の時代に本気でコメディアンを育てようとしたら、ジャニーズ事務所でやるしかないんじゃないかと思う。最初から修行が終わっているんだもん。こんなに楽なことはないよ。ジャニーさんに僕が伝えたのは「あなたのところなら、一流のコメディアンがすぐにでも作れるよ」ってこと。実際、そのあとのSMAPが活躍していく様子を見ていたらわかるでしょ。
──話を伺っていると、ジャニーさんの着眼点も鋭すぎますね。その大胆な発想は、アイドル村の中にいるとなかなか持てないかもしれない。
萩本 本当にしょっちゅうスタジオに顔を出していたもんなぁ。『欽どこ』の収録前、僕はお茶を飲んでいたのよ。そうすると、どこからともなくジャニーさんが現れるんだよね。ジャニーズ事務所のタレントが『欽どこ』に出ているわけでもないのに。さすがに「なんなんだろう?」って思うじゃない。番組のプロデューサーは「たまたまじゃないですか。ジャニーズの若手がダンスレッスンするのに、うちの局がスタジオを貸すこともあるみたいですし」とか言っていたけどね。でも「たまたま」なんて、そんなはずがないよ。あとから考えると、ずっと研究していたんだろうね。SMAPはいろんな番組で数字を取ったわけだし。ジャニーさんは、僕にとってもすごくありがたい人だったよ。いろんなことを教えてくれたね。


【プロフィール】
萩本欽一(はぎもと・きんいち)
1941年5月7日、東京・入谷生まれ。高校卒業後、浅草・東洋劇場の軽演劇一座に加わる。66年に坂上二郎とコント55号を結成。68年から始まったテレビ番組『お昼のゴールデンショー』で人気が爆発し時代の寵児に。71年に始まった『スター誕生』からは司会業にも進出した。80年代は『欽ドン!良い子悪い子普通の子』『欽ちゃんのどこまでやるの!?』『欽ちゃんの週刊欽曜日』などが絶大な人気を博す。05年にはクラブ野球チーム「茨城ゴールデンゴールズ」を結成し監督に就任。15年に駒澤大学仏教学部に入学を果たすが、新しいお笑いを志すため19年に自主退学。近著に『人生後半戦、これでいいの』(ポプラ新書)など。
(企画・撮影:丸山剛史、執筆:小野田衛)