この肩書を名乗る者は、日本にただひとり。【製硯師 —せいけんし-】とはいったい……? 編集部がたずねたのは、浅草で1939年の創業以来、都内では希少な硯の工房を併設している書道用具専門店「宝研堂(ほうけんどう)」。今回、ここで4代目として硯を作り続けている青柳貴史さんです。
硯といっても、現代の日本に暮らす私たちにとっては普段、ほとんどなじみのない道具。小学校で書道を習ったときに使ったのが目にした最後、という人も多いでしょう。ところが、ここで20年以上に渡って硯を作り続けている青柳さんの仕事は、近年多くのメディアに注目され、特に昨年はドキュメンタリー番組『情熱大陸』(TBS)にも出演して大きな話題を集めました。
なぜなら、彼の仕事ぶりは想像を絶するほどユニークなのです。あるときは、優れた硯石を求め世界中を駆け巡るハンターに。あるときは、指先の感覚ひとつでコンマミリレベルの造形を仕上げていく職人に。そしてまたあるときは、お風呂場にまで石を持ち込んで、石紋の美しさをうっとり眺めている重度の石ホリックに!
彼がそれだけ、硯の世界に魅了される理由とはなんなのでしょうか? その根底には、筆記具としての硯の本当の姿、かつて日本にも当たり前にあった毛筆文化の豊かさを伝えたいという、純粋な思いがありました。
【プロフィール】
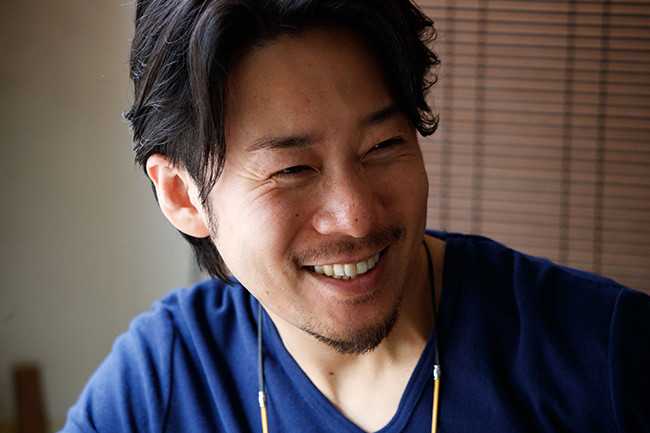
製硯師 / 青柳貴史
あおやぎ たかし/1979年、東京都浅草生まれ。16歳より祖父と父に作硯を師事。浅草の書道用具専門店「宝研堂」内の硯工房にて、4代目製硯師を務める。大東文化大学文学部書道学科で、非常勤講師としても活躍。若い世代に、毛筆文化の豊かさとその本質を伝える活動にも情熱を注ぐ。
毛筆は、誰もが日常的に使っていいもの
「みなさんは、硯というと“書道用具”のイメージがあるかもしれません。でも硯って、本来はただの筆記具。1500年前の中国でおおむねこの造形が決まって、それからほぼモデルチェンジもマイナーチェンジもされることなく、現代まで続いている、世界最古の筆記用具のひとつなんです」
硯が生まれた中国でこれが現在の形になったのは、約1500年前の唐代。その当時、書の教育を受けられたのは、皇帝をはじめ政(まつりごと)に携わる高官など限られた人間のみでした。青栁さんいわく、当時の硯は剣や宝石にも勝る権威の象徴であり、親から子へ代々受け継がれていくものでもあったのだそう。
「その毛筆は書道とともに海を渡って日本に伝わり、日常の筆記具として人々の暮らしに根付きました。だからほんの数十年前までは、日本人ならみんな何かを書こうと思ったら硯と墨、筆を使っていました。戦後、毛筆は日常の筆記具の中から少しずつなくなっていきますが、書道は芸術として残り、発展を続けていきます。すると日常生活から乖離した毛筆は、一般の書き手にとって“うまく書かなきゃいけない”ものになってしまった。
毛筆を取り巻く現在の状況というのは、ちょうど着物文化と似たようなものかもしれませんね。着物がかつてすべての日本人の普段着であったように、毛筆だって実は誰でも日常的に使っていい。それは僕がお伝えしたい硯のありかたの本質ともいえます」

硯と毛筆の本質を伝える“製硯師”
硯とは、わかりやすくいえば墨汁を調理するためのおろしがねのようなもの。それは天然の石から、人の手で削り出すことで生まれます。表面には鋒鋩(ほうぼう)という目に見えない無数の凹凸があり、ここに水を加え、墨をこすることで墨汁ができるのです。材料となる石の採石地は、日本でも宮城県、山梨県、山口県などいくつかの場所があります。現代の硯は、そういった採石地の地場産業として作られている場合が多いそう。
「地域にもよりますが、日本の製硯現場では伝統的分業制が、今でも継承されています。それらの現場には石を切る人、彫る人、磨く人といった何人かの職人さんがいます。その中で例えば、技術的に秀でている人が、やがて硯作家として活躍されるケースも。石の性質ももちろん各地で違うので、採石地ごとに、その石に合った技術や造形、文化などが受け継がれているんです」
しかし、青柳さんが活動するのは採石地とはほど遠い東京の浅草。そこで名乗る製硯師という日本唯一の職業には、いったいどんな意味や思いが込められているのでしょうか?
GetNaviがプロデュースするライフスタイルウェブマガジン「@Living」

「僕が本格的に工房で硯作りを始めたのは、幼い頃から自分を可愛がってくれた祖父が亡くなってからのことでした。ちょうど20歳くらいの頃だったのですが、その時父に丁稚奉公に行きたいと申し出たところ、父は“行く必要はない”と言ったんです。というのも、現在の日本の硯作りは、日本独自に発展した書道文化の形式に則っている部分が大きい。でも、この宝研堂で僕の祖父や父が脈々と受け継いできたのは、本来中国で生まれた硯の本質でした」

「例えば中国で作られている硯には、それが“名硯(めいけん)”と呼ばれるような優れた硯であっても、作者の名前が彫られていることは基本的にありません。古代中国において硯は権威の象徴でしたから、そこに刻むのは硯の作者ではなく、持ち主の名だったんですね。さらに、中国には1000年以上も使い続けられているような古硯(こけん)も数多く存在しますが、それらの硯に必ず共通しているのが、石の美しさが最大限に生かされているということ。つまり石より前に出てしまうような作家性を重視した造形の追究より、石を生かした結果の伝統的造形こそが製硯の中心にあるということなんです」

良質な石を見抜き、その石紋の美しさと墨のすりやすさを同時に引き出し、持ち主がいつまでも手に触れていたい、文字を書き続けたいと思ってくれるような硯を作ること。これが、採石から仕上げまですべてを担う、製硯師の仕事であると青柳さん。
「同時にそれは、硯の源流である中国でいまだ守られている考え方と同じです。その源流に習って硯製作を行っている僕らのやり方を“青栁派”と自称しているんです」

地球が1億5000万年かけて作った石で
僕らは仕事をさせてもらっている
硯の製作や修復のオーダーを受けることはもちろん、夏目漱石遺品の硯を修復で再現したり、日本では初めてとなる北海道での硯石の採石、大学で硯文化について授業を行ったりなど、とにかく仕事の内容が多岐に渡っていることでも知られる青柳さん。16歳から祖父と父に師事し、40歳を迎えたこの春までひたすら硯と向き合ってきた中で、活動のフィールドは次第に広がっていきました。
「(工房内の戸棚を指差して)そこにふたつ並んでいる石のうち、右にあるのが江西省で採れる歙州硯(きゅうじゅうけん)という石です。そして左にあるのが、広東省で生まれた端渓硯(たんけいけん)という石。いずれも、地球上で存在している硯の素材の中で、これらより優れている石は今のところないとされている石なんです。しかも文献上では、1500年前の晩唐の時代にどちらも採掘され、硯になっているんですよね。硯の本質、石の活かし方を学ぼうと思ったら、これらの名硯が生まれた文化や時代背景を知るしかない。だから僕は、30代の前半くらいから採石地にも積極的に足を運ぶようになりました」

そこであらためて感じるようになったのは“地球”だったと、青柳さんは自著「硯の中の地球を歩く」(左右社)に書いています。
「1億5000年かけて地球が作った石で、僕らは硯を作らせてもらっている。天然の素材だからこそ、己の技術でなんとかしてやろうってムキになるほど、なんともならないのが硯なんです(笑)」
硯石やそれを研ぐための砥石は、今や青柳さんにとってダイヤモンドよりも価値のあるもの。中国の険しい山へ何日もかけて調査に出向いたり、時には石を見て触るだけなく石粉を舌で舐めて(!)みたり、良質な硯作りを追求していく過程で、石とのお付き合いもより濃密なものになっていったようです。
「地球が生んだ貴重な資源を使っているからこそ、1回使って壊れるようなものを作っちゃいけない。そう思うようになりました。僕は自分で鉱脈を探すようになってからようやく、端渓や歙州がなぜ100万円なんて値段になるのかがわかるようになったんです。1000年使い続けられるものを作っていく。それも青柳派の考え方のひとつです」

硯の製作技術や石を学び、追求してきた青柳さんは、この春ひとつの面白い試みを実現させました。
GetNaviがプロデュースするライフスタイルウェブマガジン「@Living」

硯は、人に使われて初めて完成する道具
硯の製作技術や石を学び、追求してきた中で、青柳さんはこの春ひとつの面白い試みを実現させました。アウトドアブランド「モンベル」とコラボレーションして作った小さな携帯用毛筆セット“野筆”の発売です。
「良い硯を作ること、寶研堂という専門店の信頼を守り続けること。これを全うしながら、現代日本で硯を使う事柄、シーンを作っていくことも、製硯師の仕事なのではないかと思うようになりました。そこでやってみたのが、モンベルさんと製作した野筆。おかげさまで完売して入荷待ちという状況にまでなったんです。
Instagramに“♯野筆”というハッシュタグができて、河原で文字を書いている写真がアップされたりしました。今どきは書道用品店でも硯が売れないからと扱わない店が増えているというのに、なぜか全国のアウトドアショップで硯が売り切れているという(笑)。今までいろんなメディアで硯のことをお話ししたりアピールしてきた僕らにとって、こういう動きがあるってことが、一番大事なことだったと気付きました」

モンベルオンラインストア
https://webshop.montbell.jp/
野筆を手にしたユーザーは、いわゆる書道のように背筋をピンと張って書に向き合うのではなく、岩場やキャンプサイトで思い思いに筆を走らせているのだそう。
「SNSで反響を見ていると、みんな書道のようにキレイな字を書かなきゃっていうプレッシャーを感じてない。構えずに、のびのびと絵や文字を書いてるんですよね。それは、従来の僕らが考えつかなかった動き。毛筆ってやってみればすごく楽しいし、意外とどこでも使える便利な道具。みんなはそれに気づいていないだけで、毛筆を持つって実は便利なんだよってことを、僕はずっと知って欲しいと思っていて。なぜなら硯って、持ち主が使い込んで、傷ついたりすり減ったりすることで初めて完成するものだからです」
青柳さん自身、普段はメールよりも毛筆でFAXを送る派。なぜなら、パソコンを起動するよりもその方が早いし、紙に書くことで内容が記憶に残りやすくなり、メッセージを送る相手のフルネームと顔がちゃんと一致するようになるからだそう。
「浅草には、江戸すだれとか提灯のようないいものを作ってる人がたくさんいます。江戸すだれだって、実際の生活に取り入れたら実は便利なんだけれど、それに気づいてない、知らないという方も多いでしょう。毛筆も実はすごく身近なで便利な筆記具なのだから、それを現実的な選択肢として見せていくことも、僕らの仕事なんだと思うんです。いいものを作ったらそれで終わりではない。だからといって、僕は毛筆という文化、道具を後世に遺そうというような、そんな尊大な使命感のもとに仕事をしているわけでもありません。だって僕一人が硯を作り続けたところで、存続を守れるようなものじゃないですからね(笑)。そうではなく、毛筆という文化に本当に力があるならば、それは当たり前に残っていくんじゃないかな。下火ながらも、一般の筆記具のなかに筆や硯が未だ残っているのは、それに魅力があり、何より生き残っていくだけの力があるからだと、僕は思っているんです」

青柳さんがこうも石や毛筆にこだわる理由をうかがえたところで、硯づくりの現場、またそこで生み出されたお気に入りの作品を見せていただきましょう。
GetNaviがプロデュースするライフスタイルウェブマガジン「@Living」

製硯の過程
1、採石
石はブローカーから情報を得て買い付けることもあれば、自ら中国などに採石しに行くこともあります。採石地の多くは私有地や国立公園などの場所であるため、現地で採石や研究などを行っている人物とのコネクション作りも大切な仕事のひとつ。オーダーの内容によっては、石を探すところからスタートすることも珍しくありません。
2、彫り
硬度、密度など石の性質をよく鑑みた上で設計図を引きます。金鋸やスライサーを使って原石を大まかに切り出したら、その後は鑿などの道具を使って石を緻密に手彫りしていきます。彫りに要する時間は、石の硬さや硯の大きさにもよりますが、だいたい数週間から1ヶ月程度。長いものでは1年以上かかるものもあるといいます。




3、磨き
彫り以上に多くの時間を要する磨きの行程。硯は彫りによってある程度の形のベースを作った後、丹念な磨きによってそのデザインや使い心地を細部にわたって調整していきます。



4、仕上げ
硯の仕上げには、墨がけをする方法と、漆がけをしてより装飾的に艶を出す方法などがあり、持ち主の好みに合わせて施します。完成前に一度試しに使ってもらい、さらなる微調整を加えたらいよいよ出来上がり。期間は数ヶ月でできるものから、年単位でかかるものまでさまざまです。
青柳貴史 渾身の3作

石紋の美しさを見事に活かした歙州硯は、墨をするときのシャカシャカと小気味良いレスポンスが特徴なのだそう。小ぶりながらもぽってりと肉厚な造形で、思わず触れてみたくなります。

フライパンの上でバターがとろけるような感じで、とろんと墨がおりるという端渓硯。さりげない飾り彫りと、石の自然のままの表情をあえて残したかのようなフォルムが印象的です。

日本の信楽焼のような表情を持つこちらは、澄泥硯(ちょうでいけん)と呼ばれるもの。砂が堆積してできた原石から作られます。鋒鋩が力強く独特の墨あたりが特徴。たっぷりすれる大きさです。
【店舗情報】

宝研堂
所在地:東京都台東区寿4-1-11
電話番号:03-3844-2976
営業時間:9:00〜18:00(月曜〜土曜)/10:00〜17:00(第1・3日曜)
定休日:第2・4・5日曜、祝日
http://www.houkendo.co.jp/
GetNaviがプロデュースするライフスタイルウェブマガジン「@Living」
