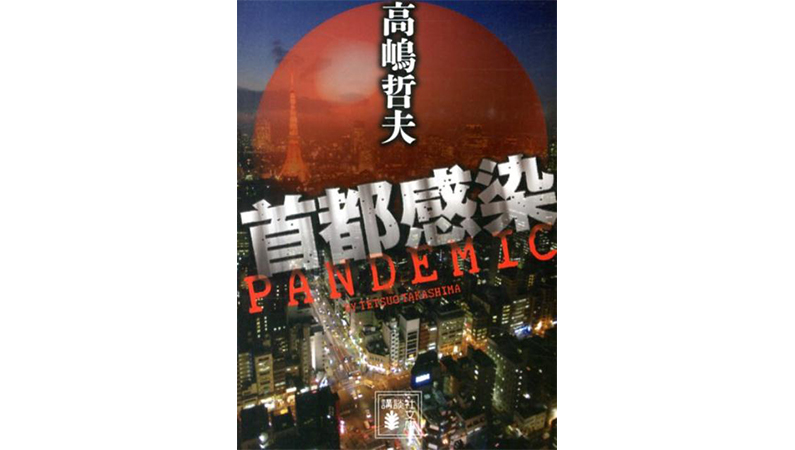不思議なもので、読むタイミングによってその本の面白さや価値が変わることがある。
たとえば、若いころに読んだときは、難解すぎて作品の奥深さを理解できなかったけれど、数年後に読み直すと、こんなにも深い話だったのか! と驚くことは少なくない。
作者はまったく同じ作品を提供している。にもかかわらず、読み手側の環境や心境、経験値によって、傑作とも駄作ともなりえてしまうのだ(作者としては、理不尽な話かもしれないが)。
さらに、そのとき話題になっている時事問題や時代背景によっても、作品の満足度は変化する。
そういった「読み時」という意味で、今ぜひおすすめしたい一冊がある。すでにご存じの方も多かろう、『首都感染』(高嶋哲夫・著/講談社・刊)だ。
2010年、今から10年前に発表された作品だが、現在の日本を予見したかのような内容なのである。
もしかしたら、昨年までに本作に接した人は、「こんな大げさな事態、ありえない」と笑みを浮かべながら読破していたかもしれない。そして今あらためて、本棚から引っ張り出し、読み返し、その予見性に恐れおののいているのではないだろうか。

世にも恐ろしい強毒性ウイルス、出現!
物語は20××年。中国の雲南省で致死率60%の強毒性インフルエンザウイルスが出現したところから始まる。世にも恐ろしいウイルスは、同じく中国で開催されたサッカーのワールドカップを観戦するために集まった観客たちを経て、世界中に拡大する。
日本の検閲も破られ、都内に感染者が発生。ここから、日本全国に拡大させないためにどうすればいいのか。出した答えは、「東京を封鎖する」前代未聞の作戦であった。
現在、第二波が来ているとも言われている新型コロナウイルスは、作中のインフルエンザウイルスほどの強毒性はない。けれども、未知のウイルスであり、日本だけでなく世界中が混沌たる状況に陥っているという意味では、同様の恐ろしさを孕んでいると思う。
ひとたび針の穴が開いてしまうと、その穴は瞬く間に大きくなり、もはやウイルスをせき止めることは不可能な状態になってしまう。だからこそ、限られたエリア内でウイルスを封じ込める。ライフラインを含めさまざまな機能は停止してしまうが、封鎖エリア外の地方都市が一致団結して、東京を支える……という施策が、『首都感染』では描かれている。
これは夢か現実か。驚くべきリアリティ
もちろん、フィクションであるがゆえ、「そううまくいくかな……?」「いやいや、そこはちょっとおかしくない?」などというツッコミどころがなくはない。
けれども、医療現場の崩壊、ウイルス防止に関わる医療用品の欠如、静まり返った街、ガタガタの経済。学校はもちろん休校、テレビをつければ感染者数のニュースか再放送の番組ばかり。作中で描かれる東京の街は、先日の緊急事態宣言時の日本の姿を彷彿とさせる。
事実、この本を数日かけて読み終えたのだが、朝起き抜けに「昨日の感染者数は……」というニュースを耳にすると、はたしてこれは小説内の話か現実か、わからなくなる瞬間があったほどだ。
『首都感染』では、極めて優秀な医師と、決断力、行動力に長けた官僚たちが空前絶後の殺人ウイルスを阻止するために画策する。
さて、2020年の日本は今後どうなっていくのか。『首都感染』のような結末を迎えることができるだろうか。
おそらく人類は、今後も幾多のウイルスとの戦いに接するだろう。いつか訪れるかもしれない強毒性ウイルスとの攻防戦のためにも、今ぜひ読んでおきたい一冊だ。
【書籍紹介】

首都感染
著者:高嶋哲夫
発行:講談社
二〇××年、中国でサッカー・ワールドカップが開催された。しかし、スタジアムから遠く離れた雲南省で致死率六〇%の強毒性インフルエンザが出現! 中国当局の封じ込めも破綻し、恐怖のウイルスがついに日本へと向かった。検疫が破られ都内にも患者が発生。生き残りを賭け、空前絶後の“東京封鎖”作戦が始まった。