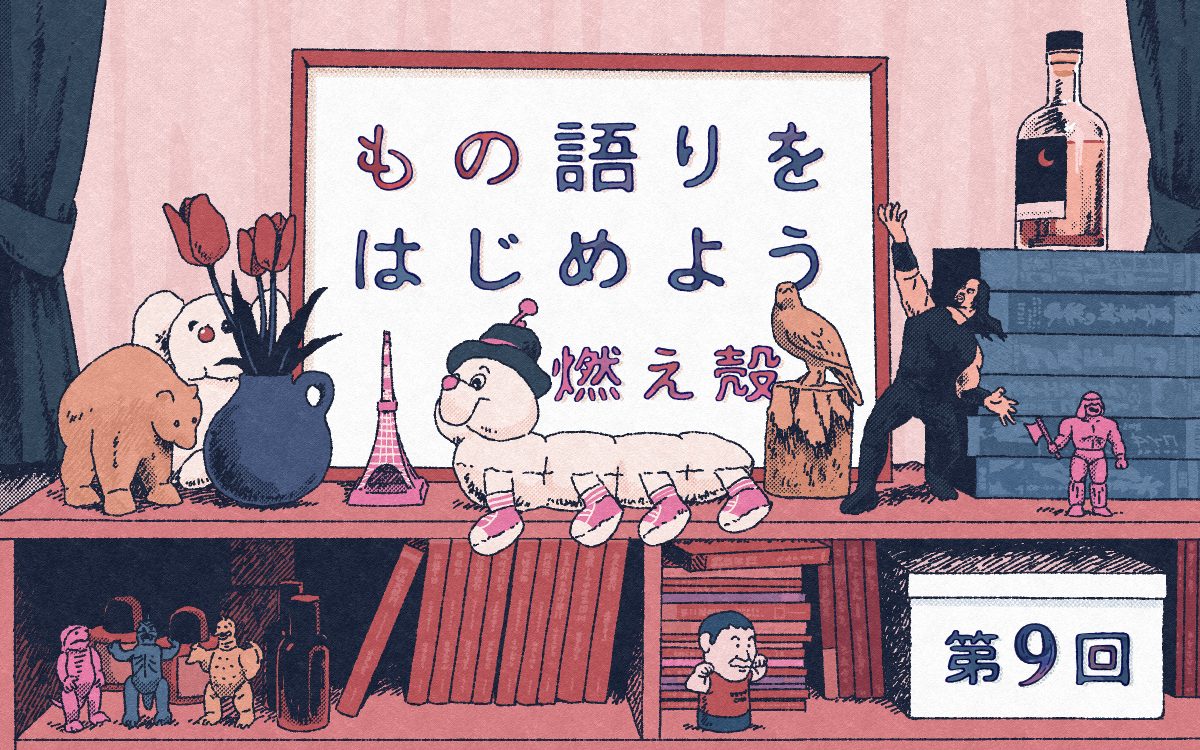第9回「なにを書いても構わない」
「阿川佐和子さんと対談」重い一行だ。
この前、そんな重量感たっぷりの対談が本当にあった。場所はANAインターコンチネンタルホテル東京。場所すら重い。間違いなくヘビー級の仕事だった。
十分前に部屋に着くと、そこには二十分前に着いていた阿川さんが、ニコニコ笑って待っていた。「よろしくね〜」と満面の笑み。そしてすぐに写真撮影。撮影中、阿川さんは冗談を交えて場を和ませてくれた。撮影はつつがなく終了し、お互いの本についての対談が始まった。

前日僕は、とあるエッセイの内容について、少々、知人と揉めていた。先方が怒っているポイントは、「エッセイに書かれたやり取りは、たしかにあったかもしれないが、そんな言い方はしていない!」というものだった。こちらとしては私怨も込めつつ、あったことよりも大袈裟に書いてしまったのは事実だ。
特定されないように匿名にして書いたんだからいいじゃないか! という気持ちも正直あったが、「読む人が読めばわかる!」と言われたら、すみません! と謝るしかない。
そこからメールで返信するのもさらに揉めそうなので、電話で謝罪し、「でも、あのときのあの態度は許せなかった」と一言伝えた。話はそれで丸く収まった、と言いたいところだが、先方はなにも言わずにそのまま電話を切った。
こういう仕事をしていると、そんなことがたまに起きる。その「たまに」が、阿川さんとの対談前日だった。ただでさえ、ヘビー級の仕事だというのに、前日にそんないざこざは勘弁してくれと思いつつ、その対談に臨んでいた。

開口一番、阿川さんは微笑みながら、僕のエッセイを誉めてくれる。前日の「あーだこーだ」のことを一瞬忘れるくらい、僕はそれだけ浮かれてしまった。
途中、食をテーマにしたエッセイの本を、お互いが出していることもあり、「酒の肴と白ごはんは相性いいのよ」だとか、「最後の晩餐はなにが食べたい?」などとキャッキャと盛り上がり、対談は穏やかに進行していく。
そして対談の最後に、阿川さんが、父親で作家の阿川弘之さんとの思い出を語ってくれた。それは、阿川さんが人生で初めて、出版社から執筆依頼が来たときの話から始まった。
依頼の内容は、「父、阿川弘之さんについて」。阿川さんは、原稿用紙十枚にわたって、自分の父親に対する悪口を、嘘を交えて派手に書いてしまったらしい。出来上がった原稿を持って、出版社に向かおうとしたそのとき、「書いた原稿を見せてみろ!」と玄関先で弘之さんに捕まってしまう。
内容からして、これは目の前で原稿用紙をビリビリに破かれるだろう、と覚悟しながら、阿川さんは目を合わせないようにして、弘之さんに原稿を渡す。
すると、「日本語としてここの形容詞の使い方が間違っている!」とか、「〜に、〜に、〜に、と『に』が三回連続つづいている! ニーニーゼミか!」などなど日本語の使い方、文章の書き方についてのチェックが入り、「いま指摘した部分を直したら、出版社に持って行きなさい」と返されたらしい。
「そのとき、内容に関しては、一言も触れなかったのよ」阿川さんは笑いながら、僕にそう言った。その話を聞いて、最初は僕も笑ってしまったが、「プロなのだから、なにを書いても構わない。ただ、日本語だけは正しく使え」という強烈なメッセージが含まれているような気がして、甚く感動してしまった。
対談が終わって、溜池山王の駅まで歩いている途中、前日に揉めた知人から電話がかかってきた。先方の言いたいことも理解できたが、自分としての態度も、もう一度しっかり伝えた。わかってもらえたかわからない。でも伝えられてよかったと思っている。阿川さんとの対談は、間違いなくヘビー級の仕事だった。こういう仕事をしていると、そんな有り難いことがたまに起こる。

イラスト/嘉江(X:@mugoisiuchi) デザイン/熊谷菜生