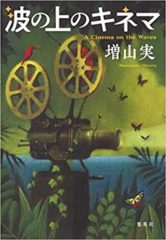境界線を見つめる4冊
「君のいない町が白く染まる」「宝島」「波の上のキネマ」「凍てつく太陽」
さて、ハードな二冊が続いてしまった。お次は小説に行こう。「君のいない町が白く染まる」(安倍雄太郎・著/小学館キャラブン!・刊)である。主人公がひょんなことから幽霊の女の子・アカネと出会うことから始まる恋愛小説だ。漫画などではままある設定だろう。しかし、登場人物たちの感情を切り分ける力と確かなプロット力によって独自性を切り開くという新人離れした手腕をいかんなく見せつけてくれる(言い忘れたが、著者は本書がデビュー作)。実に今後が楽しみな作家が誕生したといえるだろう。なお、著者の安倍さんは二作目の小説「僕の耳に響く君の小説」(同じく小学館キャラブン!)を上梓している。こちらもチェックだ。
どんどん行こう。ここのところ、小説の世界では“境界線”を扱う小説が目立ち始めている。それが証拠に、わたしが読んだ範囲でも、優れた“境界線”小説がいくつもある。「宝島」(真藤順丈・著/講談社・刊)、「波の上のキネマ」(増山実・著/集英社・刊)、「凍てつく太陽」(葉真中顕・著/幻冬舎・刊)などがそうである。「宝島」「波の上のキネマ」は沖縄の近現代を、「凍てつく太陽」は北海道の近現代を舞台にした“境界線”小説である。日本史上において、沖縄と北海道は国境という名の境界線近くに位置するがゆえに各国の思惑や帝国主義に蹂躙されてきた。ここで紹介する三冊の本は、そういった“境界線”に舞台を置きながら、三者三様に想像の翼を広げ、全く違うテーマ――「宝島」は沖縄の人々の魂を、「波の上のキネマ」は物語の意義を、そして「凍てつく太陽」はエンターテイメントを、読者に突きつけてくる。この三つの本を読み比べ、作家ごとの問題意識やテーマの違いに思いを致すのも面白いだろう。