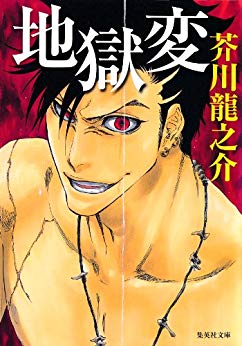毎日Twitterで読んだ本の短評をあげ続け、読書量は年間1000冊を超える、新進の歴史作家・谷津矢車さん。今回は、新元号「令和」の発表により、出典の「万葉集」に注目が集まっている今、「つい古典を読みたくなる」5冊を紹介してもらいます。
GWの10連休、「古典の名作」の世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょう?
新元号が令和に決まり、初めて日本の古典(「万葉集」)から引用されたことが話題を呼んでいる。この原稿を書いているのは発表から一週間が過ぎたあたりなのだが、各社『万葉集』の売り上げが好調というニュースが流れている。実に結構なことだと思う。古典は共有財産である。我々は古典の知識があるからこそ「春は曙」という言葉に趣を覚えるわけであるし、漫画「ドリフターズ」に出てくる那須与一が神がかり的な弓の腕を見せつけたとて、何の違和感もなく受け入れることができるのである(すまん、那須与一云々はややマニアックな話題かもしれない)。
とまあ、世が古典に価値を見出してくれているこの状況は非常にありがたい。古典の恩恵に浴して仕事をしている歴史小説家からしても、この世の動向は大変美味しいのである。というわけで、今回の選書のテーマは「古典をモチーフにした名作」である。しばしおつきあい願いたい。
『平家物語』に描かれなかったその後を描く
まずご紹介するのは『龍華記』(澤田瞳子・著/KADOKAWA・刊)である。
江戸期の絵師・伊藤若冲を主人公にした『若冲』(文藝春秋・刊)、疫病溢れる古都を描いた『火定』(PHP研究所・刊)の他、古代史を材に取った諸作で知られる著者の平安時代小説で、本書は『平家物語』でのハイライトの一つである南都焼き討ち(平家による東大寺・興福寺などへの焼き討ち)をモチーフにしている。本書が面白いのは、『平家物語』という古典作品が描いていないところにこそ真骨頂があることである。『平家物語』が緊迫感をもって描き出した南都焼き討ちそのものではなく、荒廃した南都の姿、そしてそこから立ち上がれずにいる人々、そして立ち上がろうと力を尽くす人々にこそフォーカスが向いている。
もちろん、単体で読んでも大変に感興深い作品であるが、元ネタの一つである『平家物語』と合わせ読みすることで、より著者の描き出そうとしたものの正体に迫ることができるだろう。
『宇治拾遺物語』と芥川龍之介の凄味と
平安期の説話を材に取り自家薬籠中の物とした作家といえば、芥川龍之介である。彼の平安もの諸作が“王朝もの”と呼ばれているのは読書家の間ではあまりに有名であるが、この選書で紹介しないのもおさまりが悪い。と、さんざん言い訳をした上で、一作だけ紹介しようと思う。
わたしが紹介するのは『地獄変』(芥川龍之介・著/集英社文庫・刊)である。
『宇治拾遺物語』の中に、『絵仏師良秀』という非常に短い説話がある。
火事に遭った際、家族を助けようともせず己の家が焼けるのを眺め笑っている良秀を、見舞いに来た人が咎める。だが良秀は、実物の炎を見上げているうちに己の描く炎が下手であったことを悟り、本当の炎とはこのように燃えるものなのだと悟ったとうそぶいた、というややアンモラルなお話である。
この説話を読んでから『地獄変』に当たると、芥川龍之介という作家の凄みをご理解いただけると思う。登場人物の配置を徹底的にいじり、より良秀の狂気と孤独を浮き彫りにしている。絵師もの小説としては『地獄変』は古典となっているのである(絵師もの小説作家であるわたしも影響を受けまくっている)。
なお、本作は各社から刊行されているが、あえて集英社版を推したのは、現代の絵師、久保帯人氏のイラストレーションの天衣無縫さを買ってのことである。
『論語』から読み解くザンネンな孔子の姿
次にご紹介する本は少し角度を変えよう。
『論語』という古典がある。読んだことない人も多いだろうが、名前くらいは聞いたことがあるだろう。儒教の祖、孔子の主著である。東アジア圏に影響を与えた、いや、与え続けているという意味では世界史にも特筆されるべき大古典である。
しかし我々は、孔子の何を知っているというのだろう。なんとなく偉い人、くらいの認識でいるのではないだろうか。
そんな我々の胡乱な孔子理解を嘲笑うかのような本がこちら、『エラい人にはウソがある 論語好きの孔子知らず』(パオロ・マッツァリーノ・著/さくら舎・刊)である。本書は『論語』をテキストに、実は孔子は愛すべき理屈っぽいおじさんだったのではないかと主張する。確かに孔子の年譜を見返すと、どうも今一つぱっとしない人生を送っているし、逸話の中にも孔子が言い逃れをしているのではないかと見受けられる箇所がないではない。著者は『論語』に記載されている孔子を巡るエピソードから、弟子により神格化される前の、愛すべき孔子像を描き出す。
もちろん、本書で描かれる孔子像に違和感や反発を抱かれる向きもあるだろう。そうした方こそぜひ『論語』に手を伸ばしていただきたい。恐らく本書の著者パオロ氏もそれを望んでおられるのであろうことだし。
江戸の怪談「累ヶ淵」と演劇の融合
次は漫画から。
『累(全14巻)』(松浦だるま・著/講談社・刊)である。
キスをすることで他人と顔を交換することができる口紅を得た醜い容姿の少女・累が、持ち前の才能を開花させて舞台女優として活躍してゆく姿を描くダークな演劇漫画である。役者としての才能があるにも関わらず他者から蔑まれるほどに醜い容姿をしている累が、とてつもない執念と黒い情動、そしてほんの少しの他者への期待に突き動かされて舞台の上に向かってゆく姿が痛々しく、そして美しい。累の彷徨の先に何があるのか――。時折本を閉じて休憩しながら、累、そして累に関わった人々の運命の糸のもつれを楽しむ作品である。
さて、今回この漫画をこちらで紹介するのは、本書で多数紹介される演劇の数々のおかげでもある。本書の劇中で紹介される舞台作品の多くは実在し、その舞台作品を演劇人である累がどう解釈し演じるのか。そこにも見せ場があるのである。
だが、それ以上に、本作はある古典作品を敷衍した作品でもあるからだ。江戸期に盛んに語られた怪談に「累ヶ淵」というものがある。さまざまなバリエーションを生んだこの怪談はやがて幕末明治期の噺家三遊亭圓朝によって「真景累ヶ淵」に結実し、定番怪談として定着するに至っている。本書をお読みになった後、もし気になった方は「累ヶ淵」もの(累ものともいう)に手を伸ばしてみてはいかがだろうか。
芥川賞作家による新訳と解説で『新約聖書』から19世紀欧州世界を体感する
最後は戯曲からのご紹介。『サロメ』(オスカー・ワイルド・著、平野啓一郎・訳/光文社古典新訳文庫・刊)である。
実は先にご紹介した『累』にも登場する有名な舞台作品である。
古代イスラエル王の娘が洗礼者ヨハネの首を義父の王に求めたという『新約聖書』に記載のある逸話を材に取り描かれたこの戯曲作品は現代でも愛され、たびたび上演されている。
本書が大変優れているのは、小説家である訳者の“解釈”にも求めることができるだろう。原典にあるわずかな描写から、サロメの人物像を構築し直したその着眼点にはとにかく脱帽である。
それだけではない。本書の魅力は訳文だけではなく、解説にもある。
『新約聖書』の登場人物であるサロメ(正確には、『新約聖書』には名前は出てこないそうだ)が、いかにキリスト教世界で受容されてきたか、そしてオスカー・ワイルドの時代にはどのように理解され、ワイルドがどのように「サロメ」を改変したのかも見渡せるようになっている。この本一冊だけで、「サロメ」ものの大まかな歴史、言い換えるなら古典の織りなす重層性を理解することもできよう。原典に当たる際にも役に立つ一作である。
さて、ここまで古典と現代を行き来する本を紹介してきたわけだが、最後にお知らせである。
実をいうとわたしも古典を材に取った小説を書いたばかりである。江戸期の講談や巷説の中で語られてきた事件をモチーフにした短編集「奇説無惨絵条々」(文藝春秋)が好評発売中である。もちろん、上記五冊がおすすめであることは論を俟たないが、もしもご興味がおありの向きは拙作も手に取っていただけると本当に嬉しい。
【プロフィール】
谷津矢車(やつ・やぐるま)
1986年東京都生まれ。2012年「蒲生の記」で歴史群像大賞優秀賞受賞。2013年『洛中洛外画狂伝狩野永徳』でデビュー。2018年『おもちゃ絵芳藤』にて歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞。最新作「奇説 無残絵条々」(文藝春秋)が絶賛発売中。