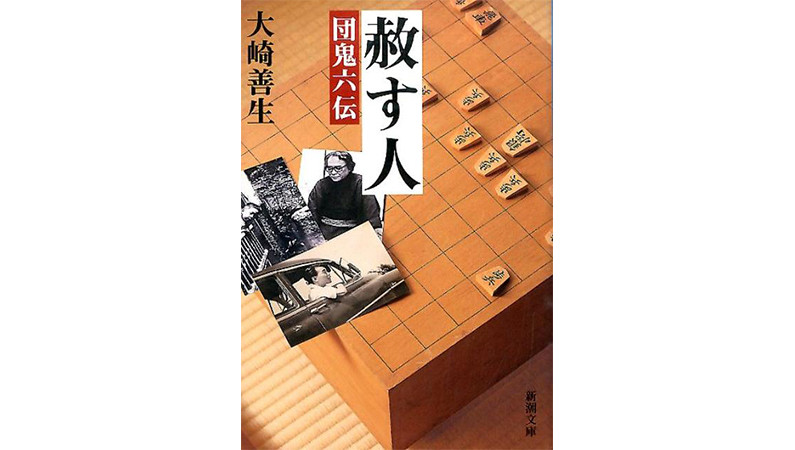『赦す人』(大崎善生・著/新潮社・刊)は、官能小説の大家として一時代を築いた団鬼六の伝記です。
著者の大崎善生は、『聖の青春』や『将棋の子』さらには『パイロットフィッシュ』などの著作で知られています。私は大崎善生の小説が好きで出版されるとすぐに読んでいたのですが、この『赦す人』はうかつにも見逃していました。

団鬼六と大崎善生の接点
まずは、団鬼六と大崎善生のコンビが意外だと感じました。団鬼六は、官能小説の書き手であり、とくにSMもので広く知られています。代表作とされる『花と蛇』は映画にもなりましたので、ご存じの方も多いでしょう。一方、大崎善生は、切ない恋を描いた作品で知られており、作風が違います。
けれども、実は二人をしっかりとつなぐものがありました。「将棋」です。
団鬼六は、将棋のアマ六段の腕前を持つ強豪です。趣味が高じて、「将棋ジャーナル」という雑誌の発行を引き受けたといいます。結果的には赤字経営が続き、鬼六を苦しめることになるのですが、彼は一心不乱に雑誌に打ち込みます。資金不足で、アルバイトを雇うこともできないため、自ら袋詰めの作業までしたのですが、結局、多額の負債を抱えたまま、倒産してしまいます。
大崎善生は、元々は雑誌の編集者であり、「将棋世界」の編集長もつとめた人です。作家としてのデビュー作となった『聖の青春』も、天才棋士でありながら、若くして病気のため亡くなった棋士・村山聖の人生を描いたものです。
二人の出会い
二人が出会ったのは、1994年「将棋ジャーナル」が廃刊した年のことだといいます。その時、団鬼六は借金返済のため、金目のものをほとんど売り払い、家も競売の手続きに入っている状態でした。
一方、大崎善生は、「将棋ジャーナル」のライバル誌「将棋雑誌」の編集長をつとめ、雑誌の売れ行きも好調でした。作家としてデビューする6年ほど前のことになります。
そんな二人が、将棋会館の近くの鰻屋に連れ立って出かけることになりました。ただ一緒にお昼ご飯を食べるはずだったのですが、以来、団鬼六が亡くなるまで続く親しい関係が始まる「運命のランチ」になったのです。その時のことを大崎はこう書いています。
将棋雑誌編集者と将棋雑誌発行人を辞めたばかりの老作家は二人で飲みだしてしまった。ビールの栓を開けた瞬間、私はずーっといつかは本誌に書いてもらいたいと思い続けていた団鬼六という作家の栓を開けたような気がした
(『赦す人』より抜粋)
二人は会うべくして会ったのでしょう。そして、その日が『赦す人』という作品が生まれるきっかけともなりました。団鬼六は以来、大崎善生に心を許し、自分の一生を語り尽くし、書くようにと頼んで亡くなったのです。
波瀾万丈ではすまない一生
『赦す人』に綴られた団鬼六の一生には驚かされます。波瀾万丈という言葉でさえ物足りないほどです。
すごい人生を送った方だと知ってはいたつもりですが、これほどまでに、すさまじいとは……。想像していませんでした。インタビューと飲み会をくり返し、団鬼六に迫った大崎善生でさえ、時に呆然とし、立ち尽くしてしまった様子が、文章にも表れています。
団鬼六は1931年に滋賀県彦根市で生まれ、大阪で育ちました。
戦争ごっこやチャンバラが好きな少年でしたが、何よりも映画が大好きで、ジャンルを問わず、片っ端から観たといいます。洋画も邦画も、とにかく何でも好きだったのですが、そのころ、鬼六は奇妙なことに気づきます。『丹下左膳』や『鞍馬天狗』に夢中になりながらも、お姫様や奥方が悪者に縛られるシーンになると、性的な興奮を覚える自分に気づいたのです。
父と息子
団鬼六の父である信行の教育方針にも、驚かないではいられません。
人生は甘くないではなく、甘いものと考えろ――からはじまる。次に人生はすべて勝負事という信念。高級住宅街を散歩していて、その中のひと際大きな家を見かけると、信行は鬼六に懇々と諭す。あんな家はサラリーマンになっていくら真面目に働こうが買えるわけがない。あれを手に入れるには相場しかない。相場で勝ち上がればあっという間や
(『赦す人』より抜粋)
とくに勝負事が好きではなかったはずなのに、鬼六は相場に身を投じる大人になります。
団鬼六の複雑さ
『赦す人』によって、私は団鬼六という作家の二面性を教えられました。
キリスト教系の学校に通いながら、心の中にはSMに惹かれる鬼六。相場で大損する父親に手を焼きながら、自分もアルバイトのお金を相場につぎ込んでしまう鬼六。新橋でバーを経営したものの失敗し、教員をしていた恋人の三枝子のおかげで、三浦市の代用教員になる鬼六。
昼は教壇に立ちながら、SM小説を書き続ける鬼六。恋人の三枝子と結婚し、子どもを可愛がる生活をしながらも、「愛人は車のスペアタイヤのようなものだ」と豪語し、次々と愛人を持つ鬼六。
そして、何より、妻が浮気したと知り、激怒しつつも、結局は妻を赦す鬼六。これらすべてが、鬼六の人生をつくりあげているのです。まったくもって、簡単には理解しえない人物であることをかみしめながら、読まないではいられません。
鬼六の死
ジェットコースターのように浮き沈みの多い人生を送った団鬼六ですが、そんな彼にも最期のときが来ました。それまでも、脳梗塞に苦しみ、骨折もし、透析治療をしながら暮らすようになっていました。晩年には、食道癌を発症し肺にも転移、余命が少ないことを認めざるを得なくなります。
けれども、団鬼六は最期まで団鬼六でした。「まだ遊び足らない」と、大崎善生に訴えたといいます。死をおそれ、ゾッとすると嘆きながらも、鬼六は「死は観光だ」と思うようになります。
そのたどり着いたひとつの結論が、観光という鮮やかな言葉なのだ。知らない場所を見て歩く。まるで死すらも遊びの中に組み入れて表現してしまおうというのだ。この生を遊び尽くした鬼六は、それでは飽き足らず死後もただ遊び続けようとしているのか
(『赦す人』より抜粋)
まったくもって、複雑で、絶望的に暗く、同時にどこか明るい結論だと思いませんか?『赦す人』という一冊の本から、あふれ出てしまいそうな鬼六の人生。もう一度、その生から死までをたどりつつ、読み直したいと思います。
【書籍紹介】

赦す人
著者:大崎善生
発行:新潮社
昭和6年。文士と親しく交流する女優の母と相場師の父との間に鬼六は生れた。純文学を志すが挫折、酒場経営で夜逃げ、一転中学教師を経て、SM作家として莫大な稼ぎを得る。しかし、映画製作や雑誌の発行に乗り出し破産。周囲は怪しげな輩が取巻いていた…。栄光と転落を繰返す人生は、無限の優しさと赦しに貫かれ、晩年に罹患した病にさえも泰然としていた。波瀾万丈の一代記。