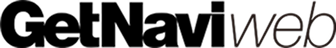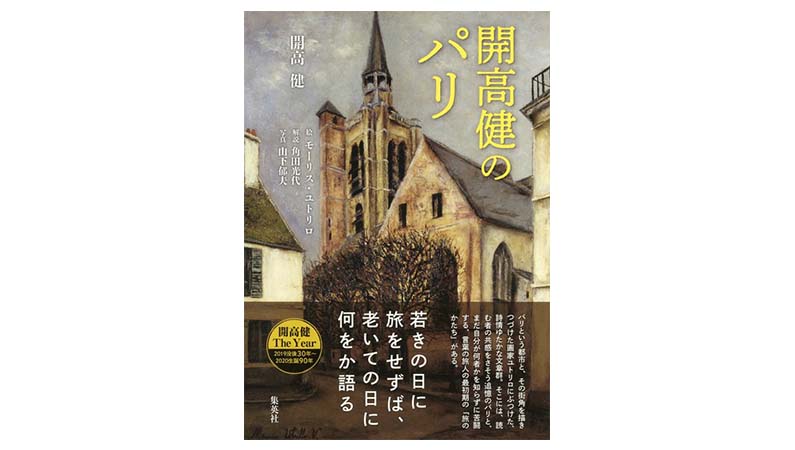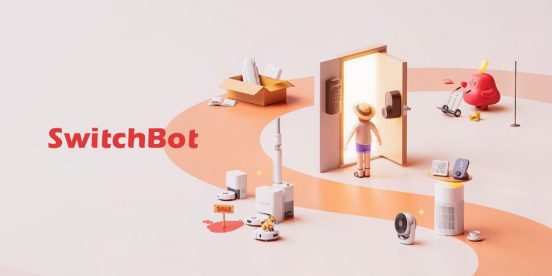最近、荻原朔太郎の「旅上」という詩をしきりと思いだす。
ふらんすへ行きたしと思へども
ふらんすはあまりに遠し
せめては新しき背廣をきて
きままなる旅にいでてみん。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、海外旅行に行くことができないからだろうか。いや、それだけが理由ではない。私にとって、フランス、とくにパリは、憧れてはいるものの、そうは簡単には行くことができない街だ。せめてもの慰めに、『開高健のパリ』(開高 健・著/集英社・刊)を読んだ。

開高 健という作家
開高 健は1930年に大阪の天王寺で生まれた。1989年、食道癌の手術後、食道腫瘍に肺炎を併発して亡くなった。まだ58歳だった。
長いとは言えない生涯だが、彼は苦しみながら書き続けた。ジャンルは問わず小説、随筆、ノンフィクションなど、様々な分野で優れた作品を残している。個性的な生き方に憧れる人も多かっただろう。私は『夏の闇』が好きで、夢中になって読んだ。開高ファンの多くが、こうした「自分だけの1冊」を持っているのではないだろうか。
今年は、開高 健の生誕90年にあたる。90歳になった彼を想像するのは難しいが、開高 健は過去の人ではない。今年、ある新聞社が行った「読めば家でも旅気分」というランキングで、開高 健の「オーパ!」は、堂々の1位を獲得している。彼は今もなお、人々の記憶に残る作家だ。
パリとユトリロと開高 健
『開高健のパリ』は不思議な本だ。そもそも、どのジャンルに属するのかよくわからない。作家・開高 健が、画家・ユトリロ、そして、パリについて書いた作品で、随筆のようでもあり、画集のようでもあり、旅行記だと言われれば、そうだなと感じる。
どのページにも、パリやユトリロ、そして開高自身について、愛憎あふれる文章がみっちりと埋めこまれるように書かれている。角田光代の解説や山下邦夫の写真も興味深く、多くの人が加わって製作したコラボレーションならではの魅力が光る1冊だ。
開高 健は、パリの街角を描き続けたユトリロに対して、ラブレターを書くように思いを吐露し、本音も遠慮なく伝える。その一方で、自分の焦燥感をぶちまけ、激しい言葉をぶつけてもいる。その意味で、開高 健はユトリロに向かって、時を越えて叫んでいるかのようだ。
忘れてはならないのは、パリがそれに加わっていることだ。もしパリという街がなかったら、ユトリロも『開高健のパリ』も成り立たない。開高 健、ユトリロ、そして、パリという3つが、それぞれに自らを主張している。同時に3つの存在は徹底的に孤立し、ばらばらでもある。それが『開高健のパリ』の不思議さであり、醍醐味であり、混沌さを感じさせる理由だ。
パリを描くように書く
開高 健は、パリに何度も出向いては滞在している。彼にとって、パリとは何だったのだろう。「ふらんすに行きたしと思へども、ふらんすはあまりに遠し」というまなざしを向ける街だったのだろうか。
『開高健のパリ』で、彼はパリをユトリロというひとりの画家を通して書こうとする。それはまるで、作家が画家となって、表現したかのようだ。もしかしたら、彼はパリを「書く」のではなく、「描き」たかったのかもしれない。万年筆を絵筆に持ち替えて……。開高はユトリロに対しての思いをこう綴っている。
彼の画に向かうと私たちは埃りまみれになって古びてすれっからしになった自分たちの内部のある領域が、みずみずしくよみがえって樹液の活動のような新鮮さをみなぎらせてくれることを感ずるのである。
(『開高健のパリ』より抜粋)
パリの一日
開高 健のパリでの1日は、以下のようなものだ。朝は、宿屋を這い出してキャフェへ行く。そして「三日月パン」と「牛乳入りコーヒー」を飲み、新聞を眺めたりして店を出る。午後の3時になると、ビールと「ハムを棒パンにはさんだの」をおなかにおさめ、楽しい夕方に備える。
夕方になるのを待ちかねて、アペリチフにカシスかベルモット。秋の新酒の季節ともなれば、ボージョレかモンバジャックの赤を楽しむ。夕食には、ムール貝かカタツムリを味わいながら、ワインは白かロゼ。その後、映画や芝居を観て、11時ごろに名物玉ネギスープをどんぶり鉢ですすり「夜食」とする。そして、飲む。さらに飲む。いい気持ちでたまらないと微笑みつつ飲む、続けて飲むをくり返す。
あぁ、こんなパリを過ごしてみたい。誰もがそう思うのではないかだろうか。しかし、やがて気づくだろう。開高 健は苦しんでいたのだと。苦しくてたまらないから、日本を脱出し、ワイングラスを風船玉と呼び、そこにワインを注ぎ、何度も風船玉を傾ける。それでもやはり、やはり彼は苦しかったのだろう。
『開高健のパリ』には、うなるようなパリの描写がある。
パリ市の俯瞰図を見ると、複雑な血管の網のあちらこちらに大小さまざまな瘤ができたみたいである。
どれでもよいから1本の道をとって、たんねんにたどってゆくと、そのうちにきっとどこかで、この”丸い点”に入る。昼でもたそがれたように薄暗い、しめってくたびれた壁のなかを歩いていると、とつぜん石の腸の中から広場へ踏み込むことになるのである。(『開高健のパリ』より抜粋)
こうして文章を写しているだけで、私は「そうよ、そうよ。パリってこうよ」などと頷きたくなる。ほんの数回行っただけだというのに。
パリのもうひとつの顔
パリは素敵なだけの街ではない。美味しくオシャレなだけでもない。ちょっとしたことで、抱え込んだ鬱屈、人種的混沌、激しい自己主張が、噴出する場所でもある。そんなとき、パリはいきなり姿を変える。
その複雑な暗さが、パリをパリたらしめているのだろう。
開高 健はパリの無残さも目の当たりにしている。あるとき、バスチーユ広場で行われた反右翼抗議集会に遭遇した。警察が広場の入り口を封鎖し、地下鉄も閉鎖、お店もシャッターを降ろして危険を回避しようとする。当然のことながら、デモ隊は行き場を失い、挙げ句の果てに、殴られたり蹴られたりとサンドバッグ状態となる。悲鳴、流血、そして逃亡……。これもパリのもうひとつの顔だ。
たとえ正視したくなくても、見なくてはならない問題を彼は書く。それを生フォアグラの見事さを書くのと同じ筆致で書いていく。それでいながら、不思議なほど違和感はない。それが開高 健の筆力によるのか、パリという街の混沌のためか、それともユトリロの画の効果かはよくわからない。わからないままに、パリについて強い印象を持つ、それが『開高健のパリ』だ。
出来ることなら、開高 健の口から直接、2020年のパリについて聞いてみたい。今のパリをどう思うか知りたい、知りたくてたまらない。しかし、それはかなわぬ夢である。今はただ、「ゆっくりとパリの夢をみてくださいね」と言うべきだろう。
【書籍紹介】
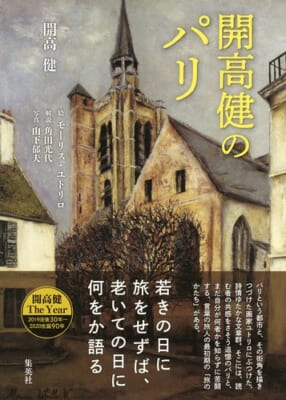
開高健のパリ
著者:開高 健
発行:集英社
パリという都市と、その街角を描きつづけた画家ユトリロにぶつけた、詩情ゆたかな文章群。そこには、読む者の共感をさそう追憶のパリと、まだ自分が何者かを知らずに苦闘する、言葉の旅人の最初期の「旅のかたち」がある。