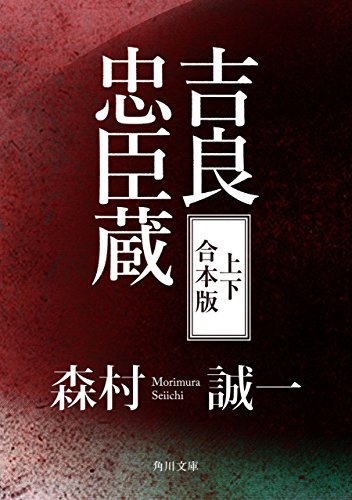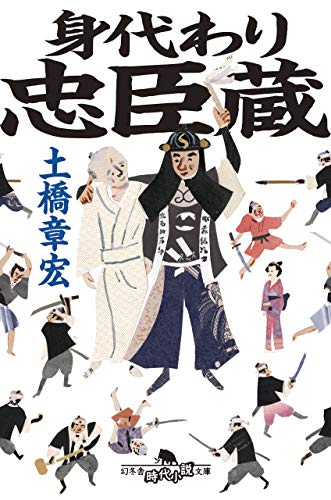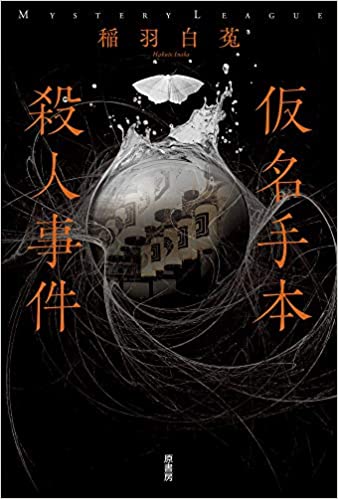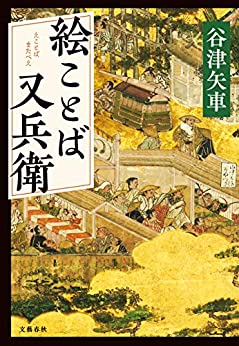毎日Twitterで読んだ本の短評をあげ続け、読書量は年間1000冊を超える、新進の歴史小説家・谷津矢車さん。今回のテーマは「忠臣蔵」。かつての冬の代名詞であり、今でも12月14日の討ち入りの日には四十七士の墓がある泉岳寺には多くの人が訪れます。そんな「忠臣蔵」谷津さんはどんな5冊を選ぶのか?
【過去の記事はコチラ】
「ここのところ、忠臣蔵が忘れ去られつつある」
歴史、時代小説家が集まると口の端に上るのが、この話題である。歴史小説は、二次創作物的な側面もある。商業で歴史小説を書く際にはネタの面白さやテーマ性なども勘案されるが、扱う事件や人物の知名度がものをいう。それがため、信長、秀吉、家康の三英傑に近い人物を描いた歴史小説が書店さんに溢れているわけである。
昔、忠臣蔵は戦国三英傑、新撰組などと並ぶ、歴史創作のドル箱ジャンルだった。それどころか、かつての日本では、クリスマスと並ぶ師走の風物詩だったのである。ところが今はどうだろう。数年に一回、映画が封切られたり地上波でドラマが放送されるのがせいぜいといったところだ。もちろん、マスメディアの動向だけで文化を論じるべきではないが、マスメディアは今日においても国民的な知名度を形作っている。
その結果、「吉良上野介って誰ですか?」という三十代の声に際してしまい、「ああ、これじゃ企画が通らないや」と歴史小説家が肩を落とすことになるのである。だが、あえて言いたい。
忠臣蔵は面白い。
江戸城松之廊下(本当に松之廊下が現場だったかは議論の余地があるようだが)で白昼起こった浅野内匠頭による刃傷事件。喧嘩両成敗が武士の祖法にもかかわらず、もう一方の吉良上野介にはなんのお咎めもなかった。これを不服とした浅野家家臣による吉良邸討ち入り。冷静に見ればとんでもない話であるが、江戸時代、近現代に至るまで、日本の人々にある種のエモさを与えてきたことは否定できない。
というわけで、今回は復権を祈っての「忠臣蔵」選書である。
昭和の国民作家の「忠臣蔵」
まずご紹介するのは『新編忠臣蔵(一・二)』 (吉川英治・著/KADOKAWA・刊) である。言わずとしれた昭和の国民作家による忠臣蔵作品である。さて、皆さんは吉川英治にどういう印象をお持ちだろうか。戦前から戦後にかけて活躍した作家ということもあって、読みづらいんじゃないかとお思いの方もいらっしゃるのでは? しかし安心してほしい。吉川英治作品は時々難しい言葉が出てくるが、少し読むうちに慣れてくる。それどころか、独特の躍動感、リズム感が文体に存在し、結局はするすると読むことができるはずである。
そして、最初に紹介する作品でありながら、本作、かなり『仮名手本忠臣蔵』の印象を躱している作品である。一般的なイメージでは意地悪な老人として描かれる吉良上野介の名君としての面を取り上げたり、ただの復仇譚ではない陰影を、様々な視点から複眼的に浮かび上がらせていることに特徴がある。
また、この作品は戦中期に描かれた作品であるため、皇室の描き方にも特徴がある。どう特徴があるのかと言えば……ここは皆さんの楽しみのために取っておこう。
吉良視点で描かれた「忠臣蔵」
次にご紹介するのは、『吉良忠臣蔵』 (森村誠一・著/KADOKAWA・刊) である。
忠臣蔵ものは大抵、討ち入り側、すなわち浅野家臣団から描かれることが多い。その方が知られたエピソードも多いからである。だが本作は従来の図式である浅野方――善玉、吉良方――悪玉の図式を逆転させたところに新しさがある。その結果何が起こったか。浅野方、吉良方、さらにはある第三勢力による三つ巴の謀略戦が始まるのである! そしてその結果、従来の忠臣蔵作品においてはちょい役、斬られ役にすぎなかった人物たちが躍動感を持って動き始め、それぞれのドラマが展開し始める。群像の人となりや立場、人としての懊悩が鮮やかに描かれてゆき、破局(討ち入り)に向かって収束していく様には舌を巻くよりほかない。
忠臣蔵のストーリーと第一級のエンターテイメントが両立した、とんでもない作品である。
お金から見た「忠臣蔵」
お次に紹介するのは、『「忠臣蔵」の決算書』 (山本博文・著/新潮社・刊)である。2019年封切り映画『決算! 忠臣蔵』の原作といえばピンとくる方も多いかもしれない。
本書は忠臣蔵(正確には忠臣蔵の元ネタとなったいわゆる赤穂事件)に迫った歴史系一般書籍であるが、その観点が面白い。史料『預置候金銀請払帳』という、浅野方の頭領だった大石内蔵助の会計報告書がある。これを縦横に用い、討ち入り方の苦闘を浮かび上がらせている。
わたしたち現代人は、浅野内匠頭切腹から二年弱で吉良邸討ち入りが行なわれたことを知っている(あるいはご存じなくとも調べることができる)。そのためにその歴史的な行動が必然のことのように思われるが、討ち入りに至った人々はそれぞれに人生があり、それぞれ飯を食ってどこかに泊まり、銭を払っていた――つまりは生活を営んでいたのである。本書は芝居の登場人物のようにさえ思える四十七士を、経済というアングルを導入することにより、実在の人間としての横顔を浮かび上がらせることに成功したといえるのである。
吉良は影武者だった!? 奇想で描く「忠臣蔵」
続いてはこちら。『身代わり忠臣蔵』(土橋章宏・著/幻冬舎・刊)。『超高速! 参勤交代』などのユーモア時代小説で知られる作家の忠臣蔵ものであるからして、当然ただの忠臣蔵ではない。本書を他の忠臣蔵ものと差別化しているものは、「吉良上野介は松之廊下事件で死に、それからの上野介は別人の影武者だった」という奇想である。また、この影武者もいい。影武者を吉良上野介の弟にして放蕩者であった破戒僧・孝証(ちなみにこの人物の来歴はほぼ知られていないが、実在の人物である)としたことで、お話に膨らみが生まれ、出会うはずのない人物との出逢いや、起こるはずのない出来事が出来する。
本作の面白さは、従来の忠臣蔵からたった一人、重要人物をすげ替えたことにより発生する意外性にこそある。忠臣蔵のストーリーなのに、まるでわたしたちの知らないストーリーが用意されている。その大胆な換骨奪胎に、ぜひ驚いて頂きたい。
『仮名手本忠臣蔵』をモチーフにした本格ミステリー
最後はこちら。『仮名手本殺人事件』 (稲羽白菟・著/ 原書房・刊)である。本書は、史実の赤穂事件ではなく、芝居である『仮名手本忠臣蔵』をモチーフにしたミステリー小説である。
時は現代、衆人環視の中、血を吐いて倒れた人間国宝の歌舞伎役者の死を受け、劇評家の海神惣右介、冨澤弦二郎の二人が独自に捜査を始めるところから話が始まる。本作のミステリー的な工夫は、謎の提示と解決の鮮やかさである。一つの謎が解決したかと思ったらさらに謎が深まっていき……という具合に、読者をどんどん深みに引きずり込んでいく。それだけに、解決編の満足度も高い。
そうしたミステリーとしての面白さとは別に、本書は『仮名手本忠臣蔵』、そして赤穂事件のガイドブックとしても楽しめる。どうしても歌舞伎の演目というと二の足を踏まれる向きもあろうかと思うが、本作ではそうした読者がいることも想定し、作中、無理なく『仮名手本忠臣蔵』と事件としての赤穂事件の違いについても丁寧に語られている。そして、物語の『仮名手本忠臣蔵』と史実の赤穂事件、この虚実のあわいが本作の肝なのだが……。ネタバレはここまでにしよう。
忠臣蔵が忘れ去られようとしているのに対し、それでもいいじゃないか、というご意見もある。封建的な内容が現代にそぐわない、とのことだが、わたしはそのご意見には与しない。
忠臣蔵は、理不尽に際した人々の物語である。理不尽を前に意志を通したり、通せなかったり、逃げ出してしまったり、仲間を裏切ってしまったり、ドンキホーテ的な行動に意気を感じて協力したりする。忠臣蔵に出てくる登場人物たちは、常に理不尽と戦っているのである。
わたしたち人間が理不尽のない世界を実現しない限り、忠臣蔵は古びない。これが、忠臣蔵に対するわたしのざっとした思いなのだが、これをお読みの皆様、いかがなものであろうか。
【過去の記事はコチラ】
【プロフィール】
谷津矢車(やつ・やぐるま)
1986年東京都生まれ。2012年「蒲生の記」で歴史群像大賞優秀賞受賞。2013年『洛中洛外画狂伝狩野永徳』でデビュー。2018年『おもちゃ絵芳藤』にて歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞。最新作は『絵ことば又兵衛』(文藝春秋)