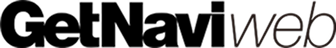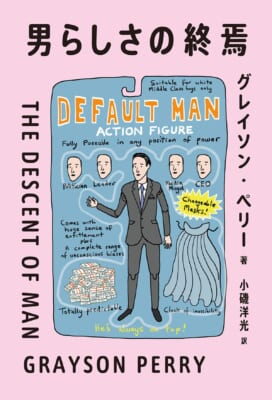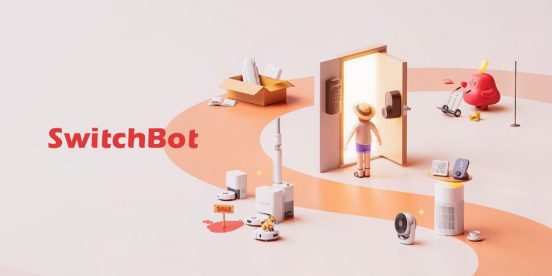毎日Twitterで読んだ本の短評をあげ続け、読書量は年間1000冊を超える、新進の歴史小説家・谷津矢車さん。今回のテーマは「ジェンダー」。谷津さんが選んだ硬軟取り混ぜた5冊で、あなたも、この問題にしっかり向き合ってみませんか。
【過去の記事はコチラ】
ジェンダーバイアスを巡る話題が、止まらない。連日のように報道される有名人によるミソジニー(女性嫌悪)的な言動、インビジブルな男女間格差、そして、この話題を政治・思想の問題と限定して語る人々……。
わたしにも無論、思いや考えはある。とはいえ、わたしは小説家である。小説家であるわたしが何かを発信する時には、テキストで語るのが常。というわけで、今回の選書テーマは「ジェンダー」である。
ただ、今回はテーマがセンシティブなため、一つ、注意を述べておきたい。
わたしの選書は、あくまで「ジェンダーにまつわる何かがモチーフとなっている」本を取り上げている。主題が別のところにある書籍を選んでいる場合があるが、ジェンダーという論点が、身近なものに含まれていることの裏返しであると捉えて頂ければ幸いである。
常に主体的な、新たなエンタメの女性像
まずご紹介するのは漫画から。『呪術廻戦』 (芥見下々・著/集英社・刊) である。本書は言わずと知れた呪術・呪力がモチーフの異能バトル漫画であり、既に社会現象的な人気を博している作品である。今更本書を紹介するのも気が引けるのだが、ジェンダーを巡る本、という視点から眺めると、また違った様相が見えてくる。
本作の女性陣の描かれ方は色々だが、常に主体的であり、トロフィーワイフ的な描かれ方はしていない。一番わかりやすいのは、主人公虎杖悠仁(いたどり ゆうじ)の傍にいる釘崎野薔薇(くぎさき のばら)であろう。この登場人物は決して「男たちの帰りを待つ女」ではない。自らの目的の元に戦場に立ち、体を張って戦っている。そんな野薔薇にはいわゆる「女の子っぽいもの」が好きという設定があるが、それすらも、「自分のために」選び取った志向であることが作中で明言され、様々な行動の動機に連動している。そしてジャンプ読者はその野薔薇のあり様を支持しているのである。
エンタメにおける女性表象の在り方として、現代的な落ち着き処の一つを体現した漫画であると言えよう。
「女性の献身」その美談の裏にあるもの
次は歴史小説作品から。『華岡青洲の妻』(有吉佐和子・著/新潮社・刊)である。『悪女について』『紀ノ川』『連舞』などの傑作小説で知られる作家の代表作である。
華岡青洲をご存じだろうか。江戸時代後期の医者で、西洋に先んじること40年、全身麻酔「通仙散」の開発、これを使用した乳がんの摘出手術に成功した人物である。華岡青洲には、一つの〝美談〟がある。全身麻酔薬「通仙散」の開発中、動物実験までは上手くいったものの、臨床実験を行なうことが難しかった。これを見かねた青洲の妻と実母が自ら実験台になることを申し出て、臨床データを得ることに成功、その上で「通仙散」の開発にこぎつけたというものである。本書はその〝美談〟をモチーフにしているのだが……。
本書で表面的に描かれるのは、女たちの献身、そして、意地の張り合いである。息子・夫のために身を捧げる女の戦いが紙幅の多くを占め、華岡青洲その人の印象はむしろ薄いといってもいい。だが、嫁姑の愛憎の末、作品も終局に至ろうとする場面になって、華岡青洲の存在感がいや増してくる。
詳しくは本書に譲るが、女というジェンダーに縛りつけられた女性たちの思いや、エネルギーを収奪することで成立する江戸社会――あるいは現代社会――の姿を告発しているのではないか、とも読めるのである。
男性もまた、「男らしさ」の檻に囲まれている
さて、次はこちらを。『男らしさの終焉』(グレイソン・ペリー ・著、小磯洋光 ・訳/フィルムアート社・刊)である。
本稿をお読みの男性読者の方は、こう考えてはおられないだろうか。ジェンダー問題っていうけど、結局男には関係ない話題なんじゃないの? ジェンダー問題は女性が割を食って男性が得をするシステムだから、男の自分からすれば得だよ、と。そんな思い込みを粉々に粉砕するのが本書である。
社会が求める女性像が女性を縛りつけるように、社会が求める男性像もまた、男性を苦しめる面があるのである。
男性もまた、「男らしさ」の檻に囲まれている。
男性にとっても、ジェンダーは他人事ではない。
もしかすると、男性のあなたが今、生きづらさを感じているとするなら、それは制度化・形式化された男らしさについて行くために必死だからかもしれないのだ。本書は、今ある枠組みを疑う大切さを教えてくれる本でもあろう。実は、わたしが「男性のジェンダー」について考えるきっかけをくれたのが本書である。感謝を込めてご紹介。
ジェンダーと戦争
次は古典作品を。『戦争は女の顔をしていない』 (スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ ・著、三浦みどり・訳/岩波書店・刊)である。最近漫画化もされている(小梅けいと・作画/KADOKAWA・刊)ので、そちらを手に取っておられる方も多いだろう。
本作は、第二次世界大戦中の東部戦線を巡るルポルタージュ作品である。ナチス・ドイツとソビエトとの戦争である東部戦線において、防御に回ったソビエトは、多くの女性を戦争に動員した。工場勤務や後方支援は元より、前線での狙撃任務や破壊活動に当たった女性たちもあった。そうしたひとびとにフォーカスを当てた作品である。
本書が剔抉(てっけつ)するものはあまりに多岐に亘っており、一口で述べることは難しい。国家総動員戦争の悲惨さであり、大きなものに蹂躙される小さなものたちの記録であり、苦しい局面にあってもなお存在する人間らしいひとときの輝きであり……。読み返す度に発見がある。
だが、本書において強く浮かび上がるモチーフの一つは、やはりジェンダーであろう。現代でこそ払拭が進んでいるとはいえ、軍隊は古今東西、男の園でありつづけた。第二次世界大戦中も、もちろんそうである。そんななかに、女性という異なるジェンダーのグループが入ったらどうなるか――。本書はそんな現場の混乱や困惑、そして戦争遂行という大義と軍内の秩序のために否応なくジェンダーを凍結させられてゆく女性たちを描いているようにも見える。
「普通」からはずれて生きること
最後にご紹介するのはこちら。『水を縫う』(寺地はるな・著/集英社・刊)である。この著者は「普通であること」「人並み」から外れた人々の群像をモチーフにしてきた作家だが、本作もその一冊で、「普通であること」からちょっと外れた一家の、危うくもしなやかな繋がりを描いた連作短編集である。
普通。この二文字ほど危険な言葉はないかもしれない。この言葉の裏には、「正しいとされるロールモデル」が顔をのぞかせる。そしてそれは往々にしてわたしたちの個性とバッティングし、摩擦を起こす。その摩擦熱を駆動力に物語を紡いできたこの著者が、ジェンダーをテーマに取るのは当然の成り行きといえる。
本作主人公格である清澄は裁縫を趣味としており、それゆえに「男らしさ」のジェンダーモデルからはみ出している。その姉の水青は過去の体験から「かわいい」という価値観――「女らしさ」のジェンダーモデルに違和感を抱いている。そんな水青のために清澄がウエディングドレスを縫おうというのだから、軋轢が起こらないはずはない。この姉と弟の衝突に、方向性の違う生きづらさを抱えた家族が関わっていくことで、物語は加速していく。やがて、この物語は、異なる生きづらさを抱えた人々がどうやって共生していくのかを描き出しているのだが、その答えは、ぜひ自らの手で確認していただきたい。
歴史上、ジェンダーは変化してきた。二十一世紀の現代、わたしたちは高度なテクノロジーによって肉体的な性差をある程度埋めることができるようになった。
現代を生きるわたしたちは、数世代に亘って既存のジェンダーを疑い、更新してゆく必要があるのだろう。昨日より今日、今日よりも明日がよい日になることを願いながら。
【過去の記事はコチラ】
【プロフィール】
谷津矢車(やつ・やぐるま)
1986年東京都生まれ。2012年「蒲生の記」で歴史群像大賞優秀賞受賞。2013年『洛中洛外画狂伝狩野永徳』でデビュー。2018年『おもちゃ絵芳藤』にて歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞。最新作は『小説 西海屋騒動』(二見書房)