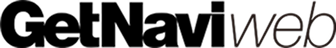「週刊GetNavi」Vol.67-3
スタンドアローンVR機器において、最初の重要なコンテンツはなにか、といわれれば、筆者は「ごろ寝シアター」だ、と答える。VR機器は、視界のすべてを映像で置き換えるものだ。そこに「自分しかいない映画館」を作り、数百インチの大画面で映画を観るのは快適で新鮮な体験だ。特にOculus Goは、頭に機器を固定するためのバンドがゴム製で、寝転がってもゴツゴツとした感触がない。だから、ベッドやソファに寝転がれば、手軽に「天井方向に映画館のスクリーンがある」ような体験ができる。

こうしたパーソナルホームシアターは、1996年に発売されたソニーの「グラストロン」が目指していた方向性であり、2013年にOculus Riftが登場するまで、「頭につけるディスプレイ」全般が目指していた未来そのものである。実際、これまでにもスマホ用VRがある程度人気を博し、「映像を見る」用途で広がったが、こうした市場はアダルトコンテンツが中心。結局のところ、さほど大きなビジネスには成長していない。
スタンドアローンVR機器が拓く「ごろ寝シアター」であれば、あらゆる映像をシアターの中で楽しめる。映像配信サービスの普及により、ネットにさえつながっていれば映像が楽しめるようになったことが、こうした機器の可能性を広げているのだ。そういう意味では、「今の世の中だから可能になった」、スタンドアローンVRならではの使い方と言えるだろう。
とはいえ、ごろ寝シアターだけがスタンドアローンVRの価値ではない。次に大きな価値となるのが「コミュニケーション」だ。Oculus Goには純正アプリとして「Oculus Rooms」というものが用意されている。これは、友人同士がバーチャル空間内に作った部屋に集まり、音声でのコミュニケーションを行う、というものだ。部屋の中では、写真や動画を一緒に見ることもできる。
バーチャル空間でのコミュニケーションは、これまでのビデオ会議よりも「一緒にいる感覚」が高い。バーチャル空間での自分は、簡素化された3Dのキャラクターになる。映像のほうがリアルだろう……と思えるが、実はそうではない。話に合わせて顔が動いて視線があったり、手を動かしたりできると、とたんに「実在感」が高まる。人間の脳が「そこにいる」と感じる際には、映像のリアルさよりも、会話に合わせて身振り・手振りがあるといった、非言語的なコミュニケーションが成立することのほうが重要なのだろう。
気軽にバーチャル空間で会えるようになると、コミュニケーションのあり方は変わる。ビジネス的な視点だけで見ても、「ミーティングの形の変化」は、大きな金銭的価値を持っているはずだ。
バーチャル空間でのコミュニケーション要素を持ったアプリは意外と多く、「一緒に映画を見る」「一緒にライブ中継を見る」といったアプリも登場し始めている。ただ、Oculusが標準でこうしたコミュニケーション系サービスを複数用意した一方、Mirage Soloのプラットフォームを提供するGoogleは、それらを用意していない。OculusのほうがVRビジネスの将来について、明確なビジョンを持っているため、こうした差が生まれているのではないか……と思える。
では、Mirage SoloはOculus Goに対して一方的に劣っているのだろうか? 実際には、そうではない。両者の違いについては、次回のVol.67-4で解説する。
週刊GetNavi、バックナンバーはこちら!