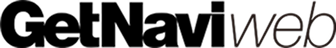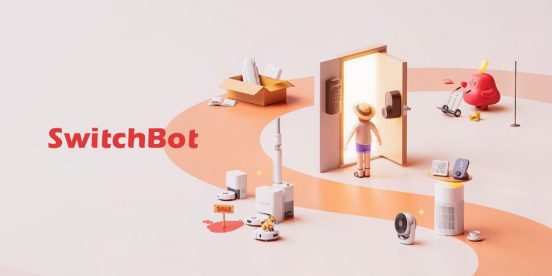『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』のモデルである小林さやかさんが、この9月、コロンビア教育大学院に合格してニューヨークに渡った。本が出版されてからおよそ10年。日本国内での大ヒットは言うまでもなく、中国においては上映初週に興行収入記録を塗り替えた映画公開から7年。小林さやかさんは今何を思い、どこを目指しているのか。詳しくお話を伺う機会を得た。

高い目標を持って努力をすることにはメリットしかない
−−『ビリギャル』が出版されて約10年が経過しました。その間に日本の大学院で学習科学を学んだ小林さんが、教育について興味を持った理由について教えてください。
小林さやかさん(以下、小林) ビリギャルが出版された2013年、私はウェディングプランナーとして働いていました。本の出版で多くの人たちに知ってもらえて、主に子ども向けの講演依頼をいただくようになり、子どもたちのためなら何でもしたいと思っていたので、働きながらあちこちに伺って話をさせていただいていました。
最初のころは自分の何がそんなにすごいのかと思っていました。もちろん頑張ったけど、私は受験しただけです。頑張って慶應大学に入った人は自分だけじゃないという感覚もあったので、何で私が注目されるのかとても不思議でした。
そんな中で衝撃的な体験をしました。「この子はもともと頭がよかったんだろう」という反応が、想像以上に大きかったんです。多くの人にそう思わせるものは何か。学習科学を学ぶために聖心女子大学院に進学した一番の動機は、「ビリギャルはもともと頭がよかった。だから自分には無理」と思い込んでいる人たち、あるいはそう思い込みたい人たちの意識を変えたいと思ったから。学習科学を選んだ理由は、昔の私がなぜできたのかを科学的に証明したいという気持ちがあったからです。
−−ビリギャル時代の小林さんは、日本の学校教育の問題をご自身で体験なさっていたのでしょうか? ポジティブなマインド設定をできない子どもが多いのは、そういうものが原因なのでしょうか?
小林 大人も含めて、日本人は総体的に自己肯定感が低いと思います。これには「わびさび」とか「和を以て貴しとなす」とする古くからの文化が、関係しているのではないかと感じます。みんなが自主規制するだけでなく監視をし合い、誰が作ったのかもわからないルールに従い、「和」を大切にする文化。「目立ったことをしてはいけない」という潜在意識によって治安の良さや街の綺麗さが保たれる反面、いろいろな可能性も同時に蓋をされてしまっていることも少なくないような気がします。
日本から出た今、長く根付いた文化が自己肯定感の低さを助長する感覚について、さらに思いを強めました。大人たちは、意図しないまま、子どもたちに自分たちの低い自己肯定感を受け継がせてしまっているのかもしれません。子どもたちは、まず周りの大人に信じてもらわないと、自ら挑戦していくことはなかなかできないでしょう。
自己肯定感の低さと、自分たち自身が信じてもらえなかった体験、規範から外れるのは良くないと教え込まれそれを当たり前と思って育ってしまったこと。代々受け継がれているこうした要素が日本の課題なのではないでしょうか。
それに「失敗すること」に対する免疫が低いようにも感じます。例えば私のように、偏差値が全国模試で28のときに、偏差値が70の慶應に行きたいと言うと、ほとんどの大人は止めに入ります。「リスクがでかすぎる」と。でも、高い目標を前に努力をすることは、結果がどうであれとんでもない成長を伴うわけで、「挑戦しないほうがいい」理由が、私には思い浮かびません。結果だけでなく、その過程でその本人がどれだけ成長できたかを評価できる大人が増えれば、子どもたちはもっとのびのびと、やりたいことに挑戦できるんじゃないかなあと思います。
自信は、自分との約束を守ることで生まれる
−−子どもたちは、自己肯定感が低い大人に囲まれている環境を変えることができるのでしょうか? 自分の手でカスタマイズしていくことの重要性についてお話しいただきたいと思います。
小林 ビリギャルとして活動していると、多くの後輩たちや先生、保護者の方と話をする機会に恵まれます。そして私は重要なことに気が付きました。私が大学受験で成功できたのは、「環境に恵まれていたから」ということ。それは、お金持ちだったから、とかそういうことではなくて、「信じてくれる人がいたから」ということです。やりたい、と自分で決めたことに、さやちゃんだったら絶対にできるよ、と飛び上がって喜んでくれた母。正しい努力の仕方を教えてくれて、伴奏してくれた坪田先生がいた。でも、多くの子どもには、そういう大人が周りに誰もいないのだということを、これまで痛感してきました。
親御さんだって、子どものことが大好きで、幸せになってほしいと心から思っている。でも、子どもが何かに挑戦したいと言ったとき、手放しに喜べる人は、比較的少ないのではないでしょうか。心理学で「ピグマリオン効果」という言葉があります。これは、「人は信じれば伸びる」という効果です。反対に「あなたにはどうせ無理だからやめておきなさい」などのネガティブな言葉をかけ続けると、能力もモチベーションも下がり、結果も望めなくなるというのが「ゴーレム効果」といいます。“良かれと思って”子どもの可能性に蓋をしてしまっているケースは少なくないです。
まずは、大人が価値観をアップデートすること。これが最も重要だと感じていますが、子どもたちには、「環境は自分で選べるよ」とも伝えています。別に親に理解してもらえなくても、学校や塾の先生があなたにワクワクの種をくれるかもしれないし、一冊の本やアートが、あなたのモチベーションになるかもしれない。なるべく多くの選択肢を持てるように、なるべく広い世界と接点を持つ努力をしてほしい、と伝えています。
−−子どもたちには、勉強に対する自分なりの考え方があると思います。子どもたちの気持ちを尊重しながら、可能性を消さない学習メソッドには、具体的にどんなものがあるでしょうか?
小林 セオリーとしてのメソッドはいろいろありますが、まだプロフェッショナルな教育者ではない私が「これがいい」とは言えません。ただ坪田先生(※)と母からいい教育を受けた立場の人間として言うなら、子どもがやってみたいことをダメだと思わせないようにする姿勢が大切です。
うちの母がたったひとつ、子育ての指針としていたのが「ワクワクする目標を自分で設定できるような人になってもらいたい」ということでした。ワクワクすることを自分で見つけ、それを目標にして一歩踏み出せる勇気を常に持っていられる大人になってほしいと思っていたそうです。
私は、こうした考え方が自分の根底にあることを感じています。子どもがワクワクする気持ちを邪魔しない。挑戦して進歩し成長して小さな成功を感じられたら、一緒に喜んであげる。それが次のチャレンジにつながっていけばいい。母はそう思っていたようです。仮に間違ったり失敗したりする時は、「これってすごく重要なステップだよね」ということをちゃんと伝え、それが成長につながればいいという感覚がありました。小さいころから母が「さやちゃん、ナイスアイデアだね」とか「よく挑戦できたね」といった言葉をずっとかけてくれていたんです。だから中学受験も自分からやりたいと思いました。中学受験に関しては、知識の基礎よりも自己肯定感の基礎が固まったという意味で本当によかったと思っています。
※坪田信貴さん:小林さんを導いた教育家であり、『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』の著者。坪田塾塾長。
−−そこからさらに踏み込んで、ネガティブな思いを消す方法や、子どもたちの成長を促す成功体験の刷り込み方について教えてください。
小林 さまざまなことに挑戦できる人とネガティブな人の違いは、トレーニングをしているかどうかということだそうです。ものごとの多面性をとらえるための働きをする前頭前野という脳の部位が発達している人は、攻略法をうまく立てることができたり、何かに挑戦する勇気があったりする人です。
私の場合は「挑戦してみよう」「やってみたらできた」といったことが、勝手に蓄積された成功体験のようなものとなりました。こうしたトレーニングを通して、たまたま前頭前野が比較的発達したと思うのです。
経験がない人は、自分で意図的にしていくしかないと思います。ただ、いきなり大きなことをやるのは無理です。少しずつでも成功体験を積み重ねていくことがトレーニングになります。自信は、「自分との約束」を守ることで生まれる、と坪田先生は言います。自信とは、自分を信じることです。約束を守る人は信頼できますよね。自分自身に対しても同じで、自分を信じる力は「実績がある自分ならできる」という思いから生まれます。自分との約束を確実に守り、積み重ねていけば自信になって、一歩を踏み出す勇気が生まれると思います。

“ティーチャー”ではなく“コーチ”になるという感覚を持つ
−−小林さんは実体験を積み重ねた結果、ポジティブ思考の大人になれたのでしょうが、大人がものごとにポジティブに取り組んでいく姿勢を見せること、そして自らがロールモデルになることの大切さについて聞かせてください。
小林 これはまさに今私がやっていることで、今回の留学を決めた動機でもあります。講演会では、ビリギャルの話を中心にしてきましたが、やがて「私はいつまでこの話をしてるんだろう?」と思うようになりました。受験しただけなのにすごく偉そうだという感覚もあって「私は何者なんだろう?」「調子に乗ってないかな?」という気持ちが拭えず、違和感が積み重なっていきました。
32歳のころ、ある女の子に「人生で後悔していることはないんですか?」と尋ねられたことがあります。自分でもびっくりしたんですが、すぐに「留学しなかったこと」と答えました。「だからみんなは、留学にちょっとでも興味があったらしといたほうがいいよ」と言ったのですが、同時に「なんで私は今から行こうとしないんだろう」と思いました。
子どもたちに対して「やってみなければわからない」「飛び込む勇気を持とう」と言っているのに、自分がそうしていないという違和感が私の留学の動機です。ワクワクすることがあるのに、怖気づいているのは自分だと気づきました。何歳からでも挑戦していいんだぞ、ということをもう一度みんなに伝えたいですね。YouTubeチャンネルを開設したり、「年内にTOEFL100点取るから見てて!」と宣言したり、ロールモデルになる気持ちはとても強かったと思います。
私は、それが大人のあるべき姿だと信じています。子どもたちを追いかけ回して「勉強しなさい」と言うのではなく、「あんなに学び続けてる人がいる。自分もああなりたい」とか「大人になるのが楽しみだ」とか、子どもがそんな風に思える大人がいっぱいいるべきです。
−−たくさんの講演や大学院での研究を体験している小林さんは、“ティーチング”と“コーチング”の違いについてどのように考えていますか? 具体例を通して教えてください。
小林 簡単に言うと、(私が通っていた)学校の先生と坪田先生の違い。それがティーチングとコーチングです。コーチングという言葉の定義は「大切な人を目的の場所まで連れて行くこと」であり、何かを教え込んだり知識を詰め込んだりすることではありません。
認知科学の研究が進む以前は、「人間は無能で受動的な生き物で、自ら学ぶ能力がないから、一人前にするために教育しなくてはならない」と考えられていた時代があります。残念ながら、今の日本の学校教育はこうした概念に立脚するシステムであると感じられます。それがティーチングだと思います。
コーチングはモチベーションを保ったり、自分を信じる力をはぐくんであげたりすることが主となります。学んで成長していくのは本人なので、その人のために環境を整備すること、モチベーションを引き出し維持することがコーチングの目的なのです。
坪田先生がしてくれたのはまさにコーチングでした。とにかくずっと対話していただけです。子どもが何に反応するか、どんなものに憧れているかをわかっていないと、能力を引き出すことやモチベーションに火をつけることはできません。だからこそとにかく対話して、学習者のことをよく知るというステップから入ります。
そもそも人それぞれ学び方や考え方、感じ方は違うわけで、それなのに一つの手法で一斉に教えて、同じ速度で学ぶことを強制され、その成果をたったひとつのものさしではかるなんていうのは、かなり難しいのではないかなと思います。今、教育は変わろうとしている重要な過渡期だと感じます。より様々な尺度で、学習者自身の主体的な学びや成長を効果的に評価できるような仕組みと、教育者が増えるといいなと思います。
−−ティーチングとコーチングの区別がつかない親たちは少なくないと思います。子どもの学習活動について、ただ高圧的にさまざまなタスクを押し付けるだけではなく、どんなことに気を付けるべきでしょうか?
小林 学びとは何なのか。一歩引いて考えたいのです。親御さんたちにとっての学び、子どもにしてほしい学びは何か。多くの知識を正確に覚えることが学びであると思っているのなら、それはもう古いでしょう。
今の時代の重要なスキルは、「持っている知識で新しい価値を生み出していくこと」です。何のために学ぶのかということをもう一度考えてほしいです。子どもたちにとって、幸せとは何なのか? 面倒くさいかもしれないけど、もう一度そこをじっくり考えてみてほしいのです。テストでいい点数をとることが、子どもや親御さんの幸せではないはずです。ぜひ、家族で話し合ってみてもらえたらと思います。正解はないです。でも、そこを考えると自ずと必要なことが、見えてくるはずです。親も、子どもと一緒に学び続ける、をすべきです。親が学んでいれば、子どもは勝手に学びます。
それに、親御さんにとっての“当たり前”が、社会の第一線に立って次の世代を生きて行かなければならない子どもたちの“当たり前”では、もうないかもしれないということを忘れないでほしいとも思います。お子さんが、自分で目標を持ち、自分の意思で一歩踏み出し、自分の人生を自分で生きていかなければいけないのです。だから、まずは親御さんが「失敗させる」ことにも免疫をつけなければいけません。子どもよりも親が、「失敗してほしくない」と思うあまり、挑戦させる勇気がないケースを多く見ます。
子どもたちには子どもたちの社会があり、親御さんたちの時代とは違うので、子どもからも学ぶという姿勢がいいと思います。それぞれの価値観を尊重して、大人もいろいろな視点から学ぶことが大切だと思います。
−−大学院生時代、小林さんは中学校で実践的な研究をされていましたが、当時の子どもたちと小林さんご自身が子どもだった時を比べての変化や、今の子どもと昔の子どもは違うという印象がありますか?
小林 生徒たちの表現の仕方が変わってきたと思います。先日たまたま目にしたのですが、授業中の先生の様子を隠れて動画で撮って、それをネットに上げてあざ笑うような投稿をしていた高校生がいました。私が学生だったころは、先生に面と向かって反抗していた。それが今では、SNSという手段を生徒たちが手にしてしまったので、より陰湿で見えにくく、表現の仕方も複雑になっていると感じます。
中学校での共同研究で感じたのは、先生方のアップデートが追いついていないということです。これは先生たちのせいではなく、仕組みの問題です。学習指導要領の変化などに加え、日々の業務、人員不足、様々な問題が先生たちを常に取り巻いています。先生になる過程で教えられてきたことが昔の型に当てはめたものだったりするので、新しい学習目標を実現するために必要な新たなスキルや高度な知識を習得できないままに、現場に立ち続けなければならない現状があります。この仕組みから考え直さなければならないでしょう。教員養成課程で何を学ぶべきなのか。さらにはどのように教師が「学び続ける」ことを実現するのか。そのあたりから一斉に仕組みとして変わっていかないと、理想的な教育を実現するのは困難なように感じます。
中学校との共同研究では、協調学習を通してもたらされた生徒たちの変化が先生たちを支え、学習観が安定しました。先生たちも学ぶことを欲しているけれども、そのための時間もリソースも機会も与えられていないこと、先生たちがそれを嘆いていることもわかりました。仕組みが変わって、色々な立場の人たちが学びの重要性を同時にとらえ直すことが一番大事であると学びました。
日本が「世界一幸せな子どもが育つ国」になるように
−−小林さんのお話の核の部分は、“信じること”であると感じられます。そこで、子ども自身も先生もそして親も、何かをリアルに信じられるようになる方法論についてお聞かせください。
小林 “何を”という部分に関しては、何でもいいと思います。日本では「ワクワクすること」をダメだと思う人がすごく多いと感じます。勉強も仕事もワクワクするものであるはずがないと決めつけているのではないでしょうか。私はよく「達成できたら鼻血が出るくらいのワクワクする目標を設定しましょう」と言います。
坪田先生が、勉強に対する準備がまったくできていなかった私という車のエンジンをかけてくれたおかげで、効率よく走ることができました。多くの子どもたちは、エンジンがかかっていないままずっと後ろから押されながら、ちょっとずつ進んでいる状態だと思います。能力うんぬんではなくて、1年で偏差値が40も上がるなんていうことは、そもそもエンジンがかからないと無理です。
−−坪田先生にエンジンをかけてもらって、学年ビリの学力から慶應大学合格までフルスロットルの状態で走り切ったわけですが、それをキープする原動力は何だったのですか?
小林 最初の原動力は櫻井翔くんが慶應大学に通っていたということでしたが(笑)、次第に坪田先生みたいになりたいと思うようになりました。坪田先生は常に「教育は憧れだと思う」とおっしゃっていて、私もシンプルにそう感じます。「あんな人になりたいな」という気持ち。学校の先生になりたいという人たちに「昔、いい先生がいたんでしょ?」と訊ねると、ほぼ全員がそうだと答えます。
教育は憧れ。本当にそう思います。私の場合は完全に「坪田先生みたいになりたい」「こんなに面白い大人がいるならもっと世界を広げたい」と思ったことがアクセルになりました。
−−子どもたちが無理をしないまま自分自身であることが心地よくいられる方法、そして自分なりのモチベーションを保ち続け、大きくはぐくんでいく方法についてお聞かせください。
小林 私が意識したのは「難しすぎることをやらない」ということでした。自分の能力よりもちょっと難しいことをやり続ける姿勢が、成長曲線を一番良い状態で保つことにつながるといわれています。モチベーションも保てず、好きでもないことをやらされるのは嫌ですが、「これはまあまあ得意だからできる」ということなら頑張って磨きをかけていけるでしょう。勉強もそうです。勉強嫌いになる理由は単純に「できないから」であって、できないものを好きになるのは難しいはずです。
勉強ができなくなる子が増えていく理由は、システム的に一人ひとりの速度や学び方に合わせることができないからだと思います。一度倒れたら立ち直るのは難しいでしょう。そういう状態では自分の能力が低いと勘違いしてしまい、話が「地頭が悪い」という方向に進みがちです。でも、戻ればできるのです。これはすごく大事なことです。戻るというより、埋めに行く感じかもしれません。スカスカなものの上には何も積み上げられません。だからスカスカなところを埋めに行って、階段と同じように一段ずつ上っていくべきです。
−−大学院修了後のプランについて教えてください。日本に戻るのか、それともアメリカで研究活動を継続しますか?
小林 日本を「世界一幸せな子どもが育つ国」だと言われるようにしたい。私にはそういうビジョンがあって、どんな形であっても、そこに貢献したいと思っています。
今は必死で英語を勉強している状況ですが、留学が終わるころには、自分がすごくアップデートされていると思います。これまでの価値観が根本的に変わる大きな経験になるでしょう。だから、今何かを決めたところでそれは絶対変わるだろうなというのが正直な気持ちです。でも、今一番興味があるのは、日本の学校の先生たちの学びの場をつくりたい、ということです。日本の先生の質はとても高いと感じています。あんなに情熱があって献身的な先生が集まっているのは本当にすごいことです。だから、その情熱や労力を、正しい方向に向かわせてあげるだけで、本当に多くの子ども達の未来が変わると思っています。卒業後といわず大学院在籍中から、そういったことに貢献できれば、とは思っています。
インタビューの最後に、小林さんはこうも話した。「こんなに勉強し続ける人生になるとは、思っていませんでした。でも、問題意識を持ってすると、勉強はとても面白いです。それを多くの人たちに知らせたいです」
何を勉強するか。どのように勉強するか。勉強する気になるのに遅すぎるということはない。そして、その気になったらすぐに実行すべきだ。筆者が抱いたこういう思いを、一人でも多くの人に共有していただきたいと願っている。