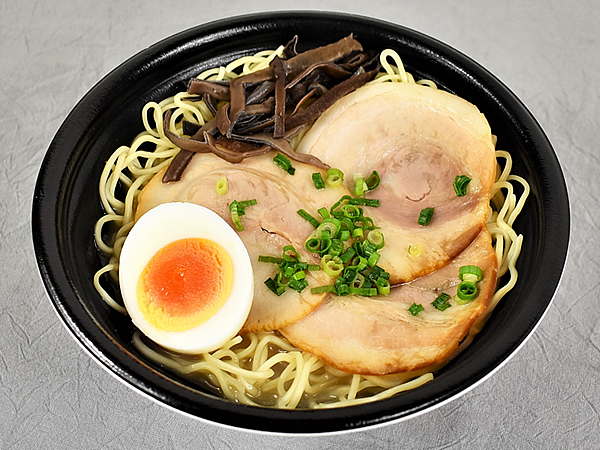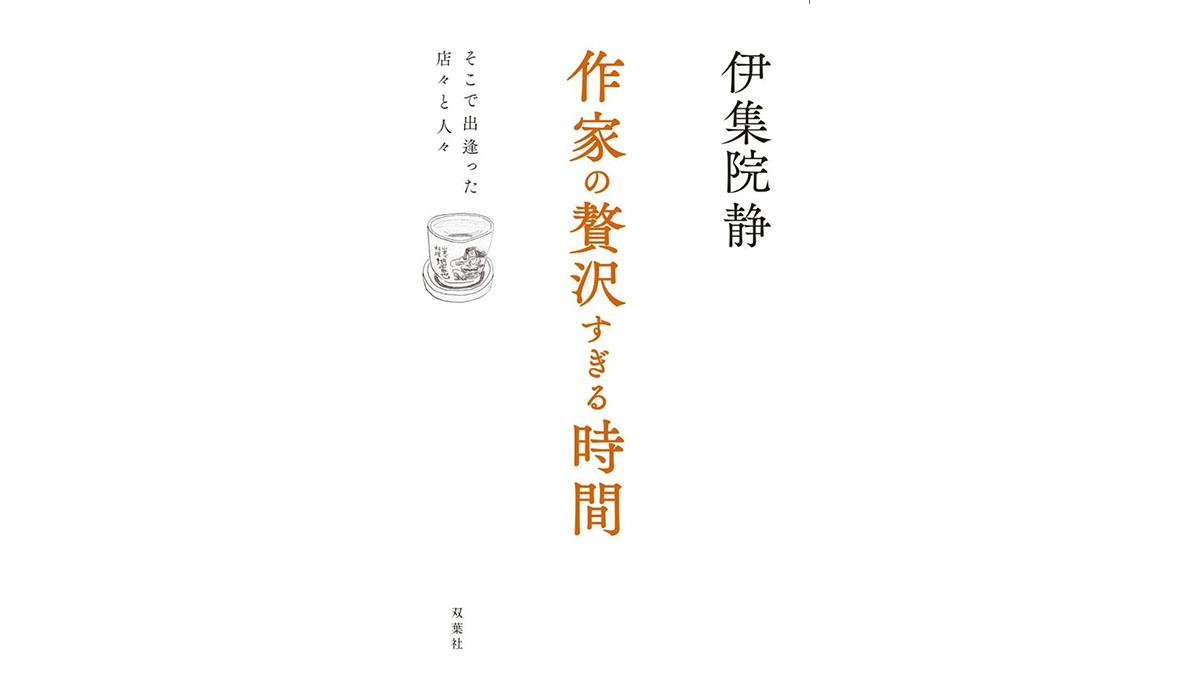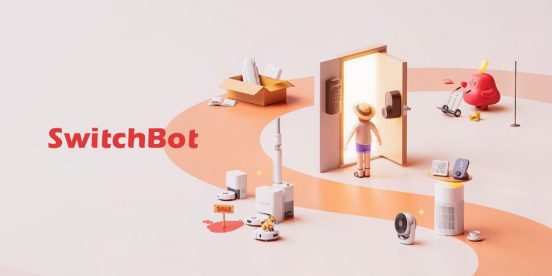「SF映画の主人公のように、巨大なロボットを操縦できたら……」と思ったことはありませんか? そんな夢を実現させてしまったのが、EXOSAPIEN社のジョナサン・ティペットCEOで、まるで自分の手足を動かすように操縦できるロボットスーツ「プロステーシス」を開発したのです。ティペット氏はどのような思いでこのロボットを作り、設計しているのでしょうか? 2月に開催されたダッソー・システムズのテック系イベント「3DEXPERIENCE World 2023」でティペット氏が語りました。

一際目立つ赤いパイロットスーツで舞台に立ったティペット氏。「もし巨人になれたら何をするだろう?」をテーマに会社を立ち上げたと語り始めました。
「私が開発した『プロステーシス(PROSTHESIS)』は、アートとテクノロジーを駆使し、6年間のタフなフィールドワークで得たデータをつぎ込んで作り上げたロボットスーツです。ロボットスーツはパワースーツ、またはパワーアシスト装置を意味しますが、プロステーシスのサイズは高さ4m、幅4.5m、奥行5.2mで、総重量は4000kg。パワーは200馬力で、操縦者の力を50倍まで引き上げることができます。2020年にはギネス世界記録に『世界一巨大な四足歩行の装着型パワーアシスト装置』として認定されました」とティペット氏は語ります。
人工知能は搭載しない
プロステーシスに操縦かんはありません。自分の手足の動きがマシンと直接連動しているので、人間が本来持つパワーを引き上げたまま、自分の身体のように動かすことが可能。足場の悪い山道も川の中も難なく進めるうえ、クルマを潰したり持ち上げたりすることもできます。
AIのような人工知能を搭載せず、あくまでも人間が操縦するように設計した理由は、楽しさを追求したかったから。「個人的にはスポーツのような位置づけで、ビジョンは国際的なスポーツエンターテイメントにすることだ」とティペット氏は話します。プロステーシスの開発には16年を費やし、脚部をスケッチするだけで1年、デザインの完成には5年かかったそう。エンジニアとしての経験と知識をフル活用し、最初の頃はデザイン、設計、組立を全て自分で行ったと言います。
進化を続ける「巨人たち」

3DEXPERIENCE World 2023では、ファン待望のプロステーシス新型機「プロステーシス2.0」が発表されました。
「次世代機のプロステーシス2.0は、従来モデルに比べてサイズは3分の2に、重量は半分に改良しました。それでいてパワーは2倍。スピードもアップし、時速20~30キロで進むことができます。将来的には、プロのアスリートに装着してもらい、広大なスタジアムで障害物コースにチャレンジするようなスポーツエンターテイメントに発展させたいと思っています。面白そうでしょう?」(ティペット氏)
その一方、EXOSAPIEN社では新たなプロジェクトが進行しているとティペット氏は話しました。
「プロステーシス・シリーズで得たノウハウにクルマの要素を加え、全く新しい概念のマシンを製作中です。この新マシン『エクソクワッド(EXO-quad)』には、オートバイ、ロボットスーツ、4輪という3つの特徴を詰め込みました。バイクにまたがるように乗るのですが、タイヤを装着した4本の脚はパイロットの手足と連動しており、体勢をリアルタイムで自由に変えることができます。乗っている感覚としては、思うままにコースを変えながら走れるローラーコースターでしょうか。道の上を飛ぶように走れるのです。
開発のきっかけは、ラスベガスの企業からの問い合わせでした。レーシングカーの乗車体験を提供している会社で、そこでプロステーシスを扱えるかという内容でした。プロトタイプのプロステーシスは操作が複雑で、自分で操作できるようになるまで3~4日はかかります。そこで、もっと簡単に操作できるマシンを作ろうと思ったのです。エクソクワッドはバイク感覚で乗れますし、曲がるときは身体を傾けるだけ。初号機のデビューは1年後を予定しているので、ぜひ楽しみにしていてください」
人類の新たな希望?
「巨人になってみたい」という憧れを、その技術と行動力で実現させたティペット氏。この巨大マシンは、人類が直面しているさまざまな問題を解決できる新たな希望だとも語ります。
人間の持つ能力や創造性をパワーアップさせるとともに、エンターテイメントとして遊び心も満たしてくれる巨大ロボットスーツ。今後の活躍に、世界中のファンが期待を寄せています。
執筆者 / 長谷川サツキ
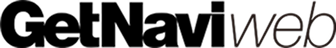
-239x240.jpg)