今から30年以上前、まだ高校生だった僕は、なぜか1970年代のフォークにはまっていた。泉谷しげる、古井戸、斉藤哲夫、なぎら健壱、ザ・ディランIIなどなど。ギター1本で歌うスタイルというものに憧れていたのかもしれない。
そのなかで、強烈なインパクトを受けたのが高田 渡だ。ひげ面のおじいさん(当時はまだ40歳くらいだったと思うが……)が、ぼそぼそと歌っているのを見て、なんだかすごいなと思った記憶がある。
それから、当時のレコードなどを収集するようになり、高田 渡のデビューアルバム(五つの赤い風船とのカップリングLP)なども手に入れた。歌詞はユーモアと批判性があり、曲はアメリカのフォークソングのマインドがあり、真似しようにもなかなか真似できない感じがあった。
そんな高田 渡は、2005年、56歳で逝去。24時間お酒を飲んでいるような人だったので、それほどショックは受けなかったが、偉大な人が亡くなったなという感じがした。

ステージのトークさながらの飄々とした文章
その高田 渡が書いたエッセイが『バーボン・ストリート・ブルース』(高田 渡・著/筑摩書房・刊)。自身の幼少期のことから、好きな映画、日々思うことなどが軽快な文章で綴られている。
高田 渡の文章を読んでいると、なんだかほのぼのした気分になる。ステージ上でのトーク同様、どこか飄々としていて、辛辣なことを言っていたりするのだが、まろやかに届いてくる感じがするのだ。
全国を旅して歌を歌っているとさまざまなことがある。それらを淡々とした文章で語られていると、思わず笑ってしまう。
三陸方面で主催されたコンサートに出演した際、その主催者が暴走族だったことがあるという。コンサートの後、暴走族の車で飲み屋に行き、次の日には一緒に海で遊んだりしたそう。
当時の三陸海岸方面の暴走族は僕のファンだったようである。だとすると、彼らは僕の歌をガンガン鳴らしながら暴走行為を繰り返していたのだろうか。
『バーボン・ストリート・ブルース』より引用
高田 渡の曲は、どう考えても暴走行為には向いてないように思うのだが……。でも、そういう層にもファンが多かったのは事実のようである。
「死ぬまで歌い続ける」を実践
本書を読んでいると、「ずっと歌を歌っていきたい」という主旨の文章がときどき出てくる。
僕は、死ぬまで歌い続けるのが歌い手だと思っている。歌わなくなったときが終わりだ。
『バーボン・ストリート・ブルース』より引用
実際に彼は、1年のほとんどを全国のどこかで歌って過ごしてきた。そして、2005年。コンサートを行った北海道で容体が悪くなり、そのまま入院。そしてあの世へ旅立ってしまった。
まさに、死ぬ直前まで歌っていたのだ。そう考えると、とても幸せな人生だったのではないだろうかと思う。
ホンモノは時代を超える
デビュー曲が「自衛隊に入ろう」という、当時の世相を皮肉ったコミカルな曲だったため、そういうイメージで見られがちだが、高田 渡はギターやマンドリンなどの楽器も上手く、ブルースやカントリーなどの音楽に造詣が深く、もちろん文学や映画にも詳しい。それでいて、富や名声に興味がなく、ただ毎日楽しく暮らしたいという、なんだか本当に仙人のような人なのだ。
今では、若い世代でも高田 渡を聴く人が増えているという。やはり、ホンモノは時代を超えて受け継がれていくのだろう。
現在はCDも手に入れやすくなっている。高田 渡に興味を持った人は、ぜひ曲を聴いてみてほしい。そして本書も一緒に読むと、数々のミュージシャンが高田 渡のことをリスペクトする理由がわかるのではないだろうか。
【書籍紹介】
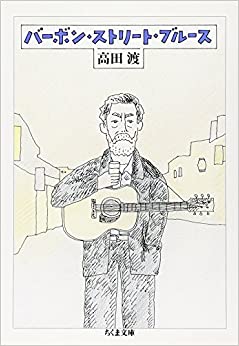
バーボン・ストリート・ブルース
著者:高田 渡
発行:筑摩書房
フォークソングが一世を風靡した頃、奇妙な曲「自衛隊に入ろう」が話題になった。「あたりさわりのないことを歌いながら、皮肉や揶揄などの香辛料をパラパラふりかけるやり方が好き」な高田らしいデビュー曲である。以後、世の流行に迎合せず、グラス片手に飄々と歌い続けて40年。いぶし銀のような輝きを放ちつつ逝った、フォークシンガー高田 渡の酔いどれ人生記。