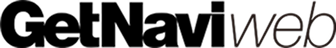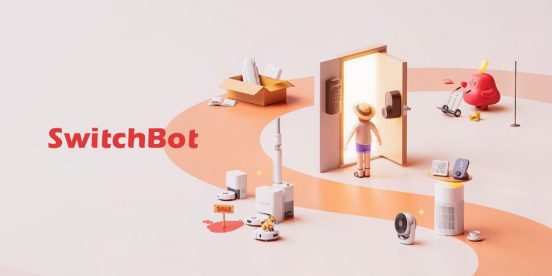認知症は怖い病気だから、食生活や生活習慣の改善で防げるものなら防ぎたい。もし発症してもなんとか進行を遅らせたい。誰もがそう思っていることだろう。
が、思えばひと昔前は、「いや~、うちのおばあちゃん、このごろボケちゃって」とか「おじいちゃんの物忘れがすごいのよ」とか、加齢に伴う様々な症状に対し、家族の反応は今よりずっとのどかだった気がする。
そもそも”認知症”は、2004年に厚生労働省によって生まれた言葉。それ以前に呼ばれていた「ボケ」や「痴呆」などには侮辱性があるとのことでそれらをやめ、まとめて”認知症”と言い換えられることになったのだ。
ところが”認知症”という言葉のパワーが強すぎるせいか、家族の誰かに認知の症状が少しでも現れると、それが不幸のはじまりのように考えてしまうケースが多いのではないだろうか。
私のおばあちゃんは認知症だった
明治生まれの私の祖母は今から40年も前、80歳を迎えることなく老衰でこの世を去ったが、亡くなる前の10年間ぐらいは今でいう認知症だった。夜中にこっそり家を抜け出し、隣の家に上がりこんでしまうような徘徊も頻繁だったし、家中のティッシュペーパーを箱から次々と出して自分の布団の周りに集める収集癖もあった。
しかし、うちの両親も、また近所の人もそれらを笑いながら話していたものだ。隣のおじさんは「夜中に目を覚ましたらお宅のばあちゃんが枕元に座ってたんだよ。幽霊かと思ってびっくりだったよ。そんでも、ばあちゃん転んで怪我することもなかったし、よかったよなぁ」などと暢気に話していた。
まあ、当時は田舎の家はどこも玄関の鍵などかけずに寝ていた時代だから、徘徊の老人が突然上がりこんで来ても不思議ではなかったし、また、年をとったら多少はボケるとみんなが思っていたので大騒ぎすることもなかった。父と母も祖母の介護で悩んだり、特別な苦労はしていなかったと記憶している。それは近所にいた他のお年寄りも含め、それぞれの認知の症状を各家庭で隠すことなく、オープンにして町内全員で見守ることができたから、気も楽だったのだろう。
はじめはやっぱり「認知症」を隠してしまう
さて、『お母さんは、だいじょうぶ 認知症と母と私の20年』(楠章子・文 ながおかえつこ・まんが/毎日新聞出版・刊)は、認知症状をテーマに描きベストセラーとなり、映画化もされた『ばあばは、だいじょうぶ」の著者の新刊。
若年性アルツハイマー型認知症になってしまった実母の介助生活を綴ったもので、家族が幸せになれる介護への道を教えてくれる。4コマ漫画と介護エッセイという構成は、認知症という重いテーマを扱っていながらも楽しく読み進められる。登場人物を名前ではなく”野菜”にしてあるのもいい。認知症になってまった母親は「トマト」、父親は「ナッパ」、姉は「オネギ」、兄は「オイモ」、愛犬は「キクナ」、そして著者は「オマメ」だ。
トマトが認知症を患いはじめたのは20年前、トマトは60歳を過ぎたばかり、その時オマメは25歳だったそうだ。はじまりはあいまいで、同じことを何回も聞く、言ったはずなのに忘れてる程度だったという。
ところが、やがて約束を忘れる、作業を途中でやめて他のことをしているなど、年をとったらこのぐらいのレベルを超えるようになっていった。
そんなトマトを見て、私もナッパも心の中でつぶやきました。(ああ、アルツハイマーやな)と。実は亡くなったおばあちゃん(母の母)が同じような感じで、若年性アルツハイマー型認知症という診断を受けていたからです。(中略)この時点で診断を受け、進行を遅らせるお薬を飲み始めていればと悔やまれますが、治らないなら、診断を受けたくないと思ったのです。(中略)検査をすることで、勘の鋭いトマトは、自分の病を疑うでしょう。
『お母さんは、だいじょうぶ 認知症と母と私の20年』から引用
その後、ゆるやかにも症状は進行し、トマトは診断を受けることとなり、薬を飲み始めた。当時、オマメは誰にも「母が認知症」とは話せず、家庭での介護はかなり閉じた状態になっていたそうだ。
仕事一番、介護は二番
しかし、家族だけの介護には限界がやってきた。ある日、トマトを病院に連れて行った帰り道、オマメはふっと目に入った特別養護老人ホームの看板を見て、ふらふらと入っていったそう。入所させようという考えはなく、そこには「ケアマネジャー(介護支援専門員)」がいると思ったからだ。突然の訪問にもかかわらず、このホームはケアマネに連絡を取ってくれたのだ。
現れたケアマネのバナナさんに、私は「母が認知症で困っています」と訴えました。「お母さまの状態を教えてくれますか?」と聞かれて、私はたくさん話しました。(中略)「だいじょうぶですよ、デイサービスなどいろいろありますから」その言葉がやさしくて、私はスイッチが入ったみたいにわんわん泣きました。
(『お母さんは、だいじょうぶ 認知症と母と私の20年』から引用)
こうしてバナナさんにはその場でトマトのケアマネになってもらえることになった。
その後、自宅への訪問介護や通いのデイサービス、そして短期の宿泊サービスなどを組み合わせることができる小規模多機能型居宅介護サービスの管理者のリンゴさんとも出会い、介護をチームワークで行えるようになっていったそうだ。
介護100%の生活はしないほうがいいというプロのアドバイスもあり、兄オイモ、姉オネギ、そしてオマメは、「まず自分たちの仕事はしっかりやること」と決め、仕事一番、介護二番を実践することになった。その結果、明るく幸せな介護ができるようになったとオマメたちは感じているようだ。
そう、ひと昔前の日本のように、世の中は助け合いで回っていると考えればいいのだ。
人間の芯の部分は認知症になっても奪われない
さて、本書で私がいちばん感動したのは、トマトの認知症発症から20年が経ち、表情も乏しくなり医師からも感情がどれだけ残っているのかわからないと言われていたなかで起きた二つの奇跡だ。
家族の愛犬、キクナが16歳で天寿を全うしたときダンボールの棺をトマトに見せたときのことだ。
みるみるトマトの表情が変わり、目にうっすら涙を浮かべたのです。表情の変化は気のせいではなく、確かなものでした。
『お母さんは、だいじょうぶ 認知症と母と私の20年』から引用
さらに、トマトを守り抜くと誓い、奮闘してきた父親のナッパが病に倒れ先立ってしまったときのこと。
すでにトマトは目さえ開けず、眠ったままのようなことが多かったという。トマトの負担にならないようお葬式は最初の十分だけと予定を立て、ヘルパーが迎えに行くと、トマトは「嫌!」と大きな声で言ったそうだ。トマトの発する声を皆が聞いたのは5~6年ぶりだったという。
気丈な父でしたが、さらに気丈な母です。ちゃんと送り出すのは、妻の務めと思ったのかな。やはり人の芯の部分というのは、認知症にも奪えない。
『お母さんは、だいじょうぶ 認知症と母と私の20年』から引用
たった今、認知症の家族の介護で悩んでいる人、もし家族や自分が認知症になったらどうしようと不安に思っている人、みんなに読んでほしい一冊だ。
【書籍紹介】

お母さんは、だいじょうぶ 認知症と母と私の20年
著者: 楠 章子、ながおかえつこ
発行:毎日新聞社
認知症を描いたベストセラー絵本&映画『ばあばは、だいじょうぶ』の著者、実母の介護生活でたどりついた明るく幸せな介護への道!後悔と罪悪感を抱え、たくさん泣いてきた20年。世の中は助け合いでまわっていると知った。家族の愛と涙あふれる介護エッセイ&4コマまんが!
楽天koboで詳しく見る
楽天ブックスで詳しく見る
Kindleストアで詳しく見る