パリ市は東京の山手線内と同じくらいの面積の街で、その昔、パリは城壁でぐるりと囲まれていた。ヴィクトル・ユーゴーの代表作『レ・ミゼラブル』で描かれているのは城壁があった時代のパリを背景としている。壁はやがて解体され、現在は、ヴェルサイユ門、オルレアン門、モントルイユ門、クリニャンクール門……など、門があった場所にその名が残っているだけだ。
『郊外へ』(堀江敏幸・著/白水社・刊)は、芥川賞、そして三島賞作家である堀江氏のデビュー作。雑誌『ふらんす』に連載されていたエッセイを一冊にまとめ1995年に刊行されたもののUブックス版だ。既製のパリやフランスのエッセイとは一線を画していて、仏文学者でもある堀江氏が、パリの城壁の外に広がる町を舞台としたフランスの現代小説や随筆を紹介しつつ、批評した読み物なのだ。
私は20年間パリの壁の外で暮らしていた。前半はパリ16区に隣接したブローニュ・ビヤンクール市、後半はパリの南西郊外、ジフ・シュル・イヴェット市にいたので、本書にはなじみのある地名、駅名が多く登場するのでとても懐かしかった。
パリ好きの方でも、本書を読むとパリ市内とは少し違う趣がある郊外の街にきっと興味が湧いてくるはずだ。そして移民国家であるフランスをより理解することもできるだろう。

パリ郊外へのびる小説
連載エッセイだったときのタイトルは”郊外へのびる小説”だったそうだ。本書のあとがきに堀江氏はこう記している。
一連の物語に登場する「私」とその周辺の出来事は、完全な虚構である。背景などに多少の知見はこめてあるものの、彼は「郊外について」の語り手を担っているのではなく、「郊外的」な立ち位置の代弁者にすぎない。もし、実体験を語っていたならば、それは既視感の反復に終わり、なにかに「ついて」言葉を綴ろうとしていたら、郊外「論」になってしまっただろう。
(『郊外へ』から引用)
どの項も、短編の小説を読んでいるような感覚でとてもおもしろい。目次は以下のようになっている。
レミントン・ポータブル
空のゆるやかな接近
夜の鳥
動物園を愛した男
霧の係船ドック
ロワシー・エクスプレス
灰色の皿
給水塔へ
記憶の場所
首のない木馬
坂道の夢想
垂直の詩
タンジールからタンジェへ
ロワシー=シャルル・ド・ゴール空港からはじまるパリ郊外の旅
私たち日本人はパリの国際空港を、シャルル・ド・ゴール空港と呼ぶことが多いが、フランスでは地名を使ってロワシー空港と呼ぶ人が大半だ。
このロワシー空港駅を起点にパリ地方を南北に横切っているのがRERのB線という電車。全長は約60キロで、パリ北駅、シャトレ・レ・アール駅などパリの真ん中を通り、南西郊外のサン・レミィ・レ・シュヴルーズ駅まで計37の駅からなっている。ちなみに私が暮らしていたジフ・シュル・イヴェットも終点から3つ手前の駅だった。
「ロワシー・エクスプレス」と題した項で、堀江氏は『ロワシー・エクスプレスの乗客』という本を紹介している。RERのB線を移動するのではなく、一日ひと駅ずつ「旅」をしてみるというユニークな発想の本で、著者はフランソワ・マスぺロ、写真は彼の友人であるアナイク・フランツだ。ふたりはまず出発点であるロワシーの町へと向かう。
パリ周辺の旅行案内書にも、細部はほとんど記されていない。わずかにパリ郊外を網羅している五万分の一地図に、ロワシー・アン・フランスという名が太字で刻まれている程度である。花の都への玄関ロワシーは通過するための空間であって、旅行者が立ち寄るべき場所ではないのだ。
(『郊外へ』から引用)
マスペロは、生粋のロワシーっ子という老人に話を聞くと、ロワシーでは赤ん坊はひとりも生まれないという。なぜなら小さな町には産院がなく隣町にしかないからだ、と。国際的大都市の近郊に故郷と出生地が一致しない町があることにマスペロは驚くのだった。
旅は続き、パリの北郊外の駅周辺は移民や失業者が多い荒廃した町が多々ある。パリの南側の駅はハイソな町と移民が多い少し荒廃した町が交互にやってくる。マスペロとフランツは1か月をかけてパリ郊外を旅をした。歩くとは、考えるとはこういうことだ、と教えられた気がする。
アラン・ドロンは郊外で生まれ育った
「坂道の夢想」という項では、俳優のアラン・ドロンについて書かれている。ある日、”私”はテレビで白髪になったドロンが子どものころの思い出を語っているのを観る。
わたしは郊外に生まれ育ったので、メトロに憧れていましてね、たまにパリに出ていくとその切符を捨てずに持ちかえって、友達に見せびらかしたり、何度も匂いを嗅いだり、ひどく大切にしていたものですよ、それがパリの匂い、都会の香りでしたね。
(『郊外へ』から引用)
アラン・ドロンの生い立ちはあまり幸福なものではない。パリ南郊ソーの乾物屋に生まれたが、両親が不仲になり8歳で里子に出された。その3年後には養父母も亡くしてしまい、離婚した両親のあいだを行き来していたが、それぞれに別の相手がいたため、厄介者扱いをされ、不安定な少年期を過ごすこととなった。当然のごとく不良化し、停学や放校処分で郊外の町の学校を転々としていたという。最終学歴はリセ(高校)どまりで、演劇を学んだ形跡もない。学業を放棄してからは、豚肉店を経営していた養父を頼って見習いをしていたそうだ。ジョルジュ・ペレックの『ぼくは思い出す』という本の中で、「アラン・ドロンがモンルージュで豚肉屋の見習いをしていたのを覚えている」という一節にがあるそうで、肉屋の使い走りと国際的スターとのギャップには誰もが驚いてしまう。
ちなみにドロンが生まれ育った郊外はすべてRERのB線沿いにある。
映画界に入るきっかけはカンヌ映画祭を冷やかしに出かけたこと。ドロンの美しいルックスが見出され、そこからサクセスストーリーがはじまったのだ。
パリの南郊で生まれたアランという名の乾物屋の倅が、両親にうとまれ、非行を重ねていたのは一九四〇年代のことであり、それはドワノーが写真機をぶら下げて歩き回っていた時代に合致している。『パリ郊外』に登場する楽しげな子どもたちのなかにこの少年がまじっていたら、アラン・ドロンという俳優は生まれていなかったかもしれず、もしかすると、彼にとってはその方がずっと幸福だったかもしれない。
(『郊外へ』から引用)
ロベール・ドワノーの写真集『パリ郊外』については、本書の最初「レミントン・ポータブル」の項で詳しく書かれている。
コロナ後、海外に自由に出掛けられるようになったら、お決まりのパリ旅行ではなく、パリの壁の外を探索してみると意外な発見があるかもしれない。本書はその参考にもなるだろう。
【書籍紹介】
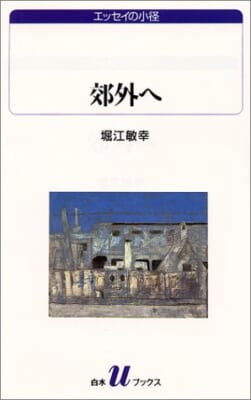
郊外へ
著者:堀江敏幸
発行:白水社
パリを一歩離れるといつも新しい発見があった。卓抜した仕掛けによって、パリ郊外を語りつくした魅惑の書。ドワノーやモディアノなど郊外を愛した写真家や作家に寄り添いつつ、ときに幸福な夢想に身をゆだね、ときに苦い思索にふける、「壁の外」をめぐる物語の数々。三島賞作家鮮烈のデビュー作。


















