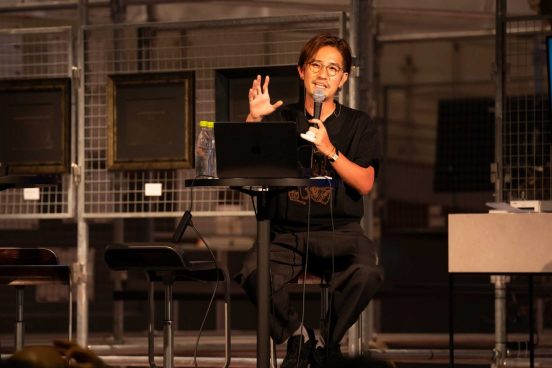デザイナー、経営者、テレビ番組のコメンテーターなど、多岐にわたる活動を展開するアートディレクターの山崎晴太郎さんが新たなモノの見方や楽しみ方を提案していく本連載。自身の著書にもなった、ビジネスやデザインの分野だけにとどまらない「余白思考」という考え方から、暮らしを豊かにするヒントを紹介していきます。第6回は山崎さんがコレクションしている「メガネ」をクローズアップ。自宅には“三軍”まであるという膨大なメガネの中から厳選してご用意いただき、そのこだわりや魅力についてうかがいました。

メガネは“wear”という言葉が付く、唯一の矯正器具
──今回は山崎さんのトレードマークとも言えるメガネについてお話しをうかがいたいと思います。まず、メガネをかけ始めたのはいつ頃からになるのでしょう?
山崎 実を言うと、僕がかけているのって全部伊達メガネなんですよ。
──そうなんですか!? いきなり想定外のお答えに驚きました。
山崎 普段はコンタクトレンズなので、家でかけているメガネには度が入っていますが、仕事でかけるものは全部伊達メガネです。ちなみに、最初にかけたのはメガネではなく、サングラスでした。もともと僕は目の色素が薄く、日常の光でも眩しく感じることが多いんです。それで中学生の頃からサングラスをかけるようになったというのが、僕のメガネの原点ですね。最初は目を守るためにかけていたのですが、そのうちにサングラス自体が好きになっていって。ただ、その頃は中学生ということもあって、周りからはただ背伸びしてかっこつけてるだけの男の子みたいに思われていたと思います(笑)。
──伊達メガネをかけるようになったのは、それからしばらくして?
山崎 随分あとですね。20代はコンタクトレンズだけでしたから、30歳になったぐらいの頃だったと思います。それにはちゃんとしたきっかけがありまして。メガネは唯一、矯正器具がファッション化やカルチャー化したものだということを本で読んだんです。例えば、補聴器は英語で〈hearing aid〉ですが、メガネは〈glasses〉のほかに〈eyewear〉という表現の仕方をする。つまり、メガネには“着るもの=ファッション”という概念や文化が定着化し、その行動変容に感銘を受けたんです。

──確かに、メガネは随分と前からファッションのアイコンになっているという認識があります。
山崎 僕たちがデザインとしてやらなければいけないのも、まさにそういうところなんですよね。本来はマイノリティなものであったり、ハンディキャップを補うためだけだったものの概念を、ただの道具ではなく、多くの人の心に届くように接続していくのがデザイナーの1つの仕事だと僕は思っています。だからこそ、美しく行動変容していったメガネを実際に自分でも体験するために伊達メガネをかけ始めたんです。
──今回、多くのコレクションをお持ちいただきましたが、これらは最初から集めるつもりで揃えていったのでしょうか?
山崎 いえ、気づいたらこれほどの数になってました(笑)。今日は2つのケースを持ってきましたが、家にはまだこのケース1個半ほどの数のメガネがあります。ここにあるのは、いわば一軍と二軍。家には三軍までいるんですが(笑)、一軍は常に玄関に置き、毎日出かける直前に靴と合わせてどれにしようか選んでます。その日の気分によってメガネを変えたくなるので、僕の中でまさしくウェア化していると言えますね。
──素朴な疑問ですが、一軍や二軍は定期的に入れ替わったりするのでしょうか?
山崎 もちろんします。一軍の中にもスタメンとベンチ組がいて(笑)、そのベンチ組を気分や季節によって入れ替えるようにしています。そうしないと、二軍のメガネたちがいつまで経っても上がってこれないので(笑)。たまに自分でも存在を忘れているメガネがあって、久々にかけてみると、“これ、案外悪くないぞ”ということもありますね。髪の色や髪型によってもメガネをかけたときの顔の印象が変わるので、ヘアスタイルを変えると昔のメガネを引っ張り出してきたりもしています。

“時間の痕跡”が感じられるアンティークはそばに置いておきたくなる
──愛用しているブランドを挙げていただくと、どのようなものがありますか?
山崎 EYEVANのシリーズはいつもチェックするようにしています。それに、ayameなど日本のメーカーが好きです。自分の顔の造形を考えると日本のメーカーのほうが相性がいいような気がします。MASAHIRO MARUYAMAも好きでたくさん持っていますが、大体において形が普通じゃないというか、少し変わり種のデザインが多いのでつい買ってしまいますね。フレームにボルトが付いていて、まるでフランケンシュタインのようなものとか(笑)。
──海外ブランドはあまりお持ちではないのでしょうか?
山崎 そんなことはないですよ。メガネを多く集めるようになったのが10年ほど前で、その頃によく購入していたのがOLIVER PEOPLESでした。ちょうどクセの強いデザインのメガネをかけ始めた時期ですね(笑)。あとはMOSCOTやボッテガ・ヴェネタなど。ボッテガ・ヴェネタはいろんなファッションアイテムを展開しているハイブランドですが、たまたま気に入ったメガネを見つけたら、それが偶然にもこのブランドでした。

──購入されるときは、どういった基準で選ぶことが多いのでしょう?
山崎 特別大きなこだわりというのはないのですが、TV出演の際に着用する点で言うと、レンズの径が大きいものを選ぶことが多いです。そのほうが、例えばTVなどに出演しているとき、引きの画でも印象に残りやすいというのがあります。それもあって、たまに放送が終わったあとに、「今日の番組でかけていたメガネはどこのものですか?」という問い合わせがDMで届くこともあります(笑)。
──それだけ、ついメガネに目がいってしまう人が多いということですね。
山崎 反対に、レンズの径が小さいものを選ばない理由として、単純に僕があまり似合わないというのと、視界の中にフレームが入り込んでくることに、少し抵抗があるからというのがあります。レンズが小さいと視野が狭くなったような感じがして、突然何かしらの敵が攻撃してきたときに反応速度が鈍くなりそうで。それは冗談ですが(笑)、視界の中でフレームの存在感が強すぎると、どうしても気が散って集中力が削がれてしまうというのも理由としてありますね。
──なるほど。また、今回のコレクションを拝見するとアンティークのメガネも多いように感じます。
山崎 アンティークはどうしても欲しくなってしまうんです。これは僕のモノ選びすべてに通じることなんですが、時計や家具でもビンテージが多いんです。それは、古き良きものに価値を見出しているというよりも、“時間の痕跡”が感じられるからなんですね。“モノ”を通して過去から今に至るまでの時間を引き継いでいるようにも思えるし、そうした時間の重なりの上に自分がいる感じもして。その感覚を大切にしてくて、アンティークを集めてしまうんです。素材もそうですね。ケミカルなものもよりも有機的なマテリアルが好きですから。
──山崎さんのアートワークも“時間”をテーマにしたものが多い印象があります。
山崎 そうですね。「未来からの化石」シリーズあたりはまさにそうですね。やはり時の流れというものに強く惹かれるみたいです。

形の概念が決定づけられているものこそ、新たなデザインのしがいがある
──山崎さん自身は、メガネをかけるようになってどのような変化がありましたか?
山崎 自分の見せ方が変わりました。それは、例えると初めて腕時計を付け始めたときに近いものがありましたね。というのも、男性って身に付けられるアクセサリーの数が、女性と比べて少ないですよね。だから、多くの男性が腕時計にはまり出すとも言えるわけですが、それと同じように、メガネをかけるというレイヤードが増えたことで、自分の見せ方・魅せ方の武器が追加されたような感覚にはなりました。
──冒頭でもお話しされていた“ファッション化”ですね。
山崎 ええ。それに、メガネのいいところは場所を選ばないということです。ファッションリングやネックレスだとビジネスの場において、状況によっては不適切な印象を与えてしまう可能性があります。でも、メガネだと多少攻めていてもあまり抵抗がない。そこがいいですよね。また、メガネはフレームの色を少し変えてみるだけで、その人の印象がガラッと変わるんです。レンズの形や大きさが1mm違うだけでも、実際にかけてみると顔の雰囲気が大きく変わることもあるので、自分のイメージをチェンジしやすいというのもあります。
──だからこそ、自分に合うメガネを選ぶのが難しい気もします。
山崎 そこはファッションと同じで、まずは冒険してみればいいと思います。最初はリーズナブルなもので試してみて、イマイチだなと思ったり、飽きてしまったら、違うタイプのものに挑戦する。そうすることで、どんどん新しい世界が広がっていきますから。もちろん、他の人とは違う個性を出そうとすると、最初は勇気がいると思います。でも、“ちょっと面白いメガネをかけている人”という印象を一度作ってしまえば、そのあとは本当にすごくラクになります。

──ちなみに、山崎さんがこれまでメガネのデザインをされたことは?
山崎 これが実はないんです。本音を言うとやれる気がしない(笑)。というのも、特殊な思想を求められるような気がするんです。それに、もともとが矯正器具なので、迂闊に手を出せない領域という思いもあって。でも、新しいことに挑戦するのは大好きなので、もし機会があればやってみたいですね。特に、メガネのように既にデザインがほぼ完成されているものに挑むことには興味があります。カトラリーやワイングラスなどもそうですが、“これ以上やりようがない”と思えるからこそ、デザイナーとして興味深い領域です。
──既存の“こうあるべき”という概念を覆していくのは難しそうであり、面白そうです。
山崎 どちらかだと思うんですよね。概念から大きく外して新たなデザインを提案していくか、あるいは概念のど真ん中をより研ぎ澄ませていくか。ワイングラスは後者の研ぎ澄ます方向に行くような気がします。例えばですが、ワインに対してのデザインはもう完成されているので、人に対してデザインを向けていく。そうすると、人の唇の厚さごとに20種類ほどのラインナップを作り、その人に一番しっくりとくるグラスを提供するなどのアイデアが出てきます。とか。いわば、受け取り側の需要に向かってマッチングさせていくデザインですよね。そういったコラボ企画をいつかGetNaviでもやってみたいですね。

【「山崎晴太郎の余白思考 デザイン的考察学」連載一覧】
https://getnavi.jp/category/life/yohakushikodesigntekikousakugaku/
【Information】
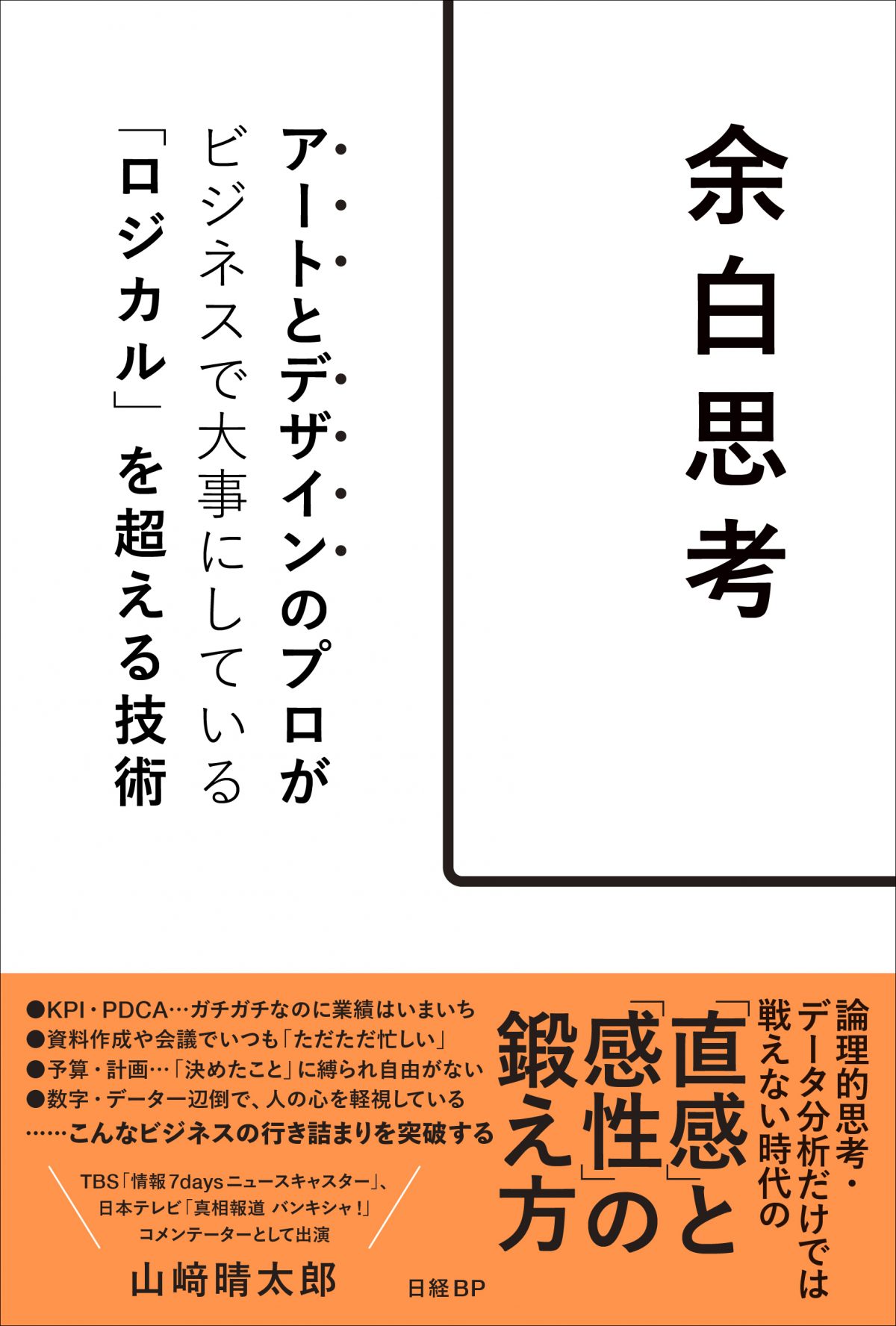
余白思考 アートとデザインのプロがビジネスで大事にしている「ロジカル」を超える技術
好評発売中!
著者:山崎晴太郎
価格:1760円(税込)
発行元:日経BP
Amazon購入ページはこちら
撮影/中村 功 取材・文/倉田モトキ