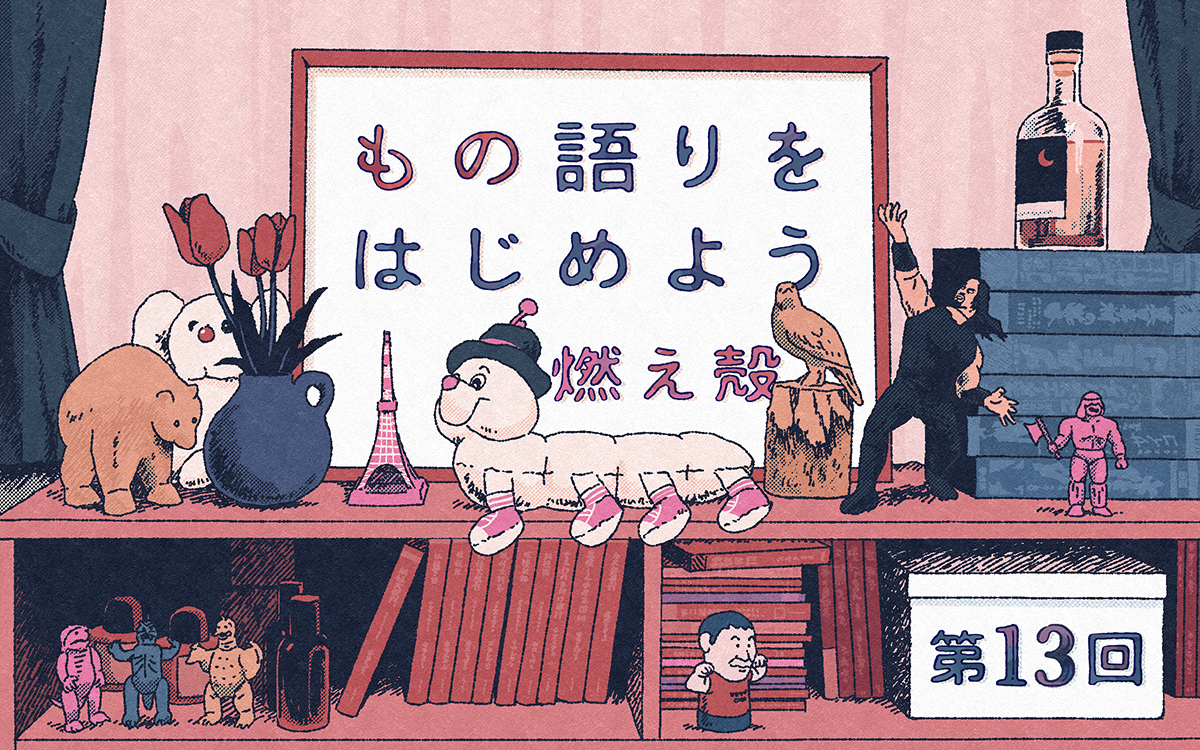第13回「シルバーの指輪」
きっと何かの病気なんだと思うが、どうでもいいときにどうでもいい嘘をついてしまう。誰も得をしない、その場で思いついて、すぐに忘れてしまう程度の下らない嘘。
付き合っていた女性に「あなたはよくわからないときに、つまらない嘘をつくから、本当に腹が立った」と別れ話の途中に吐き捨てられるように言われたことがある。いくら詫びても詫び尽くせないほど、その彼女にはたくさんのつまらない嘘をついてしまった気がするのだが、正直ほとんど憶えていない。それがまた、彼女にとっては本当に腹が立つことのひとつだったということも知っている。
別れ話の途中、「まず一つ目は……」と彼女は僕を睨みつけながら、右手の人差し指を立てた。彼女の右手の薬指には、僕がプレゼントしたシルバーの細い指輪が光っていた。
「私が観てなくて、あなたが観たと豪語していた映画を、後日私が観に行ったら、あなたは観たと言ったことをすっかり忘れて、その映画って面白いの? って私に訊いてきたの。最悪」と彼女。「ごめんなさい」僕はその言葉しか出てこない。
「それで二つ目は……」彼女がそう言い出したところで、「もう勘弁してください」と話の腰を速やかに折って、もう一度深々と謝罪を入れた。

昔からそうだった。「マンションのロビーに銀行強盗の人たちがいた!」と小学校から帰ってくるや否や、ランドセルをソファに放り投げ、急いで母に告げたのを憶えている。
「アンタね。なんでこんな古いマンションのロビーに、銀行強盗が来るのよ! もう一回ロビーまで戻って、銀行強盗なら銀行強盗らしく、ちゃんと銀行を襲ってこい! って言ってきなさい!」母はそう言って、こちらも見ずに怒鳴った。
いま考えるとあの頃、母は僕のどうでもいい、下らない嘘に心底辟易していたんだと思う。子供ながらにぐうの音も出ない母からのツッコミに、僕は言葉がつづかない。僕の頭を一度軽く引っ叩いて、「せめてもっと面白い嘘つきなさいよ!」と母から教育的指導が入った。
それからも学校帰りに殺人鬼に遭遇したとか、死んだ婆ちゃんとコンビニでバッタリ会ったとか、母に対してアイデア出しをするかのように、日々僕は「嘘」のプレゼンを繰り返した。
「アンタ、この仕事があって本当によかったわねえ」前に僕の小説を読んだ母から、そんな感想をもらったことがある。あのときの「嘘」のプレゼンの真価は、いままさに問われているのかもしれない。

別れ話の途中、僕の下らない嘘を指摘した彼女が、「深夜に私が電話したの憶えてる? あなたは三宿の駐車場で気持ち悪くて倒れてるって言ったんだよ」と呆れるように言う。正直まったく憶えていなかった。
「私あのとき、三宿にある駐車場を一つひとつ全部回ったけど、どこにもあなたはいなかった。また嘘だったのかって呆れ返りながらも、倒れてるってことが嘘で良かったって、ホッとしたの」とつづけた。
僕はまたすぐに「ごめんなさい」と言いたかったけれど、もう「ごめんなさい」の在庫が尽きてしまって、なにも言葉が出てこなかった。
あーあ、とため息をするように言った彼女は、「別れてもお互い友達少ないし、たまにはLINEしようよ。私も夜とかすると思うし」と言いながら、右手にはめていたシルバーの指輪をキュキュとはずして僕に手渡した。
「うん。たまに近況報告とかしよう。必ずLINEするよ」と僕は返した。

一度だけ本当にLINEを送ろうと思ったことはあったが、結局、LINEをすることはなかった。僕は彼女にまた嘘をついてしまった。
先日、あのとき返されたシルバーの指輪を、机の引き出しの中からたまたま見つけた。いつか、いやもう近々、処分しなければいけないと思っている。
そういえば、あれから彼女からも連絡は一切ない。「たまにはLINEしてよ。私も夜とかすると思うし」それが彼女の、僕に対してついた、最初で最後の嘘になった。
イラスト/嘉江(X:@mugoisiuchi) デザイン/熊谷菜生