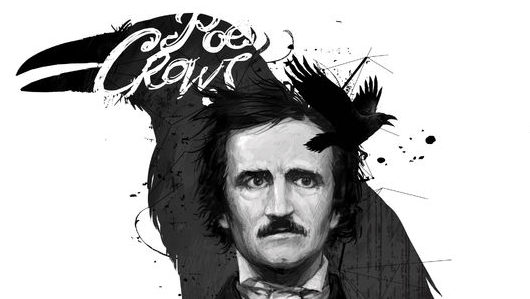子どもの頃から本を読むのが好きでした。けれども、両親は娘の私が読書するのをあまり喜びませんでした。
「また本ばっかり読んで。少しは勉強しなさい、勉強を!」と、小言を言います。読書はあくまでも娯楽であり、あまりに囚われ、淫してはいけない。それが我が家の教育方針だったのだと思います。
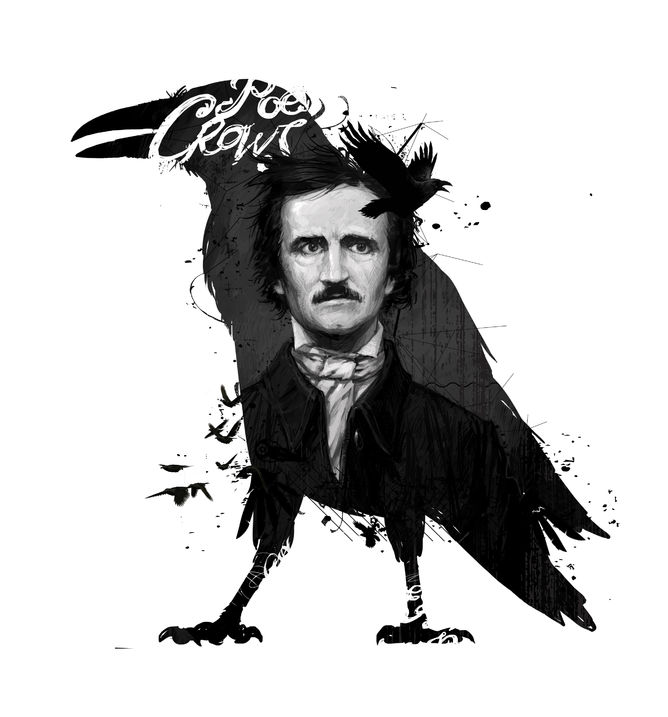
大人になって知ったこと
叱られれば叱られるほど、私は本に耽溺していきました。禁じられるとしたくなるのが人の常…というわけです。
だから、隠れて読みました。押し入れの中に電気スタンドを持ち込み、こっそり読む読書といったら、それはもう最高です。とうとう本を取り上げられても、布団の中で薬の効能書きを読んでいたのですから、ちょっとした中毒症状です。両親が心配するのも仕方が無かったと思います。
そんな私ですが、大人になると文字というものは不自由だと気づき、慄然としました。
翻訳者がいてこそ理解できる外国作品
とくに海外の作品は、制限が多いものだと思い知りました。しばりがきついとでも言ったらいいのか…。どんなに面白い小説でも、言語がわからなければ、文字は紙の上のインクのシミのようなものです。たとえ素晴らしいロシアの小説があっても、ロシア語がわからない私にとっては、「何だか知らないけど、何か書いてある」という感じです。翻訳がなければまったく意味がわかりません。
反対に、涙無しでは読めないような日本の小説も、日本語を解さない人からしたら、不思議な文字の羅列でしょう。絵文字と思う人もいるかもしれません。
考えてみると、これはおそろしく残酷なことです。言葉の違いが、人間と小説の間に立ちはだかっているということですから。そう思うようになってから、私は文字を目で追うのが怖くなりました。ただ楽しんで読んでいた本が、所詮は砂上にある楼閣のようにもろいものだと気づいたからです。
絵画の自由さ
これが絵画となると、しばりはだいぶ弱くなります。
文化的な背景がわからないと、正確に理解できない絵もあることはあります。けれども、言語に比べたら格段にわかりやすいものでしょう。だいたいの人は何を描いてあるくらいはわかります。
そう思った頃から、私は本の挿絵に注目するようになりました。たとえ言葉がわからなくても、空気感のようなものは挿絵の助けによって感じることができます。海外の作品は、正確な翻訳と美しい挿絵があってこそ完成される、私はそう信じるようになったのです。
原文と翻訳と挿絵、その3つが重なり合うとき、なんともいえない不思議な世界が築かれます。『ゴシック名訳集成 西洋伝奇物語』(東雅夫・編/学研プラス・刊)も、この3つが同時に堪能できる作品です。