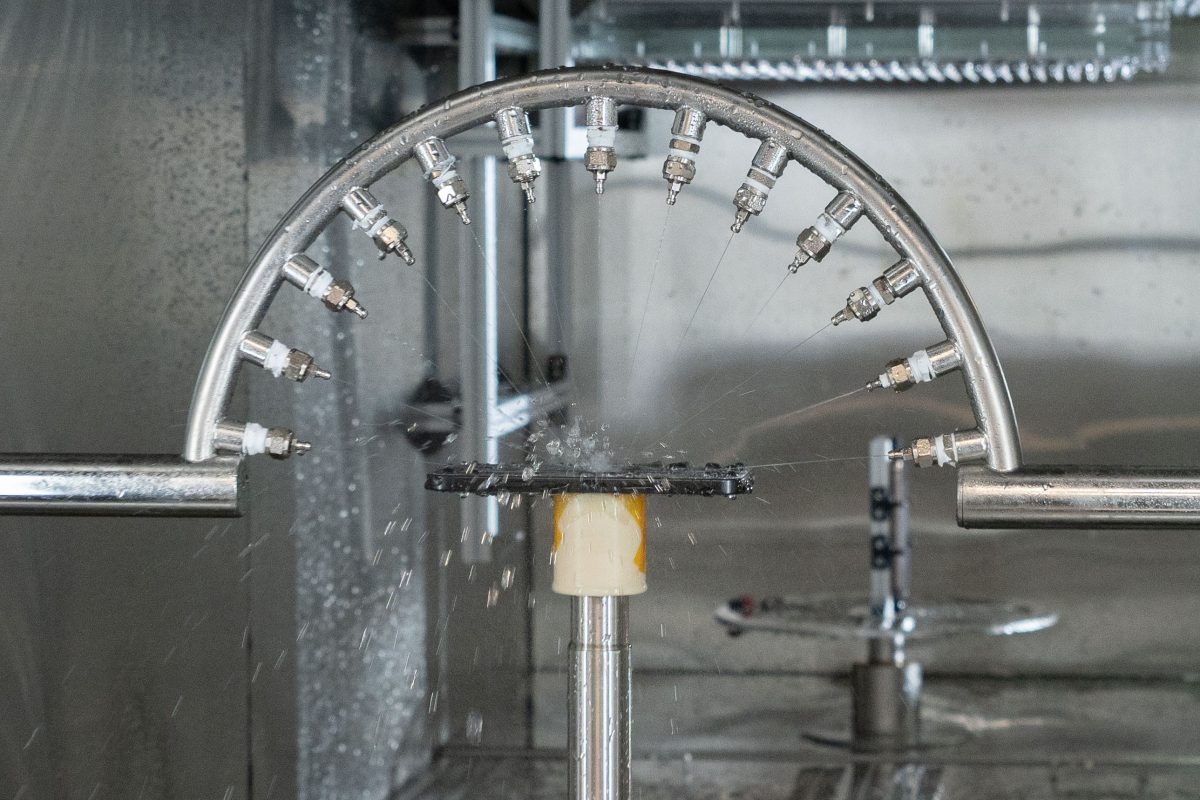Vol.152-4
本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回はApple製品の信頼性を支える、同社の「堅牢性ラボ」の話題。iPhoneやMacの故障を減らすためにどんな試験が行われているのか。
今月の注目検査施設
Apple
堅牢性ラボ
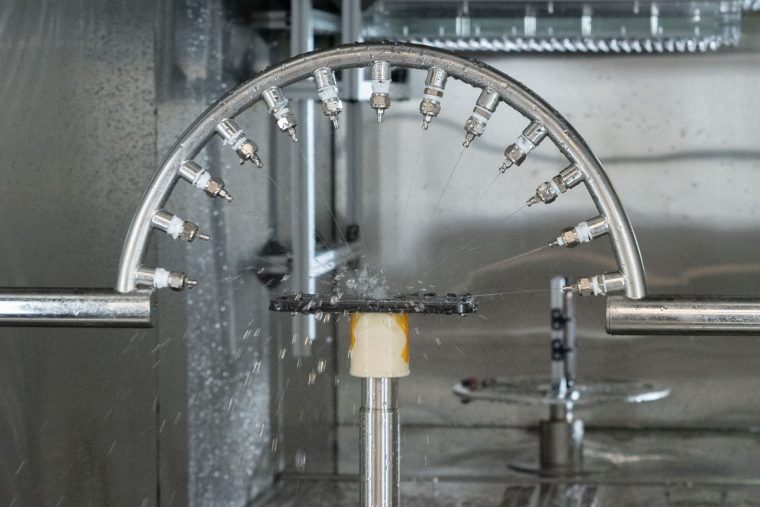
スマホの故障対策は重要なことだ。同時に現在は“修理がしやすいこと”が重視されるようなっている。
例えば多くのスマホでは、バッテリーを両面テープで止めている。工程が簡単であり、安価でもあるからだ。一方で、修理にはマイナスである。両面テープを綺麗にはがし、痕跡をなめらかにしてから再度バッテリーを搭載するには、相応のテクニックが必要になってくる。
だがアップルは、「iPhone 16」と「iPhone 16e」の世代で新しい固定方式を採用した。それが「電気誘導接着剤剥離法」と呼ばれるものだ。
これも両面テープを使っていることに変わりはない。しかし新しい素材では、従来の両面テープと異なり、内部の電極に電流を流すと、1分30秒で“剥がれる”状態になる。
そのあとは吸盤でバッテリーをくっつけて持ち上げるだけで、バッテリーや本体が傷むことはなく、接着剤も残らずきれいに外れる。電流を流すと言っても、市販されている9Vの電池で良い。
この仕組みにより、修理時間は短縮され、修理後のデバイスも内部がきれいな状態に保たれる。すなわち“修理しやすくなる”のである。
修理しやすさが注目され、メーカーも積極的に取り組むには2つ理由がある。
ひとつは、欧米において“修理する権利”が強く主張されていること。法制化も進み、メーカーは“個人に対してもパーツなどを提供し、修理できる環境を整えなくてはならない”状況になっている。その場合には、修理の難易度も下げることが必要になる。
そしてもうひとつの要素が“スマホが長く使われるようになった”ことだ。5年以上同じ製品を使う人も増えているが、そうなるとどこかの修理は必須になってくる。
例えばAppleの場合「Apple Care+」という有料の製品サポートサービスにより、修理コストを下げられる。iPhoneだと、画面が割れると最大で5万円を超える修理代がかかるが、AppleCare+に入っていれば3700円で済む。
利用者にとっては“低価格で修理できる”というメリットがある一方で、Appleにとっては“使っていた期間が明確で、故障に至った経緯の情報もしっかりした故障個体”を手に入れるきっかけが増えるというメリットもある。そうした情報を「堅牢性ラボ」で得られた検証結果を合わせることで、より良い製品作りに生かせる。
そして“長く使える”とは、ひとりの購入者がそのまま同じ製品を使うことだけを指していない。最初の購入者がその製品を中古として売り、さらに新しい製品を買う例も増えているためだ。そうなると、気軽な修理を含め、“状態が良いスマホ”の方が買い取り価格は高くなる。そのことは、結局はスマホの新品購入量増加につながり、メーカーにとっての収益拡大につながる。
そんな流れからも、“壊れにくい製品づくり”と“修理しやすい製品づくり”は連動していて、戦略的に重要な存在なのだ。
週刊GetNavi、バックナンバーはこちら