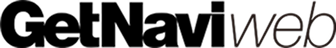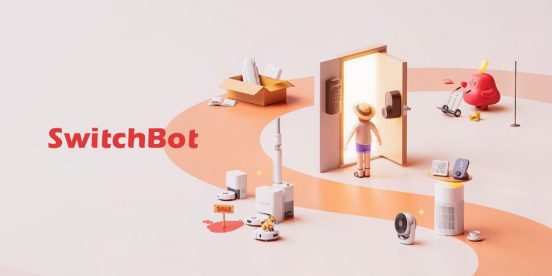発明家には、なぜか若々しい人が多いように思います。電動立ち乗り二輪車「セグウェイ」を開発したディーン・ケーメン氏はその1人。3DEXPERIENCE WORLD 2020に登場したこの発明家は、69歳とは思えないほど溌溂としており、発明家特有の少年の様な目を輝かせ語る姿が印象に残りました。

セグウェイは2001年に発売され、世界中で話題を集めました。当初はスティーブ・ジョブズやジェフ・ベゾスが「人間の移動形態を変える革命的な製品」と褒めたたえたほど。あとになって思えば、この褒め言葉は大袈裟だったかもしれませんが、ケーメン氏は気にしていないかもれません。というのも、同氏はこれまでに数百以上の発明を手がけてきており、特許数は400以上もあると言われているからです。
セグウェイのほかに、代表的な発明品はいくつもあります。インシュリンなどの薬品を一定量ずつ投与できる輸液ポンプ「AutoSyringe」や、汚水を100℃で沸騰させて気化した真水を取りだす浄水器「SlingShot」、筋肉から発せられる電気信号で操作できる電動義手「LUKE arm」などが、世界中で多くの人たちの生活を変えてきました。
そんな発明品を次々と世に送り込んできたケーメン氏の思考は一体どうなっているのでしょうか? 現在、世界中で流行している新型コロナウイルスは私たちの働き方や消費行動を大きく変えていますが、このような変化がこれから数十年間、イノベーションを形作っていくと言われています。未来の技術革新や発明について考えてみるという意味合いでも、ケーメン氏の物の見方について3DEXPERIENCE WORLD 2020での講演をもとに明らかにしてみたいと思います。
点と点をつなぐ
ケーメン氏は、1982年に設立した企業DEKAで、いまでこそ400人以上のエンジニアとともに多数のプロジェクトを動かしていますが、もともとは何も計画していなかったそうです。
「計画やビジネスプランなんて何もありませんでしたが、機会だけは見えていました。目の前に良いテクノロジーと良い人材があり、これらを活かせないかと。そこでこの離れている点と点をつないだのです。失敗したときもありますが、大体うまくいきました」とケーメン氏は言います。
点と点をつないで成功した最初のケースがAutoSyringeでした。ケーメン氏は大学生だったころ、医学部に通う兄から、赤ちゃんに点滴で薬を与える際に、その量を調整できる器具がないという不満を聞きます。それに興味を持ったケーメン氏は早速、自分で薬品を一定量ずつ投与できる器具を作ってみたのでした。その行動の目的はお金儲けではなかったと言います。
これが機縁となりました。「兄がその器具を別の病院に貸しているうちに、糖尿病患者用のインシュリン投与に使えるのではないかと提案してきた人がいました。そこで、私は多くの人を助けるためにAutoSyringeを作る会社を設立することに決めたのです」(ケーメン氏)
新しいものを生み出した結果、医療業界で技術革新が起きましたが、発明とイノベーションは似て非なるもののようです。「発明よりもはるかに難しいのがイノベーション。というのも、イノベーションは発明されたものの価値を一般の人たちに理解してもらう必要があるからです」と言うケーメン氏。「一般の人々はすごく保守的です。それ自体は社会を安定させるうえでも悪いことではありませんが、問題なのは悪いことに対してだけでなく、良いものに対しても保守的であること。したがって、イノベーションを起こすには、新しい発明を普通の人たちにも理解してもらえるよう十分に説明することが求められます。そのために私はさまざまな組織や政治家、ビジネスリーダーとコネクションを作ることに奔走してきました」
この洞察は示唆に富んでいます。発明家は発明のことだけ考えていればいいのではなく、発明が世間に受け入れられるために行動もしなければならない。これができて初めてイノベーションである、とケーメン氏は主張しているのです。
この点については、別の興味深い事例もあります。ケーメン氏はアフリカやインドの農村部で浄水器のSlingshotを普及させたいと考えていました。きれいな水を必要としているアフリカやインドの農村地帯にSlingshotを届けるにはどうしたらよいのか? しかも、ただモノを届けるだけでなく、Slingshotの使い方や定期メンテナンスについて現地の人々に教える必要もありました。医療メーカーは農村部までサプライチェーンを持っておらず、その役割を担わせるには無理があります。
あれこれ考えるうちに、ある企業のことが頭に浮かんできました。コカ・コーラです。ケーメン氏は直ちに同社の経営者に相談し、黒色の箱型のSlingshotを持って会いに行くと、相手は二つ返事で引き受けてくれました。しかし、1つだけ条件があったのです。「浄水器の色を黒からブランドカラーの赤に変えてくれませんか?」とケーメン氏は問われました。そうして、赤いSlingshotが生まれたそうですが、この話は製品のデザインや他社とのコラボレーションの方法についても参考になりそうなケースです。