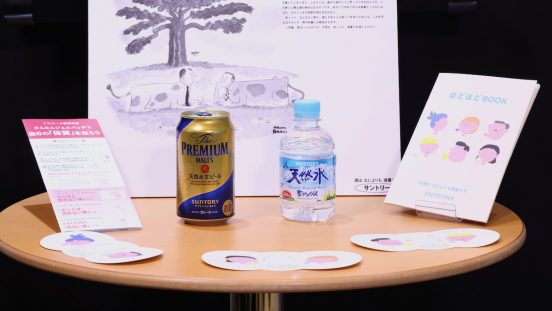居酒屋でよく飲む人なら、「あ、あのお酒だ!」と気づいたかもしれません。それが、2月18日に発売された「サッポロ 氷彩サワー1984」。開発者も参加した体験会にて、味のレビューはもちろん、製法へのこだわりや開発の裏話を取材してきました。

サッポロ
サッポロ 氷彩サワー1984/サッポロサワー 氷彩1984 素
350ml缶 148円/500ml瓶 650円(税抜)
目次
適度な甘みや酸味が調和。軽やかで奥深い爽快サワー
商品名に「1984」とあるように、「サッポロサワー 氷彩 1984」のルーツは、1984年に発売された蒸留酒「サッポロホワイトブランデー 氷彩」にあります。のちに飲食店向けの「氷彩サワー」として進化し、今もなお全国の居酒屋で支持されているロングセラーです。

氷たっぷりで香る、フレッシュな香味と絶妙なバランス
「サッポロ 氷彩サワー 1984」はワインを蒸留したホワイトブランデー仕立てであることが特徴。まずはどんな味かをレビューしましょう。氷をたっぷり入れたグラスに注ぎ、飲んでみました。

まず、香りの第一印象はみずみずしい柑橘系。レモンサワーのような直球の香りではなく、ふんわりと自然に立ちのぼるアロマが心地よいです。炭酸は強すぎず、適度なガス圧が爽快さを引き出しつつも飲み疲れしにくい仕立て。味わいの軸には、すっきりしたまろやかさがあり、ほんのりとした甘みが全体をまとめています。

アルコール度数は7%としっかりめ。しかし、重たさやクセはなく、口当たりの良さが際立ちます。パッケージに「軽やかで奥深い」と記されている通り、甘み・酸味・アルコール感の三要素が高い次元でバランスされており、「飲みごたえがあるのに軽い」という絶妙なギャップを実現。飽きずにおかわりしたくなるおいしさです。
和洋中どれとも合う。“料理に寄り添う”サワーとしての完成度

この「氷彩1984」は、どんな料理とも相性が良く、特に居酒屋のおつまみとは抜群のペアリングを発揮します。牛すじ煮のような甘辛い料理から、いくらや揚げ物まで、さまざまな味付けと見事に調和。甘みや酸味が料理の味を引き立てつつ、炭酸のキレが脂っぽさをさっぱりと流してくれます。

飲食店文化とともに育った“万能サワー”という設計思想
やはり、居酒屋を主戦場としてきたDNAはさすがの一言。外食シーンに「氷彩サワー」が親しまれていった昭和~平成は、ファミレスや総合居酒屋チェーンの黄金時代。おつまみは、和洋中にエスニックとなんでもアリだったわけで、そうした多彩な味付けの料理と幅広く合うよう味が設計されているのです。「サッポロサワー 氷彩1984」のストライクゾーンの広さにも納得です。
なぜホワイトブランデー? 開発者が語るこだわりのルーツ
今回の体験会には、「氷彩サワー1984」の開発を担当したブランドマネージャー・森田隆文さんも参加。

筆者が気になったことを聞いてみました。なぜ「氷彩」はホワイトブランデー(ウォッカと一部ブランデー)を特徴としたのでしょうか?
というのも、サッポロの定番である「濃いめのレモンサワー/グレフルサワー」や「ニッポンのシン・レモンサワー」のベースはウォッカ。その他市場の缶チューハイも多くは、ウォッカ、または甲類焼酎というのが主流。約40年前から振り返っても、スタンダードなブランドにホワイトブランデーを使うのはかなり珍しい気がするのです。
「当時の詳細が残っておらず、正確なことはわからないのですが、ひとつはブランデーへの新たなチャレンジがあったと考えています。例えば、王道のブランデーは樽熟成が生む重厚な香りや味が特徴のひとつですよね。ただ、『氷彩』は木樽ではなくステンレスタンクで仕込んだホワイトブランデーですから」(森田さん)
ホワイトブランデーは、まろやかでありながらもクリアでフレッシュな香味が魅力のひとつ。40年以上前、「氷彩」を生み出した開発チームは、木樽熟成のブランデーとは異なるこの味わいに新奇性を見出し、他の商品との差別化として打ち出したのかもしれません。
ちなみにこの味わいについて発売前に行った試飲調査では、プレーンサワーの味に対して73%の人が「ギャップがあった」と回答。それは悪いギャップではなく、73%のうち96%の人が「思ったよりも飲みやすくておいしい」と答えたとか。
他の3倍以上の試作回数。試行錯誤の末にたどり着いた味
同じく参加した開発担当の岩佐拓幸さんには、味づくりについて聞きました。今回、飲食店で愛されてきた味わいを缶の「サッポロサワー 氷彩1984」として発売するにあたり、難しかった点を挙げるなら?

「やはり味覚バランスですね。レモンや梅といった明確な味素材がありませんから、例えば甘みを落としていくと酸味が際立ってくるなど、バランスを考えながら調整する必要があります。そのうえ缶は缶で独自のアルコール度数や炭酸の強さで設計しますし、とにかく丁寧なチューニングが必要でした」
岩佐さんは、『濃いめ』ブランドや『男梅サワー』なども担当してきたそう。
「いままで担当した商品と比較すると、この『サッポロサワー 氷彩1948』は缶のほかに樽や素のビンも含めて3倍以上の試作回数に上ったと思います。それだけ細かく検証し、商品化に至りました」(岩佐さん)

店主が語る“甘み”の意義と、うまみとの関係
飲食店という顧客接点から長年「氷彩」ブランドに親しんでいる、「民家」の店主、大和田政晴さんにも「サッポロサワー 氷彩1984」の感想を聞きました。

「『“氷彩”の魅力は、その甘みにあると思います。そもそも甘みはうまみに含まれるもので、料理のおいしさにも欠かせないものなんですね。私も調理において、甘みは最も大切にしています。そして甘みがないと、酸味や辛味やすっきりしたキレなども演出できません。『サッポロサワー 氷彩1984』の爽快感の奥に感じるうまみも、甘みが出してくれているのだと思います。だからこそ料理にも合うのだと思いますし、ぜひうまみとの調和を感じてほしいですね」(大和田さん)

奇しくもサッポロで「1984」といえば、同社が1984年に開発し、いまや世界中のブリュワーから人気となっている伝説のホップ「ソラチエース」を使った「サッポロ SORACHI 1984」もあり、「サッポロ 氷彩サワー 1984」にも熱量を感じます。
また、4月15日からはさっそく限定品で「サッポロサワー 氷彩1984 晴れやかライム仕立て」が発売に。今後も新フレーバーなどが登場する可能性は高そうで、目を離せません。