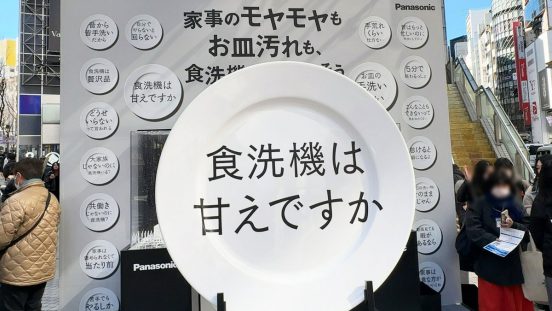パナソニック サイクルテックは、16歳以上なら誰でも免許なしで運転できる、特定小型原動機付自転車「MU(エムユー)」を2025年12月から発売すると発表しました。長年培ってきた自転車開発のノウハウを、パナソニックとしては初めてこのカテゴリーに活かすこととなります。発表当日に試乗する機会も得られ、今回はそのインプレッションを交えてご紹介します。
ほぼママチャリにしか見えないスタイルで特定小型原付を実現
パナソニックが自転車事業をスタートさせたのは、社名が松下電器時代の1952年のこと。その後、1980年には国内第一号の電気自転車(原動機付自転車)を発表し、96年にはナショナルとして初の電動アシスト自転車を発売。この間、同社は73年にわたって自転車を提供し続けてきました。今回発表したMUはこうした長年のノウハウを活かした製品として登場したものです。


MUを前にして実感するのは、特定小型原付自転車としながらも、そのフォルムは一般的な電動アシスト自転車とほぼ同じにしか見えないことです。
しかし、あえてこのスタイルを採用したとはパナソニックの弁。ママチャリでもよく見かける“U字型”フレームは乗り降りがしやすく、停車時の足つき性がいいというメリットがあります。これは万一、転倒の危険があるときにも対応がしやすく、安全性も高いということでこのフォルムが採用されたのです。

タイヤサイズも前後とも20インチと、これまたママチャリと同等のサイズ。これは他社の特定小型原付自転車と比べると大きめなサイズで、段差などの乗り越えを重視したことが理由。
特定小型原付自転車としては電動キックボードなどさまざまなタイプが登場していますが、車輪が小さいとどうしても乗り越える能力は低くなり、それが要因で転倒する危険性も高くなります。ママチャリ並みにタイヤの大径化を実現したことで、安全性がおのずと高まるのは間違いないでしょう。

「車道モード」と「歩道モード」の2つのモードを用意
走行するにあたってMUでは、「車道走行モード(以下:車道モード)」と「歩道走行モード(以下:歩道モード)」の2つのモードが用意されました。特定小型原付自転車についての詳細は後述しますが、これまで原動機付自転車で歩道を走行することはできませんでした。しかし、特定小型原付自転車では“特例”の基準を満たすことにより歩道走行を可能としたのです。
もちろん、MUではこの“特例”に適合しています。方向指示器を兼ねた前後4つのランプを備え、車道モードでは緑色に点灯し、歩道モードになると緑のまま点滅に切り替わります。最高速度は車道モードで20km/h、歩道モードでは6km/hに自動的に抑えられる仕組みです。
また、後部にはストップランプ機能を合わせ持つテールランプを装備。その下には特定小型原付自転車用のナンバープレート装着用フレームも用意されました。



MUは電動で走行できる乗物ですから、電動アシスト自転車のようなペダルはありません。足を乗せるための足置きがあるだけ。ハンドルバーの右にあるスロットを回すだけで発進し、そのままモーターによって走行できます。つまり、フォルムが基本的に電動アシスト自転車と同じMUは、“漕がずに乗れる自転車”とも言えるわけです。
一方でMUは、パナソニックが電動アシスト自転車で採用していたパーツが数多く流用されています。前後のブレーキも自転車からの流用で、前輪はリムブレーキ、後輪はハブブレーキとしました。
これは自転車店でのメンテナンスしやすさを考えたのと、後輪をハブブレーキとすることで雨天時でも安定して止まれる安全性を重視したのだと思われます。バッテリーも電動アシスト自転車で使われていた容量16.0Ahのものを流用しており、これで1充電あたり最大で約40kmを走ることができるそうです。

購入は全国の自転車販売店で。ナンバー登録と自賠責は必須
では、このMUを購入するにはどうすればいいか。実は特定小型原付自転車は一部の量販店で取り扱いもありますが、多くは近所の自転車店で購入できるものではありませんでした。しかし、パナソニックにはこれまで自転車店で販売してきた実績があり、MUの場合もそのルートを使うことになりました。
これにより、いままでの自転車と同じように自転車店で購入し、メンテナンスもそのお店で実施してもらえるのです。これはユーザーにとっても大きなメリットとなりそうです。
注意すべきは、MUは原動機付自転車の枠内に新設されたカテゴリーであり、ナンバー登録や自賠責保険への加入は必須となっているということです。年間2000円の軽自動車税を支払う必要もあります。また、ヘルメットの着用は自転車と同様、努力義務となっていますが、安全を第一に考えれば着用は必須と思うべきでしょう。さらに保険についても、できれば任意保険の加入をオススメします。自動車保険の「ファミリーバイク特約」であれば、割安に加入することができます。
次に納車までの手続きですが、パナソニックではまず販売店で本人確認のためにマイナンバーカードか運転免許証を提示し、そのうえでネット上の「安全利用ガイド」を視聴してテストを受けることを必須としています。このテストに合格したら、その画面をキャプチャーして店頭に提示するのです。
一方、特定小型原付自転車のナンバープレートは各市町村役場へ出向いてユーザー自身が取得し、合わせて自賠責保険は損害保険代理店か、コンビニなどで加入します。そしてナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼り、これを販売店に提示することでめでたく車両が受領できるというわけです。なお、パナソニックによればこれらを代行してくれる販売店も一部にはあるので、相談してみてほしいとのことでした。
車道モードでは時速20km/hまであっという間。直進性にも優れる
試乗は、東京都江東区にある東京オリンピック2020でボート/カヌーの競技場として整備された「海の森水上競技場」の、観客席前にある150mほどの特設コースが使われました。平坦な舗装路で坂道はありません。
MUに着座してみると、その姿勢はママチャリと変わりません。ステアリングバーの左右にはブレーキレバーがあって、左側にはシステム用操作ユニットがありますが、これは電動アシスト自転車もほぼ同じで、着座した印象としてはほとんど変わらないのです。

そんななか唯一違うのが、右側のグリップ部にアクセルとなる回転式スロットがあること。つまり、オートバイと同様、これを回転させることで速度の調節ができるのです。気をつけなければいけないのは、システムの電源を先に入れてしまうと乗車時にこのスロットを動かしてしまい、不用意に発進を招きかねないということです。なので、システムの電源は乗車してから入れるようにすることをオススメします。

まずは車道モードで走ってみました。スロットを回すとスルスルッと速度が上がり、あっという間に20km/hに到達。路面状態がよかったこともあり快適に走行することができました。加速力も十分で走りに力強さを感じさせます。
試乗では坂道がなかったので確証はできませんが、このパワー感からしてアップダウンのある公道でも十分な走りを見せてくれる気がしました。また、走っていて実感したのは直進性の素晴らしさで、これは明らかに20インチの大径タイヤを採用した効果だったと思います。

ブレーキ性能も十分な能力を感じました。試乗する前は自転車からの流用で大丈夫なのか? とも思っていましたが、実際に走ればそんな不安はまったくなし。自転車と同様、前後ブレーキを上手に組み合わせることで安定して停止することができました。
考えてみれば、車重そのものが電動アシスト自転車と同等なのですから、その対応力は十分検証済みということなんだと思います。

歩道モードを用意するものの、「MUは車道を走るための乗りもの」
次に歩道モードへ切り替えてみます。その場合は、法規上に沿って、MUも一旦停止しないと切り替わらない仕組みとなっています。しかも歩道へはその手前で切り替えなければいけません。万一、車道モードのまま歩道に入ると、その時点で違反となりますので注意してください。
歩道モードでの最高速度は6km/hです。人が早足で歩く速度であり、歩道を走行するうえですぐに停止できる速度ということで、この上限が決められたようです。
ただ、正直なところ、この速度で真っ直ぐ走るのは容易ではありませんでした。前を向いてなんとか真っ直ぐ走らせようとしてもふらつきが発生し、個人的にはこの速度で歩道を走るのはかえって危険なのではないかと思ったほどです。
この件についてパナソニックに訊ねると、「歩道モードは用意していますが、MUは原則、車道を走るための乗りものだとお考えください」とのこと。とはいえ、日本の道路事情を鑑みれば、車速の高い車両が背後からどんどん迫ってくると、その速度差から恐怖を感じることは否めません。周囲の交通状況を判断しつつ、上手に付き合っていくことが必要なのかもしれません。
特定小型原付自転車は、走行上のルールが自転車と異なっていることに注意
最後に特定小型原動機付自転車とは、どんな乗物なのかを改めてご説明しておきます。
この乗物は2023年7月11日に新たに定められた交通ルールの下で運用されているもので、16歳以上であれば運転免許不要で運転できるのが最大のポイントです。なので、高校生が通学に使ってもいいですし、免許返納した高齢者にとっても最適な乗り物になると期待されています。
搭載する電動機の定格出力は0.6kW以下にする必要があり、最高速度は20km/h以下で、原則、車道を走行します。また、走行する際はヘルメットが努力義務となっているものの、自賠責保険への加入やナンバープレートの装着は義務化されており、税金も軽自動車税種別割として年間2000円ががかかります。
そして、ここからが少しわかりにくいのですが、この特定小型原動機付自転車は原則、車道を走行することになっているところ、一定条件を満たした“特例”特定小型原動機自転車になると、最高速度6km/h以下で歩道を通行することができるのです。
ただし、この歩道とは「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識などが設置されている歩道に限られます。また、車道の右側走行は逆走になり完全禁止とされています。
今回発表されたMUはこの“特例”特定小型原動機付自転車の基準を満たしており、車道モードと歩道モードを切り替えることで、車道と歩道の両方を走行できます。つまり、MUは自転車のような手軽さで、電動バイクとしての快適さも合わせ持つ新しい乗りものなのです。正しい交通ルールの下、より多くの人に乗ってもらえることを期待したいと思います。