現代は、あらゆる文章をAIでまかなえてしまいます。だからこそ、読み手との関係を踏まえた「ならでは」の文章を書ける人が活躍できる時代にもなっています。
例えばメールの書き方一つとっても、成果を出せる人と出せない人との間には大きな違いがあります。他者やAIと差をつけ、「伝わる文章」を書くための3つのテクニックを、出版社ワン・パブリッシングの松井謙介取締役社長に聞きました。この後送るメールに、すぐ応用できるはずですよ!
開始から10秒で取材終了!? 松井社長からまさかの一言
――世はまさに“大AI時代”です。9月24日発売の、松井社長の文章術本『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』(マイナビ出版)も、まさしくAIを意識していますよね。誤字脱字のない正確なメールを作るのはAIのほうが得意そうですが、差をつけるにはどうすれば良いでしょうか?
松井:意外に思われるかもしれないけど、私はメールが苦手で。実はCopilotに書かせることもあるんです。
――……取材はもう終わらせた方がよいでしょうか?
松井:いやいや(笑) AIに「0から全部書いて」と丸投げしてはいませんよ。伝えたい内容の骨子を5割くらい自分で書いたうえで、あとはCopilotに形を整えてもらったり、誤字脱字のチェックをしてもらったりしています。いまはメールのツールバーにCopilotボタンがあるので、時間をかけずに質の高い文面を作る有効な手段として、活用すればよいと思いますよ。
――AIとうまく共存するのが大事だということですね。
松井:まさしくそうです。ただ「0から1」の部分は、AIには生み出せない。そこはメールを書く人の体験、感情が重要になります。つまり「生成」させるより、「今あるものの、形を変える」アシスタントとして頼るのが良いだろうと。
例えば、PowerPointで作った20枚の企画書をPDF1枚にまとめてもらうとか。企画書は膨大になりがちなので、読み手に敬遠されるリスクがあります。そういうときに「お忙しかったら、こちらのPDF1枚をご覧いただくだけでもいいですよ」と、エッセンスだけ抜き出した資料もあわせて添付しておけば、見てもらえる可能性がグッと高まりますよね。
相手にとってより良い選択肢を増やすためのAI活用、おすすめです。

「伝わるメール」はこう作る! 今すぐ使える3つのテクニック
――AIに任せるのは「成形・チェック」だとして、どうすれば「伝わる文章」を書けるようになりますか? 今すぐメールで使えるテクニックを教えてください。
松井:①パーソナルな一言を添える、②文章を書く前に下調べする、③文量は少しでも短くする、この3つですね。人間ならではの「着眼点」や「情報収集」、そして相手への「共感力」が、文章の質を大きく左右すると思います。
①は、言い換えると「あなたに向けて書く」ことです。これが非常に大切。特に、1対1のメールならなおさらです。
例えば、前夜に食事でご一緒した方がいたとして、「昨日はごちそうさまでした。おいしいお店でしたね」みたいな、いわゆる“テンプレメール”を書くのはもったいない。それこそAIにでも作れる文面だからです。
私なら「メインディッシュを食べているときの〇〇さんの表情が最高でした」とか「あそこの店員さん、蟹によく似ていましたね」とか、 共有した時間の一瞬をちゃんと切り出して、具体的に書くようにしますね。その共有した一瞬が、書き手と読み手の関係を深めてくれる、これは間違いありません。
――「私だけに送られたメール」だと感じて、グッときます。確かに、印象的だった出来事の共有はAIにはできないですね。
松井:薄っぺらい定型文じゃなく「パーソナルな一言」を添えることが、信頼関係を築くうえでとても重要なんです。
会ったことがない人にメールするのなら、まずは情報を探して、相手が「言われたら嬉しいこと」を想像して書くようにしますね。その人が制作した作品があれば、少しでも見て感想を添えるとか。かといって、今の時代Facebookなどを深堀する「やりすぎホットリーディング」は少し危険。初めての人にはあまり深い内容を書かないほうが好印象でしょう。
――相手を喜ばせたくて、感想をたくさん書いてしまいそうです。メールの長さはどのくらいが理想的でしょうか。
松井:スクロールせず、一画面に収まる程度でしょう。開いた瞬間、内容うんぬんの前に「長い!」と感じるメールだと嫌になるじゃないですか。長すぎるメールは、①人の時間を奪う罪、②要点がよくわからない罪、③同じくらいのテンションで文章を返さないと、自分が手抜きしているように感じられるんじゃないかと思わせる罪……この3つの罪に問われることになります。
だから、長々と書くよりは簡潔にまとめる方が良い。冗長な表現がないか、一文が無駄に長くないかをチェックすることも大切です。個人的には、短いメールを何通もやり取りする方が、コミュニケーションもスムーズに進むと思いますね。

文章力の価値は「爆上がりしますよ、と言いたいところですが……」。ポツりと漏らした本音
――今回は「メール」にフォーカスした取材でしたが、文章力を問われる場面は他にも多くあります。AIの進化に伴い、「文章力」の価値はどう変化していくでしょうか。
松井: 難しい質問です。以前、ある講演で「手書き」について話をしたことがあります。昨今はデジタル入力が主流だからこそ、手で書いた文字の価値は上がるだろうと。ただ実際には、手書きは「芸術」の領域というか、「習字」のような存在になってきていると感じるんですよね。
そうなると人が書く文章についても、評価が難しいかもしれませんね。「価値が爆上がりしますよ」と言いたいところですが、なんとも評価は難しい。この書籍を人に紹介したとき「えっ、松井さん全部自分で書いたんですか!」と驚かれたんです。私としては当たり前なのに、もはや自分で書くことが「伝統芸能」のようになってしまっているんだな、と。
――だとすると文章力は、あまり重要なスキルではなくなってしまいそうでしょうか。
松井:いえ、人間が書く文章は「安心感」や「信頼感」という形で価値が出てくるでしょうから、もちろん価値はあります。
AIが作った文章は、ある意味「食品における添加物」のようなものかもしれません。私は添加物を毛嫌いしませんし、食生活を豊かにするものだと思っています。AIが作った文章も同様に、世間に受け入れられていますよね。
一方で、「無添加です!」の言葉に、妙な安心感、信頼感を覚えるのもまた事実。そう考えると、これから人間が書いた文章は「無添加文章」もしくは「オーガニック文章」といった存在で、ちょっとした安心感が得られるアウトプットになっていくのではないか、という気がしています。書籍の帯に「人が書きました」とか「無AI」とか マークが入る時代が来るかもしれませんね。
――『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』も、「松井さんが書いているなら読んでみようかな」と、“人(著者)由来”で買ってくれる方がいるかもしれないですしね!
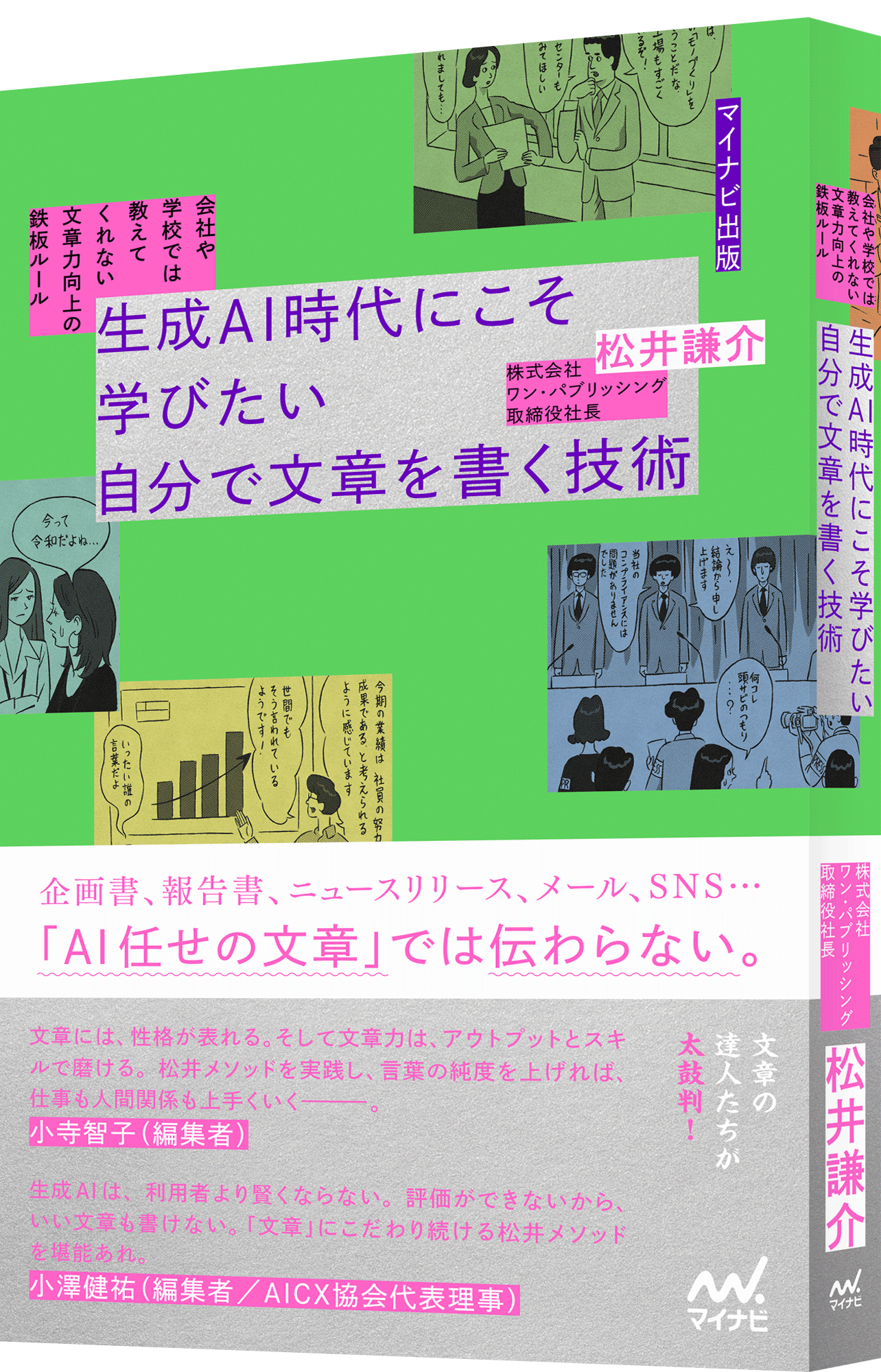
――同書について、最後にもう少しうかがわせてください。AIありきの現代に即した文章術本ですよね。帯に、AIのプロ(小澤健祐/AICX代表理事)からの推薦コメントも載っています。
松井:AIを否定するのではなく、アシスタントとして賢く活用しながら、人間ならではの感性や経験を文章に込めることが、これからの時代に求められる「文章力」なんじゃないでしょうか。
書籍で様々なテクニックをご紹介していますが、文章作成は「書く前の事前準備が9割」と私は思っています。情報を仕入れ、面白いポイントに着眼して、それを「どう形にしようか」と考えるのが実は文章の本質ではないだろうかと。
「キーボードを前にすると頭が真っ白になって、何を書いたら良いかわからなくなるんです!」と悩む人は、そもそもの情報収集が足りておらず、頭が真っ白な「まま」書き始めている可能性が高い。書き始められない原因は「文章力がないから」ではないんです。 メールを送る前に「昨日どんなことを共有したかネタをいったん棚卸ししろ!」とお伝えしましたよね。書き始める前に取るアクションこそが、「伝わる文章」づくり、ひいては文章力アップのカギを握っています。
本書を通じて、「ちょっと文章が書きやすくなったかも」「これなら自分で書けるかも」と実感を得ていただければうれしいですね!



















